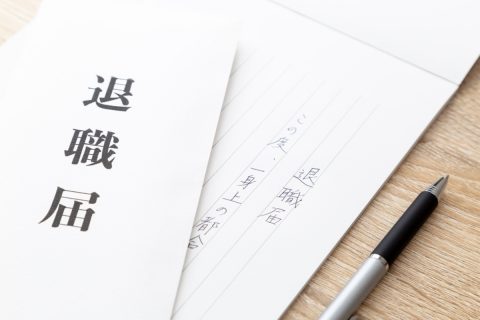
「退職代行」を使って会社を辞めようと思います。今の会社は退職金制度があるのですが、退職代行を使った場合でももらえるのでしょうか?
4月4日(金) 21:20
退職金制度は必ずあるべき制度ではない
大前提として、法律上、企業に退職金制度を設ける義務はありません。ただし、多くの企業では就業規則において退職金にまつわるルールを設けており、それぞれのルールに基づいて退職金が支給されます。つまり、退職金の有無や金額、支給条件は、企業ごとに異なるのです。
退職代行を利用すると退職金はもらえない?
近年流行している「退職代行サービス」を利用すると、退職金が受け取れなくなるのではと心配する方もいますが、基本的にそのような心配をする必要はありません。退職代行を利用したことが理由でも、退職金は支給されるからです。
退職代行を利用しても、会社の退職金規程に定められた支給条件を満たしていれば、退職金を受け取る権利があります。
退職代行を利用する際に退職金について注意したいこと
退職代行を利用して退職を検討している方で、退職金を受け取れるか不安に感じている方は、以下のポイントを押さえておきましょう。
退職金制度があるかを確認する
退職金制度は、法律によって会社に義務付けられているものではありません。退職金があるかどうかは、従業員と勤務先である企業の契約内容によって定められています。
厚生労働省の「令和5年 就労条件総合調査」によれば、日本国内の企業のうち74.9%が退職給付(一時金・年金)制度を設けている一方で、24.8%が設けていません。
設けていない企業のうち、1000人以上の企業が8.8%に対し、30~99人の企業が29.5%という結果となり、企業の規模が大きくなればなるほど制度として整備されている傾向にあるため、退職金制度を設けられない企業があることも理解しておきましょう。
勤め先の退職金についてのルールを確認する
退職金の支給条件としては一般的に、「勤続年数」「退職理由」「就業規則に定められる特定の条件」などが挙げられます。
多くの企業では、一定の勤続年数を満たしていることを退職金支給の条件としていますが、具体的な年数(3年以上など)は企業ごとに異なります。まずは、自社の規程で定められている、勤続年数を確認してください。
自己都合退職か会社都合退職かによって、退職金の金額が異なる場合もあります。自己都合で退職する場合は、どの程度の退職金が受け取れるのかを確認することが重要です。
また、懲戒解雇された従業員に対して退職金を支給しないといった、不支給条件を定めているケースも珍しくありません。退職金が減額されたり、支給されなかったりする条件も、事前に確認しておくと安心です。
会社が退職金の支払いを拒絶する恐れもある
退職金制度の条件を満たしているにもかかわらず、退職金の支払いを拒否されるケースも少なからず存在します。万が一そのような事態に陥った場合は、労働問題に精通している弁護士に相談することをおすすめします。
一般的な退職代行サービスは、本人に代わって退職の意思を会社に伝えることが主な業務であり、法律上の交渉行為をすることはできません。しかし、弁護士法人や労働組合が運営する退職代行サービスであれば法的な権限を持っているため、退職金の請求や未払い賃金の交渉まで対応してもらえるのです。
退職金を確実に受け取りたい場合は、弁護士法人や労働組合が運営する退職代行サービスの利用を検討するようにしましょう。
信頼できる退職代行サービスを見つけて退職金を受け取ろう
退職代行サービスを利用しても、退職金制度の条件を満たしていれば、退職金を受け取ることは可能です。ただし、退職金の支給条件や金額は企業ごとに異なるため、事前に就業規則や退職金についてのルールを確認する必要があります。
また、退職代行サービスを利用する際は、信頼できる業者を選ぶことが重要です。退職についてもめたり、退職金の支払いを拒否されたりするなどのトラブルに発展した場合は、必要に応じて労働問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
退職手続きをスムーズに進めるためにも、弁護士法人や労働組合が運営する退職代行サービスの利用を検討しましょう。
出典
厚生労働省 大阪労働局 退職金等について
厚生労働省 令和5年就労条件総合調査結果の概況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
失業手当ってどれくらいもらえるの? 知っておきたい受給額と手続き方法失業手当は退職理由で給付総額が大きく変わる! 押さえておくべきポイントは?
自己都合と会社都合で失業手当の支給時期が違うって本当?

新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55





























