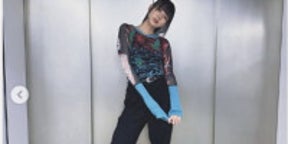写真はイメージです
体育会系人材は時代遅れになるか?AI時代に求められるアスリート人材の力
3月18日(火) 23:48
提供:
「体育会系の学生が就職活動で超人気企業から内定をもらった」「体育会系出身の営業マンがトップセールスを獲得した」--誰にも、周りにそんな「体育会系人材」が一人や二人いるのではないだろうか。
「体育会系人材ほど、会社で活躍できる可能性を秘めた人材はいません。体育会系の部活動やスポーツクラブは、社会の縮図といえます」
そう話すのは、『アスリート人材の突破力 ~才能を引き出す気づきの法則~』などの著書を持つ、資産防衛・ビジネスコンサルタントの松本隆宏さんだ。
社会に出てから活躍する体育会系人材
「体育会系では上下関係や同期との横のつながり、あるいは地域とのつながりを通して、さまざまな人間関係を学びます。また、スポーツは肉体のパワーだけでは絶対に勝てません。計画や戦略・戦術などゴールから逆算して考える力が必要になります。それらは監督やコーチに言われたことをただ単に覚え、その通りに動く力ではありません。監督やコーチが指導したこと、経験したことを時に批判的に捉えながら『自ら思考し動く力』です。すなわち、ビジネスでも必要とされるPDCAそのものなのです」(松本さん)
体育会系というと、ともすると「精神論が強すぎる」「論理的な説明が苦手」などのマイナスのイメージを持ちがちであるが、実は「体育会系人材こそビジネスに強く、社会に出てから活躍する」と断言する。松本さんは「体育会系人材」のことを、敬意を込めて「アスリート人材」と呼んでいるという。
「アスリートというとプロスポーツ選手など、一部のトップアスリートを指すことが多く、スポーツに打ち込んでいる一般の人は自分のことをアスリートだとは思っていないはずです。
しかし、プロではないからといって、先に述べたようなスキルが身についていないかというと、まったくそんなことはありません。夢中になって何かに打ち込んだ経験から学んだこと、身についた力は数えきれないほどあります」(松本さん)
アスリートとはラテン語で「賞を狙って競う人」という意味だそうだ。つまり、レベルを問わず、「スポーツで勝ちたい」「タイムを縮めたい」と本気でスポーツに打ち込んでいる人すべてがアスリートに含まれる、と松本さんは解釈している。
「もっと言えば、野球選手だけではなく、野球場の外野席で熱い応援を送る吹奏楽団やチアリーダーの人たちもまた、アスリートといえるでしょう。スポーツに限らず、何かの大会に向けて練習に励んだり賞を目指したりして日々本気で頑張ってきた人はみな、アスリートなのです」(同)
アスリート人材に向いているのは「営業」と「接客」
2015年に英国オックスフォード大学と野村総研(NRI 野村総合研究所)が行った研究結果で、「日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能になる」と発表したことは、当時社会に大きなインパクトを与えた。
数年前、「近い将来、多くの仕事がAIにとって代わられる」と言われた世界が今、現実のものとなってきている。さらに、マッキンゼーが2020年に発表したレポート『未来の日本の働き方』では、こう報告されている。
「2030年までに既存業務のうち27%が自動化され、その結果1660万人の雇用が代替される可能性がある」
なくなっていくと予想される職業としては、一般事務、警備員、工場勤務者などが挙げられている。今や日常的にAIを使うのが当たり前となり、AIを使いこなせない人材は生き残れない時代となった。
「反対に、代替が難しいと予想される職業には、医師や教員、クリエイターといった想像力や創造力を必要とするものがあり、そのなかには営業も含まれています。これらの職業には、人間でなければ担えない要素が含まれています。そのため、仕事を行う際には、より『人間らしさ』が求められるでしょう」(松本さん)
近年、AIの急速な発達によって私たちの仕事や生活にも変化が見られるようになった。ビジネスや教育、医療などあらゆる現場でAIが導入されている。
「人間にしかできないことが求められ、その風潮はさらに加速しています。ビジネス市場においても、あいさつや人当たりの良さといった『基礎的な人間力』を持つ人材がますます求められるようになるでしょう。
アスリート人材は、その特性から人と接する仕事に適性があると感じます。もちろん個人差はありますが、特に営業や接客ではアスリート人材の強みが発揮されることが多いように見受けられます。高いコミュニケーション能力や対人スキルが求められるのが、その理由ではないでしょうか。
営業や接客は、『お客さま』がいないと成立しません。商品を買ったり、サービスを利用したりするのは人であり、人と人との付き合いがすべてです。そのため、相手の心を開き顧客との間に良好な関係を築くための高いコミュニケーション能力が求められます。アスリート人材は幼い頃から年長者と接し、組織のなかで育ったことで、対人対応力が鍛えられているのです」(松本さん)
部活動や体育会系で「コーチに求められていることは何か?」と考える習慣が身についており、相手の要求から常に自分の果たすべき任務を察知し、行動に結びつける思考が身についているというのだ。
また、礼儀作法が身体に染み込んでいるのもアスリート人材の特長の一つだという。
「礼儀正しさ、姿勢のよさ、大きな声でのあいさつを毎日のように実践してきているので、社会に出てからも気持ちのよい挨拶を自然と行うことができます。このようなアスリートがスポーツを通じて習得した『基礎的な人間力』を含むスキルは、AIに代替されない価値あるスキルとして重宝され、ビジネスパーソンとしても大きな強みになります。
なかでも、営業のように対人対応力や第一印象が重要な職種では、アスリート人材が頭角を現しやすいといえるでしょう」(松本さん)
アスリート人材が持つ「厳しさに耐えうる強さ」
現代社会では、かつてのような上下関係が変化しつつある。昔は、上司や先輩の言うことは絶対であり、それに逆らうことなど考えられない時代があったのも事実だ。スポーツの分野ではそれが顕著で、むしろ勝つためならとことん厳しい指導をするのが当たり前だった。かつては「結果を出すことがすべて」といった“スポ根”で鍛えられた人も多いだろう。
「しかし現代では、少し厳しくすると選手が逃げてしまったり、『行き過ぎた指導』と監督が注意されたりします。そのため、監督としても選手に遠慮してしまうことがあるかもしれません。いろんな場面で『優しくなっている』のです。
過去の悪い慣行を正していくことは大事ですが、選手たちと向き合うことをやめ、事なかれ主義で対応していくのは問題です。それでは必要な指導もできず、選手たちは成長する機会を失うでしょう。人間関係が希薄になりつつある現代においては、上司や先輩から厳しい指導を受ける機会が減り、親密な関わりをともなう管理や監督も少なくなっています。
リーダー側としては、若手社員がすぐ辞めないよう、腫れ物に触るような対応をとるケースも多いと聞きます。新入社員の定着という意味ではそれなりの効果があるかもしれませんが、社員のポテンシャルを引き出したり、中長期的な視点で育成したりする側面においては、マイナスの部分もあるのではないでしょうか。本人の成長を考え、時には厳しく、時には優しく接してくれる上司こそが、真に信頼に値するリーダーといえるでしょう。
私も野球経験を通じて礼儀作法やマナーを徹底的に叩き込まれたからこそ、それらが自然と身についていきました。仕事においても、いい加減にこなすことなど考えられません。アスリート人材は、厳しさにもきちんと耐えられる強さを持っています。それが上下関係に揉まれてきた『強靭さ』なのです」(松本さん)
AI時代に求められるスポーツマンシップの精神
アスリートたちのマインドに根づく「スポーツマンシップ」。スポーツは、長い発展の歴史のなかで「社会的な能力を身につけるための基礎」として位置づけられてきた。肉体的な鍛錬だけでなく、品性を養い、礼節を学ぶ場としても、スポーツの教育的な価値が認められている。
「選手たちはスポーツを通じて多くのことを学び、さまざまなスキルを習得していくわけですが、その根底にあるのが、『フェアプレー』をはじめとする『スポーツマンシップ』という概念です。これからの社会では、いっそう倫理観や基礎的な人間力が求められるようになると考えます。
テクノロジーの急速な進化にともない、近年は特に変化のスピードが速まっています。AIやロボットが人の仕事を担うようになると、私たち人間がやるべきことは次第に少なくなっていくでしょう。そうした時代の流れには、誰も逆らうことはできません。
しかし、すべての仕事がロボットに代替できるわけではありません。クリエイティビティやホスピタリティが求められる仕事、いわゆるヒューマンワークは、今後も人が担っていくことになるでしょう。そこで、問われるのが『人間性』です」(松本さん)
スキルやノウハウを発揮する以前に、その土台となる倫理観や相手への配慮、つまり「良き心」を持った人間が、これからの社会ではいっそう求められる、と松本さんは見ている。
「こうした目の前の人を思いやり、想像力を働かせることは、人間にしかできないことです。スポーツを経験してきた身として胸を張ってお伝えできるのは、その『良き心』がまさにスポーツマンシップに通じているということです。
仕事のスキルやノウハウは、後からでも身につけることができますが、人間性がともなっていなければ、いつか限界が訪れます。不誠実な行いは一時的にごまかせるかもしれませんが、いずれ明るみに出るでしょう。常に試されるのは『土台』なのです。
その点、アスリート人材にはスポーツマンシップという素晴らしい精神が備わっています。それは社会人として、そして人間としても重要な要素を含んでいます。
商品を購入するときやサービスを利用するとき、同じものであれば、ホスピタリティがあり、顧客のことを考えて接してくれる人から選びたいと思うのは自然なことですよね。自分の仕事に誇りを持ち、扱う商品やサービスに自信があるのなら、いい加減な仕事をするはずはありません。その心持ちや姿勢は、細かな対応や所作にも現れます。
自分だけ良い思いをすればいいという発想ではなく、フェアに戦おうとするスポーツマンシップの精神は、ビジネスパーソンとして求められるあり方にもつながります」(松本さん)
本物のアスリートは、緊迫した試合のさなかでも相手に対するリスペクトを忘れません。常にフェアに物事を捉え、周囲への配慮を忘れず、正々堂々と行動する。こうしたスポーツマンシップに通ずる姿勢は、これからの社会で活躍する人材には不可欠なのだ。
<取材・文/日刊SPA!編集部>
【松本隆宏】
ライフマネジメント株式会社代表取締役。1976年、神奈川県相模原市生まれ。高校時代は日大三高の主力選手として甲子園に出場。東京六大学野球に憧れ法政大学へ進学。大学卒業後、住宅業界を経て起業。「地主の参謀」として資産防衛コンサルティングに従事し、この10年で数々の実績を生み出している。また、最年少ながらコンサルタント名鑑『日本の専門コンサルタント50』で紹介されるなど、プロが認める今業界注目の逸材。ラジオ大阪OBC(FM91.9 AM1314)にて、毎週水曜日19:45~20:00「松本隆宏の参謀チャンネル®︎」を放送中。最新刊『アスリート人材の突破力 ~才能を引き出す気づきの法則~』のほか、『The参謀 ~歴史に学ぶ起業家のための経営術~』(游藝舎)、『地主の経営』(マネジメント社)などがある。
【関連記事】
・ なぜ「経営」は人から学ばないのか?これからの時代に必要なのは経営者と伴走する「参謀」
・ スポーツから学んだチームプレイ、ロジカルな思考力。アスリート人材が社会に出てからも活躍するワケ
・ 2001夏甲子園優勝投手、4度の手術と波乱万丈の野球人生。「失敗への対策の引き出しを持つことが重要」
・ 「7000万円借金があるけど」新卒で入ったTBSを“突如退社”したディレクター。「自分の最低ラインを決めれば何をしてもいい」
・ 人気番組『SASUKE』、“現役最強選手”のもう一つの顔は銀行員「SASUKEファンの支店長が出場を後押ししてくれた」
「体育会系人材ほど、会社で活躍できる可能性を秘めた人材はいません。体育会系の部活動やスポーツクラブは、社会の縮図といえます」
そう話すのは、『アスリート人材の突破力 ~才能を引き出す気づきの法則~』などの著書を持つ、資産防衛・ビジネスコンサルタントの松本隆宏さんだ。
社会に出てから活躍する体育会系人材
「体育会系では上下関係や同期との横のつながり、あるいは地域とのつながりを通して、さまざまな人間関係を学びます。また、スポーツは肉体のパワーだけでは絶対に勝てません。計画や戦略・戦術などゴールから逆算して考える力が必要になります。それらは監督やコーチに言われたことをただ単に覚え、その通りに動く力ではありません。監督やコーチが指導したこと、経験したことを時に批判的に捉えながら『自ら思考し動く力』です。すなわち、ビジネスでも必要とされるPDCAそのものなのです」(松本さん)
体育会系というと、ともすると「精神論が強すぎる」「論理的な説明が苦手」などのマイナスのイメージを持ちがちであるが、実は「体育会系人材こそビジネスに強く、社会に出てから活躍する」と断言する。松本さんは「体育会系人材」のことを、敬意を込めて「アスリート人材」と呼んでいるという。
「アスリートというとプロスポーツ選手など、一部のトップアスリートを指すことが多く、スポーツに打ち込んでいる一般の人は自分のことをアスリートだとは思っていないはずです。
しかし、プロではないからといって、先に述べたようなスキルが身についていないかというと、まったくそんなことはありません。夢中になって何かに打ち込んだ経験から学んだこと、身についた力は数えきれないほどあります」(松本さん)
アスリートとはラテン語で「賞を狙って競う人」という意味だそうだ。つまり、レベルを問わず、「スポーツで勝ちたい」「タイムを縮めたい」と本気でスポーツに打ち込んでいる人すべてがアスリートに含まれる、と松本さんは解釈している。
「もっと言えば、野球選手だけではなく、野球場の外野席で熱い応援を送る吹奏楽団やチアリーダーの人たちもまた、アスリートといえるでしょう。スポーツに限らず、何かの大会に向けて練習に励んだり賞を目指したりして日々本気で頑張ってきた人はみな、アスリートなのです」(同)
アスリート人材に向いているのは「営業」と「接客」
2015年に英国オックスフォード大学と野村総研(NRI 野村総合研究所)が行った研究結果で、「日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能になる」と発表したことは、当時社会に大きなインパクトを与えた。
数年前、「近い将来、多くの仕事がAIにとって代わられる」と言われた世界が今、現実のものとなってきている。さらに、マッキンゼーが2020年に発表したレポート『未来の日本の働き方』では、こう報告されている。
「2030年までに既存業務のうち27%が自動化され、その結果1660万人の雇用が代替される可能性がある」
なくなっていくと予想される職業としては、一般事務、警備員、工場勤務者などが挙げられている。今や日常的にAIを使うのが当たり前となり、AIを使いこなせない人材は生き残れない時代となった。
「反対に、代替が難しいと予想される職業には、医師や教員、クリエイターといった想像力や創造力を必要とするものがあり、そのなかには営業も含まれています。これらの職業には、人間でなければ担えない要素が含まれています。そのため、仕事を行う際には、より『人間らしさ』が求められるでしょう」(松本さん)
近年、AIの急速な発達によって私たちの仕事や生活にも変化が見られるようになった。ビジネスや教育、医療などあらゆる現場でAIが導入されている。
「人間にしかできないことが求められ、その風潮はさらに加速しています。ビジネス市場においても、あいさつや人当たりの良さといった『基礎的な人間力』を持つ人材がますます求められるようになるでしょう。
アスリート人材は、その特性から人と接する仕事に適性があると感じます。もちろん個人差はありますが、特に営業や接客ではアスリート人材の強みが発揮されることが多いように見受けられます。高いコミュニケーション能力や対人スキルが求められるのが、その理由ではないでしょうか。
営業や接客は、『お客さま』がいないと成立しません。商品を買ったり、サービスを利用したりするのは人であり、人と人との付き合いがすべてです。そのため、相手の心を開き顧客との間に良好な関係を築くための高いコミュニケーション能力が求められます。アスリート人材は幼い頃から年長者と接し、組織のなかで育ったことで、対人対応力が鍛えられているのです」(松本さん)
部活動や体育会系で「コーチに求められていることは何か?」と考える習慣が身についており、相手の要求から常に自分の果たすべき任務を察知し、行動に結びつける思考が身についているというのだ。
また、礼儀作法が身体に染み込んでいるのもアスリート人材の特長の一つだという。
「礼儀正しさ、姿勢のよさ、大きな声でのあいさつを毎日のように実践してきているので、社会に出てからも気持ちのよい挨拶を自然と行うことができます。このようなアスリートがスポーツを通じて習得した『基礎的な人間力』を含むスキルは、AIに代替されない価値あるスキルとして重宝され、ビジネスパーソンとしても大きな強みになります。
なかでも、営業のように対人対応力や第一印象が重要な職種では、アスリート人材が頭角を現しやすいといえるでしょう」(松本さん)
アスリート人材が持つ「厳しさに耐えうる強さ」
現代社会では、かつてのような上下関係が変化しつつある。昔は、上司や先輩の言うことは絶対であり、それに逆らうことなど考えられない時代があったのも事実だ。スポーツの分野ではそれが顕著で、むしろ勝つためならとことん厳しい指導をするのが当たり前だった。かつては「結果を出すことがすべて」といった“スポ根”で鍛えられた人も多いだろう。
「しかし現代では、少し厳しくすると選手が逃げてしまったり、『行き過ぎた指導』と監督が注意されたりします。そのため、監督としても選手に遠慮してしまうことがあるかもしれません。いろんな場面で『優しくなっている』のです。
過去の悪い慣行を正していくことは大事ですが、選手たちと向き合うことをやめ、事なかれ主義で対応していくのは問題です。それでは必要な指導もできず、選手たちは成長する機会を失うでしょう。人間関係が希薄になりつつある現代においては、上司や先輩から厳しい指導を受ける機会が減り、親密な関わりをともなう管理や監督も少なくなっています。
リーダー側としては、若手社員がすぐ辞めないよう、腫れ物に触るような対応をとるケースも多いと聞きます。新入社員の定着という意味ではそれなりの効果があるかもしれませんが、社員のポテンシャルを引き出したり、中長期的な視点で育成したりする側面においては、マイナスの部分もあるのではないでしょうか。本人の成長を考え、時には厳しく、時には優しく接してくれる上司こそが、真に信頼に値するリーダーといえるでしょう。
私も野球経験を通じて礼儀作法やマナーを徹底的に叩き込まれたからこそ、それらが自然と身についていきました。仕事においても、いい加減にこなすことなど考えられません。アスリート人材は、厳しさにもきちんと耐えられる強さを持っています。それが上下関係に揉まれてきた『強靭さ』なのです」(松本さん)
AI時代に求められるスポーツマンシップの精神
アスリートたちのマインドに根づく「スポーツマンシップ」。スポーツは、長い発展の歴史のなかで「社会的な能力を身につけるための基礎」として位置づけられてきた。肉体的な鍛錬だけでなく、品性を養い、礼節を学ぶ場としても、スポーツの教育的な価値が認められている。
「選手たちはスポーツを通じて多くのことを学び、さまざまなスキルを習得していくわけですが、その根底にあるのが、『フェアプレー』をはじめとする『スポーツマンシップ』という概念です。これからの社会では、いっそう倫理観や基礎的な人間力が求められるようになると考えます。
テクノロジーの急速な進化にともない、近年は特に変化のスピードが速まっています。AIやロボットが人の仕事を担うようになると、私たち人間がやるべきことは次第に少なくなっていくでしょう。そうした時代の流れには、誰も逆らうことはできません。
しかし、すべての仕事がロボットに代替できるわけではありません。クリエイティビティやホスピタリティが求められる仕事、いわゆるヒューマンワークは、今後も人が担っていくことになるでしょう。そこで、問われるのが『人間性』です」(松本さん)
スキルやノウハウを発揮する以前に、その土台となる倫理観や相手への配慮、つまり「良き心」を持った人間が、これからの社会ではいっそう求められる、と松本さんは見ている。
「こうした目の前の人を思いやり、想像力を働かせることは、人間にしかできないことです。スポーツを経験してきた身として胸を張ってお伝えできるのは、その『良き心』がまさにスポーツマンシップに通じているということです。
仕事のスキルやノウハウは、後からでも身につけることができますが、人間性がともなっていなければ、いつか限界が訪れます。不誠実な行いは一時的にごまかせるかもしれませんが、いずれ明るみに出るでしょう。常に試されるのは『土台』なのです。
その点、アスリート人材にはスポーツマンシップという素晴らしい精神が備わっています。それは社会人として、そして人間としても重要な要素を含んでいます。
商品を購入するときやサービスを利用するとき、同じものであれば、ホスピタリティがあり、顧客のことを考えて接してくれる人から選びたいと思うのは自然なことですよね。自分の仕事に誇りを持ち、扱う商品やサービスに自信があるのなら、いい加減な仕事をするはずはありません。その心持ちや姿勢は、細かな対応や所作にも現れます。
自分だけ良い思いをすればいいという発想ではなく、フェアに戦おうとするスポーツマンシップの精神は、ビジネスパーソンとして求められるあり方にもつながります」(松本さん)
本物のアスリートは、緊迫した試合のさなかでも相手に対するリスペクトを忘れません。常にフェアに物事を捉え、周囲への配慮を忘れず、正々堂々と行動する。こうしたスポーツマンシップに通ずる姿勢は、これからの社会で活躍する人材には不可欠なのだ。
<取材・文/日刊SPA!編集部>
【松本隆宏】
ライフマネジメント株式会社代表取締役。1976年、神奈川県相模原市生まれ。高校時代は日大三高の主力選手として甲子園に出場。東京六大学野球に憧れ法政大学へ進学。大学卒業後、住宅業界を経て起業。「地主の参謀」として資産防衛コンサルティングに従事し、この10年で数々の実績を生み出している。また、最年少ながらコンサルタント名鑑『日本の専門コンサルタント50』で紹介されるなど、プロが認める今業界注目の逸材。ラジオ大阪OBC(FM91.9 AM1314)にて、毎週水曜日19:45~20:00「松本隆宏の参謀チャンネル®︎」を放送中。最新刊『アスリート人材の突破力 ~才能を引き出す気づきの法則~』のほか、『The参謀 ~歴史に学ぶ起業家のための経営術~』(游藝舎)、『地主の経営』(マネジメント社)などがある。
【関連記事】
・ なぜ「経営」は人から学ばないのか?これからの時代に必要なのは経営者と伴走する「参謀」
・ スポーツから学んだチームプレイ、ロジカルな思考力。アスリート人材が社会に出てからも活躍するワケ
・ 2001夏甲子園優勝投手、4度の手術と波乱万丈の野球人生。「失敗への対策の引き出しを持つことが重要」
・ 「7000万円借金があるけど」新卒で入ったTBSを“突如退社”したディレクター。「自分の最低ラインを決めれば何をしてもいい」
・ 人気番組『SASUKE』、“現役最強選手”のもう一つの顔は銀行員「SASUKEファンの支店長が出場を後押ししてくれた」

生活 新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55