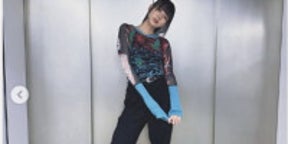la farfa magazine-ぽっちゃり女子のおしゃれ応援メディア-ラ・ファーファ公式サイト
【管理栄養士が解説!】花粉症のつらい症状を緩和するには「食事」の見直しを
3月10日(月) 1:00
提供:
「鼻水や鼻づまり、肌荒れなどの花粉症の症状がつらい……。薬以外の対策は何かないの?」と悩んでいる人もこの時期多いのではないでしょうか。実は、花粉症の症状を緩和するには、食事も重要なポイントなんです。
今回は、食事と花粉症の関係や対策に良い栄養、症状の悪化につながる可能性のある食べ物・飲み物について、あんしん漢方の管理栄養士の小原水月さんに解説していただきました。
|1. 食事と花粉症の関係
 花粉症は、スギやヒノキなどの植物の花粉(アレルゲン)に対するからだのアレルギー反応です。免疫機能が花粉を異物と判断し、抗体が過剰に反応することで、くしゃみや鼻水、鼻づまり、目や皮膚のかゆみ、咳などのさまざまな症状が起こります。
花粉症は、スギやヒノキなどの植物の花粉(アレルゲン)に対するからだのアレルギー反応です。免疫機能が花粉を異物と判断し、抗体が過剰に反応することで、くしゃみや鼻水、鼻づまり、目や皮膚のかゆみ、咳などのさまざまな症状が起こります。
免疫機能は腸や自律神経と深く関わっており、食生活の乱れや不規則な生活、ストレス、便秘などで腸内環境や自律神経の働きが悪くなると、花粉症などのアレルギー反応が出やすくなると考えられています。
したがって、食事によって腸内環境や自律神経、免疫機能を整えるのに役立つ栄養を摂取すると、アレルギーの過剰反応を抑え、花粉症の症状を緩和できる可能性があるのです ※1。
|2. 花粉症対策に摂りたい栄養
 花粉症対策には腸内環境を良くしたり、免疫の過剰反応を抑えたりする効果が期待できる栄養を積極的に摂りましょう。花粉症対策に摂りたい6つの栄養はこちらです。
花粉症対策には腸内環境を良くしたり、免疫の過剰反応を抑えたりする効果が期待できる栄養を積極的に摂りましょう。花粉症対策に摂りたい6つの栄養はこちらです。
| 乳酸菌
乳酸菌のような善玉菌は、腸内環境を整えて免疫細胞の働きを助ける役割を持っています ※2。
乳酸菌はヨーグルトやチーズ、キムチ、漬物、みそなどの発酵食品に含まれています。ただ、外から摂り入れた菌はいわば「お客さま」。腸内には定着せずに2~3日で排出されてしまいます。腸内環境を整えるには、乳酸菌を豊富に含んだヨーグルトを毎朝食べるなど、毎食何らかの発酵食品を摂るよう心がけましょう。
|食物繊維
善玉菌のえさになったり腸の動きを良くして便通を整えたりする効果が期待できます。
食物繊維が豊富な食材には、ごぼう、ブロッコリー、大根、大豆、じゃがいも、かぼちゃ、にんじん、きのこ類、海藻類、玄米などが挙げられます。
食物繊維の摂取量を増やすには、生野菜は煮たり茹でてかさを減らす、白米を玄米に置き換えるなどの方法がおすすめです。
|ビタミンA
皮膚やのど、鼻などの粘膜の健康を保つ栄養素です。レバーやうなぎ、たまご、チーズ、のり、緑黄色野菜(ほうれん草、にんじんなど)に多く含まれています。
ビタミンAは脂溶性のため、油と一緒に摂取すると吸収率が高くなります。体内に蓄積されやすいですが、食事からの摂取なら成人の耐容上限量である2700µgRAE/日を超える心配はほとんどありません。
しかし、レバーやうなぎを多く食べたときやビタミンAが含まれる医薬品やサプリメントを飲んでいる場合は、過剰摂取に気を付けましょう ※3。
|ビタミンD
過剰反応している免疫細胞を正常化し、花粉症の症状を抑える効果が期待できます。
ビタミンDが多い食材は、鮭や鯖などの魚介類、きのこ類、たまご、乳製品などです。なかでも、きのこ類は乾燥させるとビタミンDの含有量が増加します。生の状態から自分で干すのは大変という人は、市販の干しきのこを活用しましょう。
ビタミンDもビタミンAと同じく脂溶性のため、油と一緒に摂ることで吸収率が高くなります ※4。
|ポリフェノール
植物に存在する色素や苦味成分です。抗炎症作用や抗酸化作用を持ち、花粉症の症状緩和や免疫力の向上が期待できます。
代表的なポリフェノールは、緑茶や紅茶に含まれるカテキン、たまねぎの皮に多く含まれるケルセチン、チョコレートやココアに含まれるカカオポリフェノールなどです。特にカカオポリフェノールは、花粉症の症状の原因であるヒスタミンの放出と生成を抑制する効果があるといわれています。
花粉症の時期のおやつは、カカオポリフェノールを多く含み、糖質・脂質が控えめなカカオ70%以上のダークチョコレートがおすすめです。
|オメガ3脂肪酸
アレルギー症状を引き起こす物質の抑制作用があり、花粉症の症状を緩和する効果が期待できます ※5。オメガ3脂肪酸は、DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)、αリノレン酸などが当てはまります。
DHAやEPAの含有量が多い食材は、さばやいわし、ぶり、あじ、さんまなどの青魚です。αリノレン酸は、アマニ油やえごま油に多く含まれています。いつもより青魚を多く食べる、料理にアマニ油やえごま油を使うなどの方法で、オメガ3脂肪酸の摂取量を増やしましょう。
|3. 花粉症の悪化につながる可能性のある食べ物・飲み物
 アルコールや香辛料は粘膜の毛細血管を刺激し、鼻水や鼻づまりなどを悪化させる可能性があります。また、一般的にジャンクフードと呼ばれる、飽和脂肪酸が多い高カロリーの食事は、アレルギーを悪化させるといわれています。
アルコールや香辛料は粘膜の毛細血管を刺激し、鼻水や鼻づまりなどを悪化させる可能性があります。また、一般的にジャンクフードと呼ばれる、飽和脂肪酸が多い高カロリーの食事は、アレルギーを悪化させるといわれています。
花粉症の症状が気になるときは、お酒や辛いもの、ファストフード、スナック菓子などはできる限り控えましょう。
|4. 食事以外の花粉症対策
 食事による花粉症対策はからだを少しずつ整えるため、すぐに効果を感じにくいことがあります。花粉症の症状を和らげるために、食事と一緒に取り入れたい対策方法を3つご紹介します。
食事による花粉症対策はからだを少しずつ整えるため、すぐに効果を感じにくいことがあります。花粉症の症状を和らげるために、食事と一緒に取り入れたい対策方法を3つご紹介します。
|花粉を室内に持ち込まない
花粉を室内に持ち込まなければ、家の中で花粉症の症状が出にくくなります。花粉の飛散時期は、ポリエステルやナイロンなどのツルツルした素材の衣服を選び、帰宅時に玄関先で手や衣類用のブラシなどで花粉を払い落としましょう。
室内に入ったら、手洗い、うがい、洗顔、ブラッシングなどでからだや髪に付着した花粉を落としましょう。可能であれば、帰宅後すぐにシャワーや入浴で洗い流すのが望ましいです。その日着用していた衣服は脱いですぐに洗濯機に入れて洗うと、花粉が室内に蓄積するのを防げます。
|十分な睡眠をとる
寝不足は自律神経のバランスを崩し、花粉症の症状を悪化させる可能性があります。厚生労働省が公表している「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、成人の適正な睡眠時間はおおよそ6〜8時間とされています ※6。
睡眠の質を上げるために、朝起きたらすぐに日光を浴びる、毎日の起床・就寝時間を同じにする、部屋の照明を夜は暖色系の光に切り替える、湯船に浸かる、就寝前はスマホやパソコンを避けるなどの習慣を取り入れましょう。
|漢方薬を試してみる
花粉症の根本改善を目指すなら、漢方薬もおすすめです。漢方薬は医薬品としての効果が認められており、実際に耳鼻咽喉科やアレルギー専門外来でも花粉症に処方されています。
花粉症対策には、「鼻粘膜を温める」「鼻粘膜の水分循環をよくする」「鼻粘膜の炎症を和らげることで鼻水や鼻づまり、くしゃみなどの症状を抑える」といった漢方薬を選びましょう。
<花粉症対策におすすめの漢方薬>
小青竜湯(しょうせいりゅうとう)
冷えた鼻粘膜を温めて水分代謝を促し、花粉症の鼻水や鼻づまりの症状に働きかけます。水のような鼻水やアレルギー性鼻炎に悩んでいる方におすすめです。
葛根湯加川きゅう辛夷(かっこんとうかせんきゅうしんい)
鼻粘膜にこもった熱を冷まして鼻の通りをよくし、鼻水や鼻づまり、鼻の炎症を抑えます。鼻づまりがひどく、粘り気のある鼻水が出る方におすすめです。
漢方薬は自分のからだにあったものを選ぶことが重要です。漢方薬を始める際は、漢方に詳しい薬剤師にオンライン個別相談ができる「 あんしん漢方 」のようなサービスを利用しましょう。あんしん漢方なら漢方薬がお手頃価格で自宅に届くため、忙しい人にもおすすめです。
|5. つらい花粉症は食事で対策しよう
花粉症は、からだの過剰なアレルギー反応です。食事で免疫機能を調整すれば、症状が和らぐ可能性が高くなります。
「花粉症の時期は環境の変化や仕事の繁忙期などで忙しく、食生活の改善が難しい」という人は、まずは毎日飲むだけの漢方薬を始めてみるのがおすすめです。からだの内側から対策をして、花粉症の症状を和らげましょう。
<この記事の監修者>
 あんしん漢方管理栄養士
あんしん漢方管理栄養士
小原水月(おはらみづき)
管理栄養士・健康食育シニアマスター。
社員食堂で300以上の料理を修得、ダイエット合宿所・特定保健検診の業務に携わり600人以上の食事と生活習慣改善を個別サポート。自身の出産後の体調不良から食事と漢方で体調改善/増進の経験を生かし、栄養学と漢方を合わせたサポートを得意とする。「心も体も食べたものだけで作られる」をモットーに簡単で時間もお金もかけずに元気になれるレシピを発信中。
症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホ一つで相談、症状緩和と根本改善を目指す オンラインAI漢方「あんしん漢方」 でもサポートを行っている。
<参考文献>
※1 日本NCR健康保険組合「食事による花粉症対策」
※2 櫻井 大樹「アレルギー性鼻炎に対するプロバイオティクスのEBM」
※3 健康長寿ネット「ビタミンAの働きと1日の摂取量」
※4 健康長寿ネット「ビタミンDの働きと1日の摂取量」
※5 順天堂大学「オメガ3脂肪酸のアレルギー性結膜炎への改善効果を発見」
※6 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」
【関連記事】
韓国発ライフスタイルビューティーブランド「NONFICTION」日本初の路面店が待望オープン!
疲れているのに眠れない理由とは? NG行動や安眠のヒントを医師が解説!
「耳鳴り」はなぜ起こる? 考えられる病気や対策方法についてご紹介
睡眠ホルモン「メラトニン」で睡眠の質を改善するには? 分泌を促す方法を医師が解説!
「デトックス」ってどんな効果がある? おすすめ食材を管理栄養士が解説!
今回は、食事と花粉症の関係や対策に良い栄養、症状の悪化につながる可能性のある食べ物・飲み物について、あんしん漢方の管理栄養士の小原水月さんに解説していただきました。
|1. 食事と花粉症の関係
 花粉症は、スギやヒノキなどの植物の花粉(アレルゲン)に対するからだのアレルギー反応です。免疫機能が花粉を異物と判断し、抗体が過剰に反応することで、くしゃみや鼻水、鼻づまり、目や皮膚のかゆみ、咳などのさまざまな症状が起こります。
花粉症は、スギやヒノキなどの植物の花粉(アレルゲン)に対するからだのアレルギー反応です。免疫機能が花粉を異物と判断し、抗体が過剰に反応することで、くしゃみや鼻水、鼻づまり、目や皮膚のかゆみ、咳などのさまざまな症状が起こります。
免疫機能は腸や自律神経と深く関わっており、食生活の乱れや不規則な生活、ストレス、便秘などで腸内環境や自律神経の働きが悪くなると、花粉症などのアレルギー反応が出やすくなると考えられています。
したがって、食事によって腸内環境や自律神経、免疫機能を整えるのに役立つ栄養を摂取すると、アレルギーの過剰反応を抑え、花粉症の症状を緩和できる可能性があるのです ※1。
|2. 花粉症対策に摂りたい栄養
 花粉症対策には腸内環境を良くしたり、免疫の過剰反応を抑えたりする効果が期待できる栄養を積極的に摂りましょう。花粉症対策に摂りたい6つの栄養はこちらです。
花粉症対策には腸内環境を良くしたり、免疫の過剰反応を抑えたりする効果が期待できる栄養を積極的に摂りましょう。花粉症対策に摂りたい6つの栄養はこちらです。
| 乳酸菌
乳酸菌のような善玉菌は、腸内環境を整えて免疫細胞の働きを助ける役割を持っています ※2。
乳酸菌はヨーグルトやチーズ、キムチ、漬物、みそなどの発酵食品に含まれています。ただ、外から摂り入れた菌はいわば「お客さま」。腸内には定着せずに2~3日で排出されてしまいます。腸内環境を整えるには、乳酸菌を豊富に含んだヨーグルトを毎朝食べるなど、毎食何らかの発酵食品を摂るよう心がけましょう。
|食物繊維
善玉菌のえさになったり腸の動きを良くして便通を整えたりする効果が期待できます。
食物繊維が豊富な食材には、ごぼう、ブロッコリー、大根、大豆、じゃがいも、かぼちゃ、にんじん、きのこ類、海藻類、玄米などが挙げられます。
食物繊維の摂取量を増やすには、生野菜は煮たり茹でてかさを減らす、白米を玄米に置き換えるなどの方法がおすすめです。
|ビタミンA
皮膚やのど、鼻などの粘膜の健康を保つ栄養素です。レバーやうなぎ、たまご、チーズ、のり、緑黄色野菜(ほうれん草、にんじんなど)に多く含まれています。
ビタミンAは脂溶性のため、油と一緒に摂取すると吸収率が高くなります。体内に蓄積されやすいですが、食事からの摂取なら成人の耐容上限量である2700µgRAE/日を超える心配はほとんどありません。
しかし、レバーやうなぎを多く食べたときやビタミンAが含まれる医薬品やサプリメントを飲んでいる場合は、過剰摂取に気を付けましょう ※3。
|ビタミンD
過剰反応している免疫細胞を正常化し、花粉症の症状を抑える効果が期待できます。
ビタミンDが多い食材は、鮭や鯖などの魚介類、きのこ類、たまご、乳製品などです。なかでも、きのこ類は乾燥させるとビタミンDの含有量が増加します。生の状態から自分で干すのは大変という人は、市販の干しきのこを活用しましょう。
ビタミンDもビタミンAと同じく脂溶性のため、油と一緒に摂ることで吸収率が高くなります ※4。
|ポリフェノール
植物に存在する色素や苦味成分です。抗炎症作用や抗酸化作用を持ち、花粉症の症状緩和や免疫力の向上が期待できます。
代表的なポリフェノールは、緑茶や紅茶に含まれるカテキン、たまねぎの皮に多く含まれるケルセチン、チョコレートやココアに含まれるカカオポリフェノールなどです。特にカカオポリフェノールは、花粉症の症状の原因であるヒスタミンの放出と生成を抑制する効果があるといわれています。
花粉症の時期のおやつは、カカオポリフェノールを多く含み、糖質・脂質が控えめなカカオ70%以上のダークチョコレートがおすすめです。
|オメガ3脂肪酸
アレルギー症状を引き起こす物質の抑制作用があり、花粉症の症状を緩和する効果が期待できます ※5。オメガ3脂肪酸は、DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)、αリノレン酸などが当てはまります。
DHAやEPAの含有量が多い食材は、さばやいわし、ぶり、あじ、さんまなどの青魚です。αリノレン酸は、アマニ油やえごま油に多く含まれています。いつもより青魚を多く食べる、料理にアマニ油やえごま油を使うなどの方法で、オメガ3脂肪酸の摂取量を増やしましょう。
|3. 花粉症の悪化につながる可能性のある食べ物・飲み物
 アルコールや香辛料は粘膜の毛細血管を刺激し、鼻水や鼻づまりなどを悪化させる可能性があります。また、一般的にジャンクフードと呼ばれる、飽和脂肪酸が多い高カロリーの食事は、アレルギーを悪化させるといわれています。
アルコールや香辛料は粘膜の毛細血管を刺激し、鼻水や鼻づまりなどを悪化させる可能性があります。また、一般的にジャンクフードと呼ばれる、飽和脂肪酸が多い高カロリーの食事は、アレルギーを悪化させるといわれています。
花粉症の症状が気になるときは、お酒や辛いもの、ファストフード、スナック菓子などはできる限り控えましょう。
|4. 食事以外の花粉症対策
 食事による花粉症対策はからだを少しずつ整えるため、すぐに効果を感じにくいことがあります。花粉症の症状を和らげるために、食事と一緒に取り入れたい対策方法を3つご紹介します。
食事による花粉症対策はからだを少しずつ整えるため、すぐに効果を感じにくいことがあります。花粉症の症状を和らげるために、食事と一緒に取り入れたい対策方法を3つご紹介します。
|花粉を室内に持ち込まない
花粉を室内に持ち込まなければ、家の中で花粉症の症状が出にくくなります。花粉の飛散時期は、ポリエステルやナイロンなどのツルツルした素材の衣服を選び、帰宅時に玄関先で手や衣類用のブラシなどで花粉を払い落としましょう。
室内に入ったら、手洗い、うがい、洗顔、ブラッシングなどでからだや髪に付着した花粉を落としましょう。可能であれば、帰宅後すぐにシャワーや入浴で洗い流すのが望ましいです。その日着用していた衣服は脱いですぐに洗濯機に入れて洗うと、花粉が室内に蓄積するのを防げます。
|十分な睡眠をとる
寝不足は自律神経のバランスを崩し、花粉症の症状を悪化させる可能性があります。厚生労働省が公表している「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、成人の適正な睡眠時間はおおよそ6〜8時間とされています ※6。
睡眠の質を上げるために、朝起きたらすぐに日光を浴びる、毎日の起床・就寝時間を同じにする、部屋の照明を夜は暖色系の光に切り替える、湯船に浸かる、就寝前はスマホやパソコンを避けるなどの習慣を取り入れましょう。
|漢方薬を試してみる
花粉症の根本改善を目指すなら、漢方薬もおすすめです。漢方薬は医薬品としての効果が認められており、実際に耳鼻咽喉科やアレルギー専門外来でも花粉症に処方されています。
花粉症対策には、「鼻粘膜を温める」「鼻粘膜の水分循環をよくする」「鼻粘膜の炎症を和らげることで鼻水や鼻づまり、くしゃみなどの症状を抑える」といった漢方薬を選びましょう。
<花粉症対策におすすめの漢方薬>
小青竜湯(しょうせいりゅうとう)
冷えた鼻粘膜を温めて水分代謝を促し、花粉症の鼻水や鼻づまりの症状に働きかけます。水のような鼻水やアレルギー性鼻炎に悩んでいる方におすすめです。
葛根湯加川きゅう辛夷(かっこんとうかせんきゅうしんい)
鼻粘膜にこもった熱を冷まして鼻の通りをよくし、鼻水や鼻づまり、鼻の炎症を抑えます。鼻づまりがひどく、粘り気のある鼻水が出る方におすすめです。
漢方薬は自分のからだにあったものを選ぶことが重要です。漢方薬を始める際は、漢方に詳しい薬剤師にオンライン個別相談ができる「 あんしん漢方 」のようなサービスを利用しましょう。あんしん漢方なら漢方薬がお手頃価格で自宅に届くため、忙しい人にもおすすめです。
|5. つらい花粉症は食事で対策しよう
花粉症は、からだの過剰なアレルギー反応です。食事で免疫機能を調整すれば、症状が和らぐ可能性が高くなります。
「花粉症の時期は環境の変化や仕事の繁忙期などで忙しく、食生活の改善が難しい」という人は、まずは毎日飲むだけの漢方薬を始めてみるのがおすすめです。からだの内側から対策をして、花粉症の症状を和らげましょう。
<この記事の監修者>
 あんしん漢方管理栄養士
あんしん漢方管理栄養士
小原水月(おはらみづき)
管理栄養士・健康食育シニアマスター。
社員食堂で300以上の料理を修得、ダイエット合宿所・特定保健検診の業務に携わり600人以上の食事と生活習慣改善を個別サポート。自身の出産後の体調不良から食事と漢方で体調改善/増進の経験を生かし、栄養学と漢方を合わせたサポートを得意とする。「心も体も食べたものだけで作られる」をモットーに簡単で時間もお金もかけずに元気になれるレシピを発信中。
症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホ一つで相談、症状緩和と根本改善を目指す オンラインAI漢方「あんしん漢方」 でもサポートを行っている。
<参考文献>
※1 日本NCR健康保険組合「食事による花粉症対策」
※2 櫻井 大樹「アレルギー性鼻炎に対するプロバイオティクスのEBM」
※3 健康長寿ネット「ビタミンAの働きと1日の摂取量」
※4 健康長寿ネット「ビタミンDの働きと1日の摂取量」
※5 順天堂大学「オメガ3脂肪酸のアレルギー性結膜炎への改善効果を発見」
※6 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」
【関連記事】
韓国発ライフスタイルビューティーブランド「NONFICTION」日本初の路面店が待望オープン!
疲れているのに眠れない理由とは? NG行動や安眠のヒントを医師が解説!
「耳鳴り」はなぜ起こる? 考えられる病気や対策方法についてご紹介
睡眠ホルモン「メラトニン」で睡眠の質を改善するには? 分泌を促す方法を医師が解説!
「デトックス」ってどんな効果がある? おすすめ食材を管理栄養士が解説!

生活 新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55