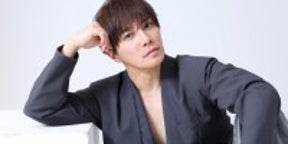スーパーで「冷凍食品」を買おうとしたらほとんどが値上がりしていて驚きました……なんでこんなに高くなっているのでしょうか?
3月7日(金) 17:10
冷凍食品の価格高騰の背景
株式会社帝国データバンクの「価格改定動向調査」によると、2025年2月、主要な食品メーカー195社が合計1656品目の値上げを実施しました。このうち、冷凍食品を含む「加工食品」は589品目と、全食品分野の中で最も多くの品目が値上げの対象となっています。この値上げの主な要因として、以下の点が挙げられます。
・原材料費の上昇
・円安の影響
・物流費や人件費の増加
世界的な気候変動や輸送コストの増加などにより、農産物や水産物の価格が高騰しました。特に、円安の影響で輸入原材料のコストが増加し、これが製品価格に反映されていると考えられます。
さらに、トラックドライバーの時間外労働規制や人手不足などにより、物流コストが上昇していることに加えて、最低賃金の引き上げや人件費の増加も価格高騰の要因となっています。
家計への影響と消費者の反応
冷凍食品の価格上昇は、消費者にとって大きな負担となるでしょう。しかし、一般社団法人日本冷凍食品協会が2024年に実施した「“冷凍食品の利用状況”実態調査」によると、消費者の約8割が市販の冷凍食品の「おいしさ」に満足しており、値上げを実感しつつも「購入量は変わらない」「増えた」と感じている人が多いことが明らかになっています。
これは、冷凍食品が他の外食や惣菜と比較してコストパフォーマンスや調理の手軽さで優れていると評価されているためと考えられます。
冷凍食品業界の今後の動向
冷凍食品業界は、価格改定を余儀なくされつつも、市場の拡大を続けているようです。これは、コロナ禍を経て冷凍食品の品質や利便性が再認識されたこと、そして物価上昇の中で外食やコンビニ惣菜に比べて割安感があることが要因とされています。
しかし、原材料費や物流費の高騰が続く中、さらなる価格上昇の可能性も否定できません。消費者としては、引き続き市場の動向に注目しつつ、賢い選択が求められます。
まとめ
冷凍食品の価格高騰は、原材料費の上昇、円安、物流費・人件費の増加といった複数の要因が絡み合い、避けられない状況となっています。しかし、その利便性やコストパフォーマンスの高さから、値上げを実感しつつも多くの消費者が購入を継続しているのも事実です。
一方で、今後も価格の上昇が続く可能性があるため、消費者としては、特売やまとめ買いを活用する、代替商品を検討する、自家製冷凍食品を取り入れるなど、工夫を凝らして家計への負担を抑えることが求められます。
冷凍食品の価格高騰は避けられないものの、賢く対策を講じることで家計への影響を最小限に抑え、この物価高の時代を乗り切りましょう。
出典
株式会社帝国データバンク 「食品主要195社」価格改定動向調査―2025年2月(2ページ~3ページ)
一般社団法人日本冷凍食品協会 “冷凍食品の利用状況”実態調査結果について(1ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
夫婦2人の「食費」は平均どのくらいにすべき? 食費の「節約ポイント」も解説4人家族で食費8万円は決して高くない。1人当たりの食費の目安は
外食を我慢して「1ヶ月自炊生活」を続けたら、食費はいくらくらい節約できる?

新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55