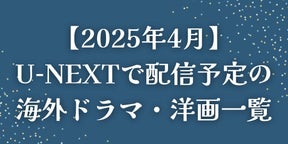picture cells - stock.adobe.com
“過去最高益”びっくりドンキー。人気の理由は、「安いから」ではなく「おいしいから」…“ハンバーグ特化”戦略の巧妙さ
3月4日(火) 23:53
提供:
ハンバーグレストランとして知られる「びっくりドンキー」(以下、びくドン)は、飲食業界の中でも好調で、2024年3月には過去最高益を記録した。顧客のブランド認知に対する調査であるNPS調査によると、ファミリーレストラン部門の首位が、このびくドン。ブランディングに成功しているのだ。「びくドンだから行く」というのが、定着しているというわけだ。この点でも、スタバに近しい特徴を持っているといえる。
※本記事は、『ニセコ化するニッポン』(KADOKAWA)より抜粋・編集したものです。
びっくりドンキーは「テーマパーク型飲食店」
びくドンといえば、ぱっと思いつくのが、あの奇抜な外観・内装。
「テーマパーク」ということでいえば、まさにぴったりかもしれない。国道沿いを車で走っていて、あの外観が目に入ったときのちょっとしたワクワク感は、どこかディズニーランドが目に入るようなワクワク感と似ている。経済ジャーナリストの高井尚之は、びくドンを「テーマパーク型飲食店」の走りだと評価する。
しかし、びくドンの人気を支えているのは、これだけではない。というより、びくドンは、もっと本質的な部分でテーマパーク的で、そして「ニセコ」的だと思われるのだ。そして実際に、その戦略を見ていると、きわめて巧妙に「選択と集中」が行われていることがわかる。
「ハンバーグ」という一品を「選択」した
びくドンが行う「選択と集中」とはなにか。
それは「ハンバーグ」という一品目に特化している、ということだ。しかも、それはただの「ハンバーグ」ではない。「日本人向けハンバーグ」に特化している。
びくドンで不動の人気を誇るのが、「ハンバーグディッシュ」。ハンバーグとご飯、そしてサラダが一つのプレートに載っている。あの丸い木の皿に愛着を覚える人も多いかもしれない。びっくりドンキーの前身は、1968年、庄司昭夫が岩手県・盛岡で開業した「ハンバーガーとサラダの店べる」。元々ハンバーガーを提供していた。しかし、その数年後、日本にやってきた「マクドナルド」を見た庄司は「これには勝てない」と思い、ハンバーガーをバラバラにして提供する形で考案したのが、このメニューだった。
大塚一馬は「ドンキーは本質的に単品のファーストフード(FFS)なのである」と書いている(『月刊食堂』2001年9月号)。確かに、現在でも、びっくりドンキーのメニューのほとんどはハンバーグディッシュで、基本的にこの店に来るほとんどの人がハンバーグディッシュを食べるだろう。これは、他のほとんどのファミリーレストランが、多品種であることを踏まえると、大きな違いだといえる。
ニセコや新大久保では、さまざまなタイプの観光客を受け入れることはしない(少なくとも、現状、受け入れるような空間の作り方をしていない)。びくドンもまた、「ハンバーグ」に注力して、すべてのメニューをまんべんなく出す、ということをしないのだ。
さらに、このハンバーグはただのハンバーグではない。徹底したこだわりがそこに詰められている。「ハンバーグ」は外国からやってきたものだが、それはすでに日本人の舌にも馴染み深いものとなっていて、そのハンバーグの強みを発見し、そこに特化したのが、びっくりドンキーの成功の要因である。
びくドン・ハンバーグの「三つのこだわり」
では、具体的にそのハンバーグのこだわりとはどんなものか。ここには主に三つのこだわりがある。①安さへのこだわり、②ハンバーグ自体の味へのこだわり、③「日本人大衆向け」にするための工夫だ。
まずは①の安さへのこだわりだが、大塚が指摘しているように、びくドン以前において、単品に特化している業態といえば、「かに道楽」や「レッドロブスター」のように、客単価が高い傾向にあった。一品目に特化するぶん、こだわりが強く、商品単価が高いからである。しかし、びくドンはそこを安価にして提供した。地域別の価格設定をしているが、東京の場合、ハンバーグディッシュSサイズで830円であり、ご飯とサラダが付いてこの価格なのは、非常にお得感が強いだろう(2024年12月現在)。
実際、多くの人がそこに行く理由の一つには、ハンバーグを食べられるにもかかわらず、その値段が安いということがあるはずだ。
「おいしいから」びくドンへ行く。「安いから」ではない
しかし、より重要なのは、②・③の「味」に関わる部分だ。LINEリサーチが22年6月に発表した「一番好きなファミリーレストラン」調査では、好きなファミレストップ4にランクインしているサイゼリヤ、ガスト/ステーキガスト、ジョイフルを好きな理由1位はいずれも「値段が安いから」だった。それに対し、びっくりドンキーを好きな理由の1位は「料理がおいしいから」(63・5%)となっている。値段もさることながら、「おいしさ」が重要な要素になっている。では、そのこだわりはどこにあるのか。
そこで、②のハンバーグ自体の味へのこだわりについて見ていこう。
びくドンのハンバーグに使われる肉はすべてオーストラリア産かニュージーランド産に絞っている。また、このハンバーグは工場で冷凍したものを店で解凍するのではなく、「必要なものを必要な分だけ」供給するジャスト・イン・タイムシステムで「生」のまま、各店舗に配送される。また、ハンバーグに使用されるタマネギは品種による水分含量なども見つつ、最もハンバーグに適したものを選んでいる。
さらに、創業者である庄司昭夫は、そこで提供する食材について、その提供者である自分たち自身で知らなければならないというモットーのもと、1980年代からは実験農場も北海道に作り、より安全で安心な牛肉・豚肉の提供を行うべく研究を続けている。ハンバーグを構成する食材へのこだわりが、(いい意味で)常軌を逸しているのだ。
日本人が食べやすい、箸で食べられるハンバーグ
次に③「日本人大衆向け」にするための工夫である。
びくドンのハンバーグは、日本人に合わせて箸で食べやすいような厚さになっている。少し薄くすることで、箸で切りやすいようにしているのだ。また、その味付けも、西洋風のハンバーグというよりは、醬油味をベースにした日本風の味付けであり、この点でも人気を博している。妙にご飯が進む、と思う裏にはそんなカラクリがある。
さらにびくドンのハンバーグへのこだわりは止まらない。そもそも、ハンバーグディッシュに有無を言わせぬように付いているご飯であるが、そもそもこの組み合わせ自体、とても日本的だろう。ちなみに、お米はオリジナルの省農薬米を使い、その栽培においては「殺虫剤」「殺菌剤」を使わず「除草剤も1回しか使わない」といったルールを設けている。ここについても徹底したこだわりが見られる。
同時に「日本人の舌」ということでいえば、「味噌汁」へのこだわりもすごい。FC店舗運営部部長の堀雅徳によると、味噌汁はハンバーグに合うよう、コクのある信州味噌を用いており、その具材も日替わりで厳選したものを使っている。
大塚一馬は「こんなシンプルなメニューなのに単調さからまぬがれているのは、ドンキーが副食材やソースの開発をおざなりにしていないからだ」と書く。
以上の三つの要素から、びくドンは「安さ」と「ハンバーグの質」により、「日本人大衆向けハンバーグ」という一品目に「集中」し、結果的にそこに来る人々も日本の一般的な家庭を「選択」しているのだ。
ただの外食じゃない。ワクワクさせる演出
こうした「日本人の一般家庭」をターゲットに彼らを満足させる戦略は、特にびくドンが郊外店舗を基本としていることからもわかるだろう。
一方で、そのように「日本人の一般家庭」を相手にしたときに、留意すべきは、ハンバーグそのものは、各家庭でも食べられるものだということだ。マイボイスコムの調査によれば、回答者の52・8%が自宅でよく食べる料理としてハンバーグを回答したという。これは調査対象になっている洋食の中ではカレーライスについで2番目に多く、いかに多くの人がハンバーグを自宅で食べるかを表している。
そうなってくると、わざわざ外食として食べるハンバーグレストランとして、必要なことは、そのレストラン空間の特別感をいかに演出するのか、ということにかかってくる。
もちろん、その一つが家庭では到底真似できないような、素材レベルでの商品のこだわりであることは言うまでもない。一方でびくドンが面白いのは、こうした「日本人の一般家庭向けハンバーグ」を中心とする食事の体験自体をさらに楽しいものにするための工夫が、空間の随所に凝らされているということだ。まさに、「選択」と「集中」を行う先に、テーマパーク的空間が出現する。
その一つが「木製のメニュー」だ。ファミリーレストランのメニューにしては、あまりにも大きく仰々しいこの木製メニューは、びくドンの定番ともいえるものだった。しかし近年では、DX化の浸透から、タブレットでのメニューに変える店舗もある。ただ、「タブレットだとワクワク感が減ってしまう」という顧客の声も多く、この木製メニューはまた少しずつ復活している。それが、食事を楽しむときの「ワクワク感」につながっていることがよくわかる。
あるいは最初に触れたが、特徴的な店内や外観も、びくドンを「特別感」のあるものにしているだろう。日常世界とは少し離れた「異空間」を形作るのが「テーマパーク」であるが、まさにびくドンは、こうした点から「選択と集中によるテーマパーク化」を行っているのである。
<TEXT/谷頭和希>
【谷頭和希】
ライター・作家。チェーンストアやテーマパークをテーマにした原稿を数多く執筆。一見平板に見える現代の都市空間について、独自の切り口で語る。「東洋経済オンライン」などで執筆中、文芸誌などにも多く寄稿をおこなう。著書に『ドンキにはなぜペンギンがいるのか』(集英社)『ブックオフから考える』(青弓社)
【関連記事】
・ 「びっくりドンキー」の“ホテル並み”豪華モーニングを実食。ワンコイン以下の独自メニューも
・ 不二家「ケーキ食べ放題」気づけば料金が3倍に…。店舗で“実食レポ”した本音
・ SNSで話題「他店より美味いマクドナルドがある」って本当?元店舗マネージャーは「入った瞬間にわかります」
・ 日本の評価を落とす「薄っぺらい商売」…観光地で「日本人が食べたことがないメニュー」を提供する歪さ
・ “高すぎる”と話題の「豊洲 千客万来」海鮮バイキングを実食。“最安値6000円以上”の価値はあるのか
※本記事は、『ニセコ化するニッポン』(KADOKAWA)より抜粋・編集したものです。
びっくりドンキーは「テーマパーク型飲食店」
びくドンといえば、ぱっと思いつくのが、あの奇抜な外観・内装。
「テーマパーク」ということでいえば、まさにぴったりかもしれない。国道沿いを車で走っていて、あの外観が目に入ったときのちょっとしたワクワク感は、どこかディズニーランドが目に入るようなワクワク感と似ている。経済ジャーナリストの高井尚之は、びくドンを「テーマパーク型飲食店」の走りだと評価する。
しかし、びくドンの人気を支えているのは、これだけではない。というより、びくドンは、もっと本質的な部分でテーマパーク的で、そして「ニセコ」的だと思われるのだ。そして実際に、その戦略を見ていると、きわめて巧妙に「選択と集中」が行われていることがわかる。
「ハンバーグ」という一品を「選択」した
びくドンが行う「選択と集中」とはなにか。
それは「ハンバーグ」という一品目に特化している、ということだ。しかも、それはただの「ハンバーグ」ではない。「日本人向けハンバーグ」に特化している。
びくドンで不動の人気を誇るのが、「ハンバーグディッシュ」。ハンバーグとご飯、そしてサラダが一つのプレートに載っている。あの丸い木の皿に愛着を覚える人も多いかもしれない。びっくりドンキーの前身は、1968年、庄司昭夫が岩手県・盛岡で開業した「ハンバーガーとサラダの店べる」。元々ハンバーガーを提供していた。しかし、その数年後、日本にやってきた「マクドナルド」を見た庄司は「これには勝てない」と思い、ハンバーガーをバラバラにして提供する形で考案したのが、このメニューだった。
大塚一馬は「ドンキーは本質的に単品のファーストフード(FFS)なのである」と書いている(『月刊食堂』2001年9月号)。確かに、現在でも、びっくりドンキーのメニューのほとんどはハンバーグディッシュで、基本的にこの店に来るほとんどの人がハンバーグディッシュを食べるだろう。これは、他のほとんどのファミリーレストランが、多品種であることを踏まえると、大きな違いだといえる。
ニセコや新大久保では、さまざまなタイプの観光客を受け入れることはしない(少なくとも、現状、受け入れるような空間の作り方をしていない)。びくドンもまた、「ハンバーグ」に注力して、すべてのメニューをまんべんなく出す、ということをしないのだ。
さらに、このハンバーグはただのハンバーグではない。徹底したこだわりがそこに詰められている。「ハンバーグ」は外国からやってきたものだが、それはすでに日本人の舌にも馴染み深いものとなっていて、そのハンバーグの強みを発見し、そこに特化したのが、びっくりドンキーの成功の要因である。
びくドン・ハンバーグの「三つのこだわり」
では、具体的にそのハンバーグのこだわりとはどんなものか。ここには主に三つのこだわりがある。①安さへのこだわり、②ハンバーグ自体の味へのこだわり、③「日本人大衆向け」にするための工夫だ。
まずは①の安さへのこだわりだが、大塚が指摘しているように、びくドン以前において、単品に特化している業態といえば、「かに道楽」や「レッドロブスター」のように、客単価が高い傾向にあった。一品目に特化するぶん、こだわりが強く、商品単価が高いからである。しかし、びくドンはそこを安価にして提供した。地域別の価格設定をしているが、東京の場合、ハンバーグディッシュSサイズで830円であり、ご飯とサラダが付いてこの価格なのは、非常にお得感が強いだろう(2024年12月現在)。
実際、多くの人がそこに行く理由の一つには、ハンバーグを食べられるにもかかわらず、その値段が安いということがあるはずだ。
「おいしいから」びくドンへ行く。「安いから」ではない
しかし、より重要なのは、②・③の「味」に関わる部分だ。LINEリサーチが22年6月に発表した「一番好きなファミリーレストラン」調査では、好きなファミレストップ4にランクインしているサイゼリヤ、ガスト/ステーキガスト、ジョイフルを好きな理由1位はいずれも「値段が安いから」だった。それに対し、びっくりドンキーを好きな理由の1位は「料理がおいしいから」(63・5%)となっている。値段もさることながら、「おいしさ」が重要な要素になっている。では、そのこだわりはどこにあるのか。
そこで、②のハンバーグ自体の味へのこだわりについて見ていこう。
びくドンのハンバーグに使われる肉はすべてオーストラリア産かニュージーランド産に絞っている。また、このハンバーグは工場で冷凍したものを店で解凍するのではなく、「必要なものを必要な分だけ」供給するジャスト・イン・タイムシステムで「生」のまま、各店舗に配送される。また、ハンバーグに使用されるタマネギは品種による水分含量なども見つつ、最もハンバーグに適したものを選んでいる。
さらに、創業者である庄司昭夫は、そこで提供する食材について、その提供者である自分たち自身で知らなければならないというモットーのもと、1980年代からは実験農場も北海道に作り、より安全で安心な牛肉・豚肉の提供を行うべく研究を続けている。ハンバーグを構成する食材へのこだわりが、(いい意味で)常軌を逸しているのだ。
日本人が食べやすい、箸で食べられるハンバーグ
次に③「日本人大衆向け」にするための工夫である。
びくドンのハンバーグは、日本人に合わせて箸で食べやすいような厚さになっている。少し薄くすることで、箸で切りやすいようにしているのだ。また、その味付けも、西洋風のハンバーグというよりは、醬油味をベースにした日本風の味付けであり、この点でも人気を博している。妙にご飯が進む、と思う裏にはそんなカラクリがある。
さらにびくドンのハンバーグへのこだわりは止まらない。そもそも、ハンバーグディッシュに有無を言わせぬように付いているご飯であるが、そもそもこの組み合わせ自体、とても日本的だろう。ちなみに、お米はオリジナルの省農薬米を使い、その栽培においては「殺虫剤」「殺菌剤」を使わず「除草剤も1回しか使わない」といったルールを設けている。ここについても徹底したこだわりが見られる。
同時に「日本人の舌」ということでいえば、「味噌汁」へのこだわりもすごい。FC店舗運営部部長の堀雅徳によると、味噌汁はハンバーグに合うよう、コクのある信州味噌を用いており、その具材も日替わりで厳選したものを使っている。
大塚一馬は「こんなシンプルなメニューなのに単調さからまぬがれているのは、ドンキーが副食材やソースの開発をおざなりにしていないからだ」と書く。
以上の三つの要素から、びくドンは「安さ」と「ハンバーグの質」により、「日本人大衆向けハンバーグ」という一品目に「集中」し、結果的にそこに来る人々も日本の一般的な家庭を「選択」しているのだ。
ただの外食じゃない。ワクワクさせる演出
こうした「日本人の一般家庭」をターゲットに彼らを満足させる戦略は、特にびくドンが郊外店舗を基本としていることからもわかるだろう。
一方で、そのように「日本人の一般家庭」を相手にしたときに、留意すべきは、ハンバーグそのものは、各家庭でも食べられるものだということだ。マイボイスコムの調査によれば、回答者の52・8%が自宅でよく食べる料理としてハンバーグを回答したという。これは調査対象になっている洋食の中ではカレーライスについで2番目に多く、いかに多くの人がハンバーグを自宅で食べるかを表している。
そうなってくると、わざわざ外食として食べるハンバーグレストランとして、必要なことは、そのレストラン空間の特別感をいかに演出するのか、ということにかかってくる。
もちろん、その一つが家庭では到底真似できないような、素材レベルでの商品のこだわりであることは言うまでもない。一方でびくドンが面白いのは、こうした「日本人の一般家庭向けハンバーグ」を中心とする食事の体験自体をさらに楽しいものにするための工夫が、空間の随所に凝らされているということだ。まさに、「選択」と「集中」を行う先に、テーマパーク的空間が出現する。
その一つが「木製のメニュー」だ。ファミリーレストランのメニューにしては、あまりにも大きく仰々しいこの木製メニューは、びくドンの定番ともいえるものだった。しかし近年では、DX化の浸透から、タブレットでのメニューに変える店舗もある。ただ、「タブレットだとワクワク感が減ってしまう」という顧客の声も多く、この木製メニューはまた少しずつ復活している。それが、食事を楽しむときの「ワクワク感」につながっていることがよくわかる。
あるいは最初に触れたが、特徴的な店内や外観も、びくドンを「特別感」のあるものにしているだろう。日常世界とは少し離れた「異空間」を形作るのが「テーマパーク」であるが、まさにびくドンは、こうした点から「選択と集中によるテーマパーク化」を行っているのである。
<TEXT/谷頭和希>
【谷頭和希】
ライター・作家。チェーンストアやテーマパークをテーマにした原稿を数多く執筆。一見平板に見える現代の都市空間について、独自の切り口で語る。「東洋経済オンライン」などで執筆中、文芸誌などにも多く寄稿をおこなう。著書に『ドンキにはなぜペンギンがいるのか』(集英社)『ブックオフから考える』(青弓社)
【関連記事】
・ 「びっくりドンキー」の“ホテル並み”豪華モーニングを実食。ワンコイン以下の独自メニューも
・ 不二家「ケーキ食べ放題」気づけば料金が3倍に…。店舗で“実食レポ”した本音
・ SNSで話題「他店より美味いマクドナルドがある」って本当?元店舗マネージャーは「入った瞬間にわかります」
・ 日本の評価を落とす「薄っぺらい商売」…観光地で「日本人が食べたことがないメニュー」を提供する歪さ
・ “高すぎる”と話題の「豊洲 千客万来」海鮮バイキングを実食。“最安値6000円以上”の価値はあるのか

生活 新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55