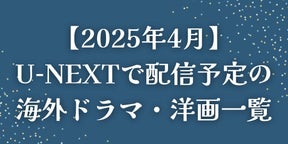年代別の退職金の相場とは。「勤続年数3年未満」だと出ない場合もあるって本当?
3月5日(水) 2:10
民間企業の退職金の平均相場は
厚生労働省が公表した「令和5年就労条件総合調査概況」によると、民間企業における勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者を対象とした調査では、退職金の平均額は表1の通りです。
表1
| 退職事由 | 大学・大学院卒 | 高校卒 |
|---|---|---|
| 定年 | 1896万円 | 1682万円 |
| 会社都合 | 1736万円 | 1385万円 |
| 自己都合 | 1441万円 | 1280万円 |
| 早期優遇 | 2266万円 | 2432万円 |
厚生労働省「令和5年就労条件総合調査概況」退職者1人平均退職給付額(勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の退職者)を基に筆者作成
退職理由によって支給額には大きな差があります。自己都合退職の場合は定年退職よりも金額が低くなる傾向にあります。一方、早期退職優遇制度を利用した場合は、定年退職を上回る金額が支給されることも特徴的です。
中小企業の退職金事情:年代・学歴・退職理由による差
産業労働局が公表している「中小企業の賃金・退職金事情」によると、学校卒業後すぐに入社し、一般的な能力と成績で勤務した場合のモデル退職金は表2の通りです。
表2
| 年代 | 自己都合 | 会社都合 |
|---|---|---|
| 20代 | 高校卒:90.7万円 | 高校卒:122.3万円 |
| 30代 |
高校卒: 170.5~272.9万円
大学卒:112.1~212.9万円 |
高校卒:214.8~328.4万円
大学卒:149.8~265.8万円 |
| 40代 |
高校卒:397.1~532.5万円
大学卒:343.1~490.6万円 |
高校卒:465.6~604.6万円
大学卒:414.7~578.2万円 |
| 50代 | 大学卒:653.6万円 | 大学卒:754.2万円 |
産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」モデル退職金を基に筆者作成
退職金の額は勤続年数が長くなるほど増加し、会社都合の方が有利であることが分かります。20代や30代での退職金は、自己都合・会社都合を問わず、比較的低い水準です。30代以降では、高校卒と大学卒で退職金に差があります。大学卒の方が全体的に高い水準になっていますが、その差は年代が上がるにつれてより顕著になります。
多くの企業では3年を退職一時金支給条件としている
産業労働局が発表した「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」によると、退職一時金を受給するための最低勤続年数は表3の通りです。
表3
| 1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年以上 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5% | 18% | 11.2% | 51.5% | 1.6% | 8.9% | 6.4% |
産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」退職一時金を受給するための最低勤続年数を基に筆者作成
表3によると、「勤続年数3年未満」では退職一時金が支給されないケースも一定数存在すると考えられます。
具体的には、1年未満(2.5%)・1年(18%)・2年(11.2%)を合わせると約31.7%の企業が、3年未満の勤続年数でも退職一時金を支給しています。しかし、逆に言えば、3年未満では退職一時金が支給されない企業もあるということになるでしょう。
「3年以上」の割合が51.5%と突出していることから、多くの企業では3年を支給条件としている可能性が高いといえます。3年未満の退職では支給されないケースがある一方で、支給される場合もあるため、企業ごとの規定を確認することが重要です。
民間企業で勤続20年以上の定年退職者の場合、高校卒では約1682万円、大学卒では約1896万円が平均的な金額
退職金の支給額は、勤続年数や退職理由、学歴、企業の規模によって大きく異なります。民間企業で勤続20年以上の定年退職者の場合、高校卒では約1682万円、大学卒では約1896万円が平均的な金額です。さらに、早期退職優遇制度を利用すると、2000万円以上の退職金が支給されるケースもあります。
中小企業においては、年代によって支給額に違いがみられます。20代での退職金はおおよそ100万円前後ですが、30代以降では学歴による差がより顕著になり、高校卒と大学卒では受け取る金額に違いが出てくるのです。特に40代や50代になると、その差はさらに大きくなる傾向があります。
勤続年数が3年未満の場合、退職金が支給されないことも少なくありません。実際に、3年未満の勤続でも退職金を支給する企業は全体の約3割にとどまる一方で、51.5%の企業が3年以上の勤続を退職金支給の条件としています。そのため、退職金を受け取れるかどうかは企業の規定によって異なります。
出典
厚生労働省令和5年就労条件総合調査概況
産業労働局中小企業の賃金・退職金事情
産業労働局中小企業の賃金・退職金事情
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
退職金を受け取った翌年、住民税がとんでもないことに…。事前にできる対策って?退職するなら65歳よりも、64歳と11ヶ月のほうがお得? いったいどういうこと?
59歳で貯蓄は「2500万」です。60歳でリタイアしても暮らしていけますか?

新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55