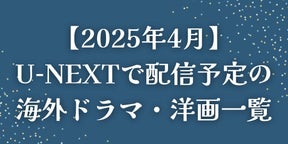la farfa magazine-ぽっちゃり女子のおしゃれ応援メディア-ラ・ファーファ公式サイト
「耳鳴り」はなぜ起こる? 考えられる病気や対策方法についてご紹介
2月24日(月) 23:00
提供:
外部の音がないのに耳から「ジー」「キーン」「ザー」といった音が聞こえて悩んでいませんか?耳の中で雑音がしていると、そのことが気になって生活の質が低下してしまいますよね。耳の中の雑音が気になって眠れなくなっている人、もしかしたら重大な病気かもしれないと不安を感じている人もいるかもしれません。
耳鳴りの種類や原因・対策方法について、あんしん漢方の山形ゆかりさんに解説していただきました。
|1. 耳鳴りの種類
 耳鳴りには大きく分けて「自覚的耳鳴り」と「他覚的耳鳴り」の2種類があります。耳鳴りを感じる人のうち、自覚的耳鳴りに悩まされている人のほうが圧倒的に多く、また人によっては難聴を伴うという人もいます ※1。
耳鳴りには大きく分けて「自覚的耳鳴り」と「他覚的耳鳴り」の2種類があります。耳鳴りを感じる人のうち、自覚的耳鳴りに悩まされている人のほうが圧倒的に多く、また人によっては難聴を伴うという人もいます ※1。
| 自覚的耳鳴り
自覚的耳鳴りは、本人にしか聞こえない耳鳴りです。耳鳴りの中で最も一般的で、「ジー」「キーン」「ボー」「ブーン」といった音が聞こえるのが特徴です。
音を処理する脳の部位(聴覚皮質)の異常な活動が原因とされており、特に耳に関連する病気の症状としてあらわれることが多いと言われています。
| 他覚的耳鳴り
他覚的耳鳴りは、聴診器などを用いれば、本人以外にも音を聞き取れる場合がある耳鳴りのことです。からだのどこかに雑音を発生させている原因があります。
例えば、血管の異常による場合は動脈硬化などにより血流が雑音として聞こえます。「ザー」や「ドクドク」という音がするのが特徴です。その他にも「カチカチ」という音が聞こえていたら、他覚的耳鳴りの可能性があります。
|2. 耳鳴りの種類別に考えられる病気
 耳鳴りの症状は、何らかの病気の影響で生じているかもしれません。それぞれの耳鳴りでどのような病気が考えられるかご説明します。
耳鳴りの症状は、何らかの病気の影響で生じているかもしれません。それぞれの耳鳴りでどのような病気が考えられるかご説明します。
| 自覚的耳鳴りの場合
自覚的耳鳴りの症状を感じている人は、次のような病気が疑われます。
▼大きな音にさらされたことによる音響外傷
▼聴器毒性のある薬剤による耳の損傷
▼メニエール病
▼片頭痛
このなかでも、音響外傷の場合は耳鳴りが両耳から聞こえ、メニエール病の場合は「キーン」という金属音の耳鳴りが片耳から聞こえることがあるなど、病気によって耳鳴りの聞こえ方が異なる場合があります。
その他にも、中耳の感染や過剰な耳あか、アレルギーによる耳管(耳と鼻をつなぐ管)のトラブルなども、耳鳴りを起こす原因のひとつです。さらに稀なケースとして「前庭神経鞘腫」という、がんではない良性の腫瘍が原因となることもあります。
| 他覚的耳鳴りの場合
他覚的耳鳴りの症状を感じる人は、ごく少ないとされていますが、この症状を感じていたら次のような病気を疑いましょう。
▼頸動脈または内頸静脈を通る血流の乱れ
▼中耳腫瘍
▼脳を覆う膜(硬膜)の血管の奇形
他覚的耳鳴は、通常は首の太い血管の速い血流または血流の乱れからくる雑音です。この異常な血流は、赤血球数の減少(貧血)や動脈の詰まり(動脈硬化)によって起こることがあり、高血圧のコントロールがうまくいっていない人ではよりひどくなる可能性があります。
稀に、上顎の前の硬い部分にあたる硬口蓋の筋肉や中耳にある小さな筋肉がけいれんして「カチカチ」といった雑音が生じることもあります。
|3. 耳鳴りの対策方法
 耳鳴りの症状はさまざまで、人によっては原因がはっきりしないまま長い期間耳鳴りに悩まされていることもあります。症状を和らげるための方法を5つご紹介するので、自分に合ったケアを見つけてみてください。
耳鳴りの症状はさまざまで、人によっては原因がはっきりしないまま長い期間耳鳴りに悩まされていることもあります。症状を和らげるための方法を5つご紹介するので、自分に合ったケアを見つけてみてください。
| ストレスを解消する
ストレスは耳鳴りを悪化させる要因とされています。リラックスできる環境をつくり、深呼吸やヨガなどを取り入れてみましょう。気持ちを落ち着かせ、十分な休息をとって体力を回復させることで耳鳴りの軽減が期待できます。
また、耳鳴りを気にしすぎないことも大切です。耳鳴りに意識を向けすぎると、かえって気になり、さらに大きく聞こえるという悪循環に陥ってしまいます。自分に合ったリフレッシュ方法で、心身をリラックスさせましょう。
| 生活習慣を見直す
生活習慣の見直しは、健康的な生活を送る基本です。睡眠時間は6時間以上とるようにしましょう ※2。
スマートフォンやテレビから放出されるブルーライトを浴びると、入眠が妨げられます。就寝前についついスマートフォンを触ってしまう人がいるかもしれませんが、デジタルデトックスをする日を設け、ブルーライトを避けるようにしましょう。
運動習慣がない人やデスクワークが多い人は、階段を使ったり、定期的に立ち上がってストレッチをしたりするなど適度な運動を心がけることも大切です。
また、栄養バランスのとれた規則正しい食事を摂り、耳や脳などの健康維持に必要な栄養を積極的に摂ることも耳鳴り対策として効果的です。
| 音のある環境をつくる
耳鳴りの軽減には音響療法も効果的です。音響療法とは、耳鳴りよりも小さな音を聞き続け、耳鳴りが際立つような静かな環境をなるべくつくらないようにする療法のことです。
継続することで、耳鳴りが気にならなくなるようにしていきます。すぐに効果がでるものではないので、根気よく続けていきましょう。
| ツボを刺激する
耳鳴りの対策には、日常生活で簡単にできるツボ押しもおすすめ。耳鳴りの改善に効果があるといわれているツボのひとつが「翳風(えいふう)」です。
翳風は耳たぶの後ろにある突出した骨と、耳たぶの間のくぼみ部分のことです。ツボ押しをするときは、人差し指や親指で「気持ちいい」と感じる程度に押してみましょう。
| 漢方薬を試してみる
耳鳴りの症状に悩む人には、症状の根本改善を得意とする漢方薬を飲むのもおすすめです。漢方薬は、「耳鳴り」に効果が認められているものもあり、耳鼻科での治療にも使われています。
耳鳴りを解消するさまざまな対策をご紹介してきましたが、忙しい毎日のなかで、すぐにストレスを軽減したり、生活習慣を見直したりすることは難しいかもしれません。そんなときでも、漢方薬は毎日飲むだけなので、無理せず続けることができますよ。
耳鳴りの改善には、「血流をよくして内耳や神経の機能を回復する」「水分代謝をよくして内耳のむくみを改善する」「自律神経を整えてストレスによる耳鳴りを改善する」などの作用のある生薬を含む漢方薬を選ぶといいでしょう。
<耳鳴りでお悩みの人におすすめの漢方薬>
苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)
胃腸の水分代謝を促して余分な水分を取り除くことで、耳鳴りやめまいなどの症状を改善します。胃腸が弱く、冷えがあり、めまいがある人のたちくらみ、頭痛などにも用いられます。
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
栄養を補い、血行を促進して水分代謝を整えることで、耳鳴りを改善します。比較的体力が乏しく、冷えや貧血などのある人の耳鳴り、めまいなどに使用します。
漢方薬を選ぶときは、その人の状態や体質に合ったものを選ぶことが重要です。うまく合っていないと十分な効果を得られず、場合によっては副作用が生じることもあります。しかし、たくさんある漢方薬の中から、自分に合うものを選ぶのは難しいですよね。
そんなときには、「 あんしん漢方 」など漢方薬に特化したオンライン漢方サービスに、相談してみるのもいいでしょう。あんしん漢方では、漢方薬に精通した薬剤師がAIを用いて、あなたに適した漢方薬を提案してくれます。プロの選んだ漢方薬が、お手頃価格で自宅に郵送されるのもおすすめポイントです。
|4. 耳鳴りには自分に合った対策を!
耳鳴りは原因や症状がさまざまで、生活の質を大きく左右します。しかし、適切な対策を取ることで症状を和らげることが可能です。
ストレス管理や生活習慣の見直し、音響療法、ツボ押し、漢方薬などを試して、自分に合った方法を見つけてみましょう。
<この記事の監修者>
 あんしん漢方薬剤師
あんしん漢方薬剤師
山形ゆかり
薬剤師・薬膳アドバイザー・フードコーディネーター。
病院薬剤師として在勤中、食養生の大切さに気付き薬膳の道へ入り、牛角・吉野家他薬膳レストランなど15社以上のメニュー開発にも携わる。症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホひとつで相談、症状緩和と根本改善を目指す オンラインAI漢方「あんしん漢方」 でも薬剤師としてサポートを行う。
<参考文献>
※1 MSD家庭版マニュアル「耳鳴り」
※2 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」
【関連記事】
睡眠ホルモン「メラトニン」で睡眠の質を改善するには? 分泌を促す方法を医師が解説!
「デトックス」ってどんな効果がある? おすすめ食材を管理栄養士が解説!
肌が老化する原因は? 老化のサインや対策方法を解説
「いつもと味が違う」と感じたら味覚障害かも!? 味覚の変化の原因や対策方法を解説
【腸活】で冬の不調を予防しよう! おすすめの食材やポイントを解説
耳鳴りの種類や原因・対策方法について、あんしん漢方の山形ゆかりさんに解説していただきました。
|1. 耳鳴りの種類
 耳鳴りには大きく分けて「自覚的耳鳴り」と「他覚的耳鳴り」の2種類があります。耳鳴りを感じる人のうち、自覚的耳鳴りに悩まされている人のほうが圧倒的に多く、また人によっては難聴を伴うという人もいます ※1。
耳鳴りには大きく分けて「自覚的耳鳴り」と「他覚的耳鳴り」の2種類があります。耳鳴りを感じる人のうち、自覚的耳鳴りに悩まされている人のほうが圧倒的に多く、また人によっては難聴を伴うという人もいます ※1。
| 自覚的耳鳴り
自覚的耳鳴りは、本人にしか聞こえない耳鳴りです。耳鳴りの中で最も一般的で、「ジー」「キーン」「ボー」「ブーン」といった音が聞こえるのが特徴です。
音を処理する脳の部位(聴覚皮質)の異常な活動が原因とされており、特に耳に関連する病気の症状としてあらわれることが多いと言われています。
| 他覚的耳鳴り
他覚的耳鳴りは、聴診器などを用いれば、本人以外にも音を聞き取れる場合がある耳鳴りのことです。からだのどこかに雑音を発生させている原因があります。
例えば、血管の異常による場合は動脈硬化などにより血流が雑音として聞こえます。「ザー」や「ドクドク」という音がするのが特徴です。その他にも「カチカチ」という音が聞こえていたら、他覚的耳鳴りの可能性があります。
|2. 耳鳴りの種類別に考えられる病気
 耳鳴りの症状は、何らかの病気の影響で生じているかもしれません。それぞれの耳鳴りでどのような病気が考えられるかご説明します。
耳鳴りの症状は、何らかの病気の影響で生じているかもしれません。それぞれの耳鳴りでどのような病気が考えられるかご説明します。
| 自覚的耳鳴りの場合
自覚的耳鳴りの症状を感じている人は、次のような病気が疑われます。
▼大きな音にさらされたことによる音響外傷
▼聴器毒性のある薬剤による耳の損傷
▼メニエール病
▼片頭痛
このなかでも、音響外傷の場合は耳鳴りが両耳から聞こえ、メニエール病の場合は「キーン」という金属音の耳鳴りが片耳から聞こえることがあるなど、病気によって耳鳴りの聞こえ方が異なる場合があります。
その他にも、中耳の感染や過剰な耳あか、アレルギーによる耳管(耳と鼻をつなぐ管)のトラブルなども、耳鳴りを起こす原因のひとつです。さらに稀なケースとして「前庭神経鞘腫」という、がんではない良性の腫瘍が原因となることもあります。
| 他覚的耳鳴りの場合
他覚的耳鳴りの症状を感じる人は、ごく少ないとされていますが、この症状を感じていたら次のような病気を疑いましょう。
▼頸動脈または内頸静脈を通る血流の乱れ
▼中耳腫瘍
▼脳を覆う膜(硬膜)の血管の奇形
他覚的耳鳴は、通常は首の太い血管の速い血流または血流の乱れからくる雑音です。この異常な血流は、赤血球数の減少(貧血)や動脈の詰まり(動脈硬化)によって起こることがあり、高血圧のコントロールがうまくいっていない人ではよりひどくなる可能性があります。
稀に、上顎の前の硬い部分にあたる硬口蓋の筋肉や中耳にある小さな筋肉がけいれんして「カチカチ」といった雑音が生じることもあります。
|3. 耳鳴りの対策方法
 耳鳴りの症状はさまざまで、人によっては原因がはっきりしないまま長い期間耳鳴りに悩まされていることもあります。症状を和らげるための方法を5つご紹介するので、自分に合ったケアを見つけてみてください。
耳鳴りの症状はさまざまで、人によっては原因がはっきりしないまま長い期間耳鳴りに悩まされていることもあります。症状を和らげるための方法を5つご紹介するので、自分に合ったケアを見つけてみてください。
| ストレスを解消する
ストレスは耳鳴りを悪化させる要因とされています。リラックスできる環境をつくり、深呼吸やヨガなどを取り入れてみましょう。気持ちを落ち着かせ、十分な休息をとって体力を回復させることで耳鳴りの軽減が期待できます。
また、耳鳴りを気にしすぎないことも大切です。耳鳴りに意識を向けすぎると、かえって気になり、さらに大きく聞こえるという悪循環に陥ってしまいます。自分に合ったリフレッシュ方法で、心身をリラックスさせましょう。
| 生活習慣を見直す
生活習慣の見直しは、健康的な生活を送る基本です。睡眠時間は6時間以上とるようにしましょう ※2。
スマートフォンやテレビから放出されるブルーライトを浴びると、入眠が妨げられます。就寝前についついスマートフォンを触ってしまう人がいるかもしれませんが、デジタルデトックスをする日を設け、ブルーライトを避けるようにしましょう。
運動習慣がない人やデスクワークが多い人は、階段を使ったり、定期的に立ち上がってストレッチをしたりするなど適度な運動を心がけることも大切です。
また、栄養バランスのとれた規則正しい食事を摂り、耳や脳などの健康維持に必要な栄養を積極的に摂ることも耳鳴り対策として効果的です。
| 音のある環境をつくる
耳鳴りの軽減には音響療法も効果的です。音響療法とは、耳鳴りよりも小さな音を聞き続け、耳鳴りが際立つような静かな環境をなるべくつくらないようにする療法のことです。
継続することで、耳鳴りが気にならなくなるようにしていきます。すぐに効果がでるものではないので、根気よく続けていきましょう。
| ツボを刺激する
耳鳴りの対策には、日常生活で簡単にできるツボ押しもおすすめ。耳鳴りの改善に効果があるといわれているツボのひとつが「翳風(えいふう)」です。
翳風は耳たぶの後ろにある突出した骨と、耳たぶの間のくぼみ部分のことです。ツボ押しをするときは、人差し指や親指で「気持ちいい」と感じる程度に押してみましょう。
| 漢方薬を試してみる
耳鳴りの症状に悩む人には、症状の根本改善を得意とする漢方薬を飲むのもおすすめです。漢方薬は、「耳鳴り」に効果が認められているものもあり、耳鼻科での治療にも使われています。
耳鳴りを解消するさまざまな対策をご紹介してきましたが、忙しい毎日のなかで、すぐにストレスを軽減したり、生活習慣を見直したりすることは難しいかもしれません。そんなときでも、漢方薬は毎日飲むだけなので、無理せず続けることができますよ。
耳鳴りの改善には、「血流をよくして内耳や神経の機能を回復する」「水分代謝をよくして内耳のむくみを改善する」「自律神経を整えてストレスによる耳鳴りを改善する」などの作用のある生薬を含む漢方薬を選ぶといいでしょう。
<耳鳴りでお悩みの人におすすめの漢方薬>
苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)
胃腸の水分代謝を促して余分な水分を取り除くことで、耳鳴りやめまいなどの症状を改善します。胃腸が弱く、冷えがあり、めまいがある人のたちくらみ、頭痛などにも用いられます。
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
栄養を補い、血行を促進して水分代謝を整えることで、耳鳴りを改善します。比較的体力が乏しく、冷えや貧血などのある人の耳鳴り、めまいなどに使用します。
漢方薬を選ぶときは、その人の状態や体質に合ったものを選ぶことが重要です。うまく合っていないと十分な効果を得られず、場合によっては副作用が生じることもあります。しかし、たくさんある漢方薬の中から、自分に合うものを選ぶのは難しいですよね。
そんなときには、「 あんしん漢方 」など漢方薬に特化したオンライン漢方サービスに、相談してみるのもいいでしょう。あんしん漢方では、漢方薬に精通した薬剤師がAIを用いて、あなたに適した漢方薬を提案してくれます。プロの選んだ漢方薬が、お手頃価格で自宅に郵送されるのもおすすめポイントです。
|4. 耳鳴りには自分に合った対策を!
耳鳴りは原因や症状がさまざまで、生活の質を大きく左右します。しかし、適切な対策を取ることで症状を和らげることが可能です。
ストレス管理や生活習慣の見直し、音響療法、ツボ押し、漢方薬などを試して、自分に合った方法を見つけてみましょう。
<この記事の監修者>
 あんしん漢方薬剤師
あんしん漢方薬剤師
山形ゆかり
薬剤師・薬膳アドバイザー・フードコーディネーター。
病院薬剤師として在勤中、食養生の大切さに気付き薬膳の道へ入り、牛角・吉野家他薬膳レストランなど15社以上のメニュー開発にも携わる。症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホひとつで相談、症状緩和と根本改善を目指す オンラインAI漢方「あんしん漢方」 でも薬剤師としてサポートを行う。
<参考文献>
※1 MSD家庭版マニュアル「耳鳴り」
※2 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」
【関連記事】
睡眠ホルモン「メラトニン」で睡眠の質を改善するには? 分泌を促す方法を医師が解説!
「デトックス」ってどんな効果がある? おすすめ食材を管理栄養士が解説!
肌が老化する原因は? 老化のサインや対策方法を解説
「いつもと味が違う」と感じたら味覚障害かも!? 味覚の変化の原因や対策方法を解説
【腸活】で冬の不調を予防しよう! おすすめの食材やポイントを解説

生活 新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55