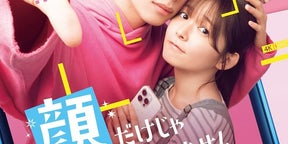実父と義父から今後のためにと合計「500万円」もらいました。贈与税はもらった相手との関係で税率が変わると聞きましたが、いくらになるのでしょうか?
2月15日(土) 14:30
贈与税の特例税率と一般税率とは
財産を受け取ったときに課される贈与税には、税率が2種類定められています。祖父母や両親といった直系尊属から成人済みの子どもが贈与されたときの「特例税率」と、それ以外の「一般税率」です。
贈与税は基礎控除(110万円)を受け取った合計額から引いた金額に課税されます。課税される金額が一定以上になると、それぞれの税率で課される割合が変わるため税額も変わります。税率の種類ごとの割合は表1の通りです。
表1
| 課税される金額 | 特例税率(控除額) | 一般税率(控除額) |
|---|---|---|
| ~200万円 | 10%(-) | |
| ~300万円 | 15%(10万円) | 15%(10万円) |
| ~400万円 | 20%(25万円) | |
| ~600万円 | 20%(30万円) | 30%(65万円) |
| ~1000万円 | 30%(90万円) | 40%(125万円) |
| ~1500万円 | 40%(190万円) | 45%(175万円) |
| ~3000万円 | 45%(265万円) | 50%(250万円) |
| ~4500万円 | 50%(415万円) | 55%(400万円) |
| 4500万円超 | 55%(640万円) | |
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に筆者作成
表1からも分かるように、特例税率の方が税金の負担は軽くなります。
もし、自身が成人している状態で義父と実父から贈与された場合、それぞれの税率は、義父から受け取った金額には一般税率、実父からの分は特例税率です。一方、もし、自身が成人していなければ、どちらから受け取ったとしても一般税率になります。
税率が2種類とも適用されるときの計算方法
一般税率と特例税率がともに適用されるときは、それぞれの税率で贈与税額を求めたあとに、適用される金額の割合を求め、合計します。具体的な手順は以下の通りです。
(1)贈与総額から基礎控除を引く
(2)(1)の金額をすべて特例税率で計算し、実際に適用される割合で乗じる
(3)(1)の金額をすべて一般税率で計算し、実際に適用される割合で乗じる
(4)(2)と(3)を合計する
500万円受け取るといくらになる?
今回は、以下の条件で財産を受け取ったときの贈与税額を求めます。
・250万円を実父、250万円を義父から受け取る
・同じ年にほかの贈与はない
・受け取る本人は成人済み
まず、500万円から基礎控除を引くと390万円です。条件を基にすると、実父から受け取った分は特例税率、義父から受け取った分は一般税率になります。計算をすると、特例税率分の贈与税は24万2500円、一般税率分は26万5000円になるため、贈与税は合計50万7500円です。
受け取ったお金の目的によっては非課税になるケースも
贈与税には、受け取ったお金の目的によって非課税になる項目が設けられています。例えば、入学祝いやお年玉、香典などは、社会通念上相当と認められる金額の範囲であれば非課税です。
また、親子間や夫婦間などの扶養義務者から生活費や教育費のために渡されたお金も、直接そのお金を生活費や教育費に使用していれば非課税になります。ただし、貯金に回したり株に使用したりすると課税対象です。
実父や義父から受け取ったお金が、これらの非課税項目に該当する場合は、実際の税額も変動する可能性があります。
実父と義父から250万円ずつ受け取った場合は50万7500円の税金が課される可能性がある
贈与税は、自身が成人しているか、また贈与された相手が直系尊属か否かで税率が変わります。実父から成人している子どもが贈与された場合は特例税率ですが、義父からの場合は直系尊属でないため一般税率です。
1年で受け取った金額がどちらも適用されるときは、計算時に間違えないようにしましょう。今回のケースだと、50万7500円の贈与税が課される可能性があります。なお、非課税項目に該当する金額が含まれているときは、税額が変わる場合があります。
出典
国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
夫の口座から妻の口座にお金を移した。贈与税がかかるって本当?祖母から結婚資金として「300万円」もらいました。税金ってかからないんですか?
娘の大学費用が足りないと言ったところ、母が「400万円」援助してくれました。「200万円」で足りそうなのですが、余剰分もまとめて受け取ってよいでしょうか?

新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55