
『リング』の脚本を手掛けるなど“Jホラー”ブームを牽引した高橋洋へのインタビューを敢行/各配信サービスにて配信中![c]1998「リング」「らせん」製作委員会
“Jホラーの創始者”高橋洋が語る、ホラーシーンの現在。『リング』からフェイクドキュメンタリーへ
1月22日(水) 11:30
『リング』(98)や『呪怨 劇場版』(03)の大ヒットによって地位を確立した“Jホラー”。ブーム最盛期から四半世紀が経ったが、ここ数年、国内ではホラーブームが再燃しているといわれている。このブームの特徴は、「ゾゾゾ」や「フェイクドキュメンタリー『Q』」に代表されるYouTube発のコンテンツや、「変な家」や「近畿地方のある場所について」などのネット発のベストセラーなど、従来とは異なるメディアから次々とヒットが生まれていることだ。
【写真を見る】衝撃のビジュアル…「イシナガキクエを探しています」失踪した女性が口からエクトプラズムを放出する瞬間の写真

PRESS HORRORでは、『女優霊』(96)や「リング」シリーズの脚本を手掛け、昨今では『霊的ボリシェヴィキ』(17)や『ザ・ミソジニー』(22)といった監督作でも知られる高橋洋へのインタビューを敢行。“Jホラー”という概念をあらためて問うと共に、ジャンルの第一人者である高橋がホラーブームの現状について感じていることについても語ってもらった。
■「“Jホラー”で重要なのは、日常の延長線上に異界が存在している…という感覚」

“Jホラー”という言葉が広く使われるようになって久しいが、その言葉の示す概念を説明できる者は数少ないだろう。このジャンルを定義付けるものはなんなのか?という我々の率直かつ抽象的な疑問に対して、高橋は「“得体の知れないなにか”に近づくこと」だと答えてくれた。
「“Jホラー”で重要なのは、私たちが生きている日常の延長線上には、よくわからない異界が存在している…。という感覚です。ベール一枚を隔てた向こうにはよくわからないものがあり、たまたまそれに触れてしまったがゆえに日常生活を送れなくなった人間たちが、怖くて近づきたくないのに後戻りもできず、核心部分に迫っていかざるを得なくなる、という物語が“Jホラー”ではしばしば描かれています」。
高橋の発言を踏まえて考えてみると、“観ると一週間で死ぬ”ビデオテープの恐怖を描いた「リング」シリーズ、強い恨みを持って死亡した女性の怨念が拡散していく「呪怨」シリーズは、“得体の知れないなにか”に近づく物語の代表格と言っていいだろう。

高橋は前掲したような、昨今ブームになっているホラー作品にも関心を持って見聞きしているそうだ。テレビ東京で放送された失踪した女性の公開捜査番組という設定のモキュメンタリー「TXQ FICTION/イシナガキクエを探しています」や、同作を手掛けたテレビ東京の大森時生プロデューサー、ホラー作家の梨、株式会社闇のタッグによる展覧会「行方不明展」、心霊スポットなどを探索するYouTubeチャンネル「ゾゾゾ」といった映画以外のコンテンツの美点に触れながら、それらのなかにも「“Jホラー”的な恐怖表現が息づいているのではないか」と指摘する。
「昨今ブームになっている『行方不明展』などのフェイクドキュメンタリー的な作品群にも、よくわからない世界が日常のなかで口を開けて待ち構えているんだ、というコンセプトが根本にあるように感じます。そして、若い世代を中心にしたお客さんが、自分たちが感じ取っている日常の不確かさの感覚をこうした作品の中に見出して共感が得られているように思います」。

「イシナガキクエを探しています」では、失踪した女性が口からエクトプラズム(物質化された霊体)を放出する姿を収めた心霊写真が劇中に登場するが、高橋はこのビジュアルが「とても印象的だった」と語る。「この写真のエクトプラズムはCGではなく、19世紀末のイギリスの降霊実験で使われた、白いシーツを駆使したアナログなトリック撮影が採用されたようですね。『ありそう』と思わせる心霊写真の作り方としていい着眼点だと思いますし、写真自体もインパクトがありました。シャッタースピードも何パターンも試すなどいろいろな工夫がされているのではないでしょうか」とクリエイターならではの視点で、リアリティを生みだす仕掛けを称賛する。

■「過剰に説明してしまうと、ただの“おはなし”になってしまいます」
鈴木光司による同名小説を映像化し、Jホラーブームの火付け役となった『リング』。実は原作はミステリーが主軸であり、呪いのビデオの謎を追う推理劇が中心の構成になっている。映画化の過程でミステリーからホラーへとジャンルをシフトしていった経緯について、当時を振り返ってもらった。
「原作における高山竜司(真田広之)は頭脳明晰な一般人で、彼の推理によって呪いの起源がひも解かれていくのですが、そこを丁寧に描写していくには映画の尺や構成のなかでは制約があったため、高山に霊能力を持たせることにしました。そして、霊能力ゆえに生きづらさを抱えた人物として描写しています。また、浅川玲子(松嶋菜々子)も男性から女性に変えたキャラクターで、映画では高山とは元夫婦という設定にしているのですが、彼女は霊能力を持たないがゆえに恐怖に怯える、という対照的なキャラクター像を描こうとした結果、このようなアレンジになったのだと記憶しています」。

この『リング』をはじめ、“得体の知れないなにか”に対する恐怖をいかに描きだすかということを、作品を通して追求してきた高橋。物語を構築するうえで気を付けていることについて尋ねると、以下のように答えてくれた。
「“得体の知れないなにか”が背後にあるという感覚を、あえて語り過ぎないようにしています。過剰に説明してしまうとただの“おはなし”になってしまうからです。ただ、あまりにもわからなさ過ぎると、今度は観客がついてこられなくなってしまう。なので、そのさじ加減をすごく気にしながら執筆していますね」。
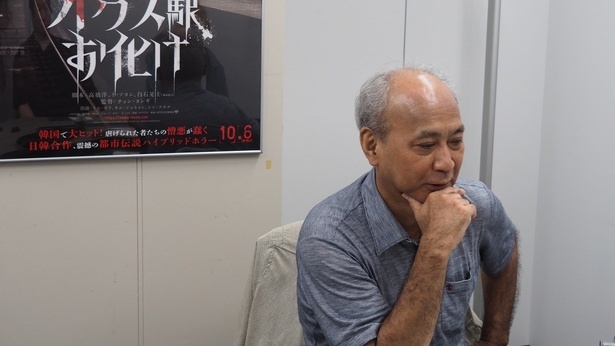
このような試行錯誤を重ねて書き上げられる脚本ではあるが、最終的には撮影現場における監督の判断が重要になってくるとも説明する。「例えば、『リング』の貞子のビジュアルをどうするかなどといった部分では、脚本段階での描写には限界がありますよね。また、Jホラーで大事になってくるのは、画面に映っていないところに『なにかがいる…』という感覚をいかに観客に伝えるかということです。これも現場で実際に撮影してみないとわかりません。そこをうまく調整するのが監督の腕の見せ所だと考えています」。
■「空間が変容していく感覚が表現されていて、スクリーンに釘付けになってしまった」
そんな高橋がいま注目している作品が、『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』(1月24日公開)だ。本作は「第2回日本ホラー映画大賞」にて大賞を受賞した近藤亮太監督が、受賞短編を自ら長編映画化した商業長編映画監督デビュー作で、総合プロデュースを、「日本ホラー映画大賞」の選考委員長である清水崇監督が務めている。
主人公は、子ども時代に弟が失踪したことがトラウマとなって心に残り続け、行方不明者を探す山岳ボランティア活動をしている青年、敬太(杉田雷麟)。ある日、彼のもとに母親から弟の日向(白鳥廉)が失踪した瞬間を撮影したビデオテープが送られてきたことから、彼の同居人で霊感を持つ司(平井亜門)、失踪事件を追う新聞記者の美琴(森田想)も巻き込み、敬太はかつて弟が消えた“山”へと導かれていく。

近藤監督は映画美学校時代に高橋の授業を受講しており、高橋が監督した『霊的ボリシェヴィキ』では実習の一環として助監督も務めた、いわば“師弟”の関係。『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』もすでに鑑賞している高橋は、本作において印象的だった描写を解説してくれた。
「例えば、敬太と司が敬太の実家を訪れ、キッチンのダイニングテーブルに座って話すシーンにはすごく求心力があると感じました。長回しで撮影されているのですが、司がなんとなく握っていた野球ボールがいつの間にかこぼれ落ち、カットが変わると非現実的にいきなり出現したみたいにポンポンと床の奥に転がってゆく。いまにもなにかが起こりそうな、だんだんと空間が変容していく感覚が表現されていて、スクリーンに釘付けになってしまいました」。

夜間、薄暗い車中にいる司が美琴とリモートで会話をするシーンにも惹かれるものがあったそう。「リモートで会話する人々を描写しようとすると、普通はPCやタブレットなどデバイスを含めて撮りたくなるところですが、美琴が話しているところはデバイスの画面のみを映していたことに感心しました。画面内画面で、いわば入れ子の映像になっているわけですが、彼女の不安で引きつった表情がスクリーンいっぱいに広がることで、2人の緊張感が観客にも伝わってきますし、画面の外になにがあるのかと想像させることで、非常に忌まわしいものを感じました」。

作品の魅力を次々と挙げてくれた高橋だが、「もっと攻めていいのでは?」と感じた箇所もあったと明かす。その理由について、「近藤監督が長回しの画面からカットを割って切り返すタイミングはカチッとセオリー通りで、テクニックとしても上手い。彼の作家性もあって日常的な世界観をベースにしていることは理解できるのですが、もっと虚構の世界に振ってありえないことを成立させることにも挑戦していってほしいですね」と語り、弟子の成長ぶりに目を細めつつ、次回作でのさらなる飛躍に期待をこめる。
「いまの若いクリエイターたちが作る作品にはディテールを追求したものが多く、こだわりを掘り下げて切磋琢磨していく姿勢は一種の共闘運動を思わせますし、私や黒沢(清)監督たちが競い合っていた時代にも似たホラージャンルの盛り上がりを感じています。一方で、ホラーに特化していない一般の映画ファンが『え!』と衝撃を受けるような、視覚的な派手さのある作品にはなかなか出会えていないのも事実なので、既存の想像力をぶち破るような作品が出てくるとまたおもしろくなりますね。…といいつつ私も、世に受け入れてもらえない作品を撮っていたりもするのですが(笑)、大衆性の重要さについては、事あるごとに後輩たちには伝えるようにしています」と現状の課題を挙げつつ、新しいムーブメントが起こることへの期待を寄せた。

■「『シビル・ウォー アメリカ最後の日』には、本当にヤバいものに近づくリアリティが全編に感じられた」
最後に、最近観た作品で「“得体の知れないなにか”に近づくこと」を感じた作品があったか?と尋ねると、意外にもアレックス・ガーランド監督の『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(24)をピックアップした。

「『シビル・ウォー』は内戦状態に陥ったアメリカが舞台で、記者たちが大統領へのインタビューを敢行するためにワシントンD.C.へと向かう物語ですが、首都に近づくにつれ、無秩序に陥った街の狂った光景を目の当たりにしてゆく。この構成は『地獄の黙示録』に通じるところがあり、ジャングルの奥地で狂ってしまったカーツ大佐を大統領に置き換えたとも言えます。本当にヤバいものに近づくリアリティが全編に感じられて、変なアドレナリンが出てしまいました(笑)。あとは児童誘拐を扱った『サウンド・オブ・フリーダム』なども、ちょっと陰謀論的な危うさは感じるんですが、映画としての完成度は高かったですね」。

『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』に続いては、あまりにも有名な“ネット怪談”を題材にしたスマッシュヒット作の続編『きさらぎ駅 Re:』(初夏公開)、背筋によるカクヨム発のベストセラー小説を白石晃士監督が映画化した『近畿地方のある場所について』(2025年公開)、社会現象となった“異変”探し無限ループゲームを実写化した『8番出口』(2025年公開)など、ネット発の話題作が複数待機している国内のホラー映画シーン。高橋が待ち望んでいる世間を巻き込むようなインパクトのある作品は生まれるのか。このムーブメントの向かう先にも注目していきたい。

取材・文/平尾嘉浩
【関連記事】
・ 『リング』『呪怨』『犬鳴村』…ホラーの大ヒットが“冬”に続出する深いワケとは
・ 「第2回日本ホラー映画大賞」から約2年…『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』が東京国際映画祭でついに全世界お披露目!
・ デビュー25周年!“マスター・オブ・Jホラー”清水崇の軌跡…『呪怨』から『あのコはだぁれ?』へ
・ 「日本ホラー映画大賞」受賞作上映会に、ホラー映画界の新たな才能たちが集結!制作の舞台裏や次回作の構想を語り合う
・ 『呪怨』に憧れて上京し、映画監督に!Jホラーの“次世代”が清水崇監督と夢の対談「ようやく一歩踏みだせた」
【写真を見る】衝撃のビジュアル…「イシナガキクエを探しています」失踪した女性が口からエクトプラズムを放出する瞬間の写真

PRESS HORRORでは、『女優霊』(96)や「リング」シリーズの脚本を手掛け、昨今では『霊的ボリシェヴィキ』(17)や『ザ・ミソジニー』(22)といった監督作でも知られる高橋洋へのインタビューを敢行。“Jホラー”という概念をあらためて問うと共に、ジャンルの第一人者である高橋がホラーブームの現状について感じていることについても語ってもらった。
■「“Jホラー”で重要なのは、日常の延長線上に異界が存在している…という感覚」

“Jホラー”という言葉が広く使われるようになって久しいが、その言葉の示す概念を説明できる者は数少ないだろう。このジャンルを定義付けるものはなんなのか?という我々の率直かつ抽象的な疑問に対して、高橋は「“得体の知れないなにか”に近づくこと」だと答えてくれた。
「“Jホラー”で重要なのは、私たちが生きている日常の延長線上には、よくわからない異界が存在している…。という感覚です。ベール一枚を隔てた向こうにはよくわからないものがあり、たまたまそれに触れてしまったがゆえに日常生活を送れなくなった人間たちが、怖くて近づきたくないのに後戻りもできず、核心部分に迫っていかざるを得なくなる、という物語が“Jホラー”ではしばしば描かれています」。
高橋の発言を踏まえて考えてみると、“観ると一週間で死ぬ”ビデオテープの恐怖を描いた「リング」シリーズ、強い恨みを持って死亡した女性の怨念が拡散していく「呪怨」シリーズは、“得体の知れないなにか”に近づく物語の代表格と言っていいだろう。

高橋は前掲したような、昨今ブームになっているホラー作品にも関心を持って見聞きしているそうだ。テレビ東京で放送された失踪した女性の公開捜査番組という設定のモキュメンタリー「TXQ FICTION/イシナガキクエを探しています」や、同作を手掛けたテレビ東京の大森時生プロデューサー、ホラー作家の梨、株式会社闇のタッグによる展覧会「行方不明展」、心霊スポットなどを探索するYouTubeチャンネル「ゾゾゾ」といった映画以外のコンテンツの美点に触れながら、それらのなかにも「“Jホラー”的な恐怖表現が息づいているのではないか」と指摘する。
「昨今ブームになっている『行方不明展』などのフェイクドキュメンタリー的な作品群にも、よくわからない世界が日常のなかで口を開けて待ち構えているんだ、というコンセプトが根本にあるように感じます。そして、若い世代を中心にしたお客さんが、自分たちが感じ取っている日常の不確かさの感覚をこうした作品の中に見出して共感が得られているように思います」。

「イシナガキクエを探しています」では、失踪した女性が口からエクトプラズム(物質化された霊体)を放出する姿を収めた心霊写真が劇中に登場するが、高橋はこのビジュアルが「とても印象的だった」と語る。「この写真のエクトプラズムはCGではなく、19世紀末のイギリスの降霊実験で使われた、白いシーツを駆使したアナログなトリック撮影が採用されたようですね。『ありそう』と思わせる心霊写真の作り方としていい着眼点だと思いますし、写真自体もインパクトがありました。シャッタースピードも何パターンも試すなどいろいろな工夫がされているのではないでしょうか」とクリエイターならではの視点で、リアリティを生みだす仕掛けを称賛する。

■「過剰に説明してしまうと、ただの“おはなし”になってしまいます」
鈴木光司による同名小説を映像化し、Jホラーブームの火付け役となった『リング』。実は原作はミステリーが主軸であり、呪いのビデオの謎を追う推理劇が中心の構成になっている。映画化の過程でミステリーからホラーへとジャンルをシフトしていった経緯について、当時を振り返ってもらった。
「原作における高山竜司(真田広之)は頭脳明晰な一般人で、彼の推理によって呪いの起源がひも解かれていくのですが、そこを丁寧に描写していくには映画の尺や構成のなかでは制約があったため、高山に霊能力を持たせることにしました。そして、霊能力ゆえに生きづらさを抱えた人物として描写しています。また、浅川玲子(松嶋菜々子)も男性から女性に変えたキャラクターで、映画では高山とは元夫婦という設定にしているのですが、彼女は霊能力を持たないがゆえに恐怖に怯える、という対照的なキャラクター像を描こうとした結果、このようなアレンジになったのだと記憶しています」。

この『リング』をはじめ、“得体の知れないなにか”に対する恐怖をいかに描きだすかということを、作品を通して追求してきた高橋。物語を構築するうえで気を付けていることについて尋ねると、以下のように答えてくれた。
「“得体の知れないなにか”が背後にあるという感覚を、あえて語り過ぎないようにしています。過剰に説明してしまうとただの“おはなし”になってしまうからです。ただ、あまりにもわからなさ過ぎると、今度は観客がついてこられなくなってしまう。なので、そのさじ加減をすごく気にしながら執筆していますね」。
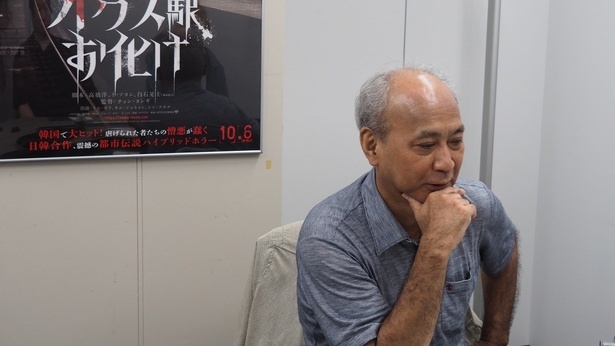
このような試行錯誤を重ねて書き上げられる脚本ではあるが、最終的には撮影現場における監督の判断が重要になってくるとも説明する。「例えば、『リング』の貞子のビジュアルをどうするかなどといった部分では、脚本段階での描写には限界がありますよね。また、Jホラーで大事になってくるのは、画面に映っていないところに『なにかがいる…』という感覚をいかに観客に伝えるかということです。これも現場で実際に撮影してみないとわかりません。そこをうまく調整するのが監督の腕の見せ所だと考えています」。
■「空間が変容していく感覚が表現されていて、スクリーンに釘付けになってしまった」
そんな高橋がいま注目している作品が、『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』(1月24日公開)だ。本作は「第2回日本ホラー映画大賞」にて大賞を受賞した近藤亮太監督が、受賞短編を自ら長編映画化した商業長編映画監督デビュー作で、総合プロデュースを、「日本ホラー映画大賞」の選考委員長である清水崇監督が務めている。
主人公は、子ども時代に弟が失踪したことがトラウマとなって心に残り続け、行方不明者を探す山岳ボランティア活動をしている青年、敬太(杉田雷麟)。ある日、彼のもとに母親から弟の日向(白鳥廉)が失踪した瞬間を撮影したビデオテープが送られてきたことから、彼の同居人で霊感を持つ司(平井亜門)、失踪事件を追う新聞記者の美琴(森田想)も巻き込み、敬太はかつて弟が消えた“山”へと導かれていく。

近藤監督は映画美学校時代に高橋の授業を受講しており、高橋が監督した『霊的ボリシェヴィキ』では実習の一環として助監督も務めた、いわば“師弟”の関係。『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』もすでに鑑賞している高橋は、本作において印象的だった描写を解説してくれた。
「例えば、敬太と司が敬太の実家を訪れ、キッチンのダイニングテーブルに座って話すシーンにはすごく求心力があると感じました。長回しで撮影されているのですが、司がなんとなく握っていた野球ボールがいつの間にかこぼれ落ち、カットが変わると非現実的にいきなり出現したみたいにポンポンと床の奥に転がってゆく。いまにもなにかが起こりそうな、だんだんと空間が変容していく感覚が表現されていて、スクリーンに釘付けになってしまいました」。

夜間、薄暗い車中にいる司が美琴とリモートで会話をするシーンにも惹かれるものがあったそう。「リモートで会話する人々を描写しようとすると、普通はPCやタブレットなどデバイスを含めて撮りたくなるところですが、美琴が話しているところはデバイスの画面のみを映していたことに感心しました。画面内画面で、いわば入れ子の映像になっているわけですが、彼女の不安で引きつった表情がスクリーンいっぱいに広がることで、2人の緊張感が観客にも伝わってきますし、画面の外になにがあるのかと想像させることで、非常に忌まわしいものを感じました」。

作品の魅力を次々と挙げてくれた高橋だが、「もっと攻めていいのでは?」と感じた箇所もあったと明かす。その理由について、「近藤監督が長回しの画面からカットを割って切り返すタイミングはカチッとセオリー通りで、テクニックとしても上手い。彼の作家性もあって日常的な世界観をベースにしていることは理解できるのですが、もっと虚構の世界に振ってありえないことを成立させることにも挑戦していってほしいですね」と語り、弟子の成長ぶりに目を細めつつ、次回作でのさらなる飛躍に期待をこめる。
「いまの若いクリエイターたちが作る作品にはディテールを追求したものが多く、こだわりを掘り下げて切磋琢磨していく姿勢は一種の共闘運動を思わせますし、私や黒沢(清)監督たちが競い合っていた時代にも似たホラージャンルの盛り上がりを感じています。一方で、ホラーに特化していない一般の映画ファンが『え!』と衝撃を受けるような、視覚的な派手さのある作品にはなかなか出会えていないのも事実なので、既存の想像力をぶち破るような作品が出てくるとまたおもしろくなりますね。…といいつつ私も、世に受け入れてもらえない作品を撮っていたりもするのですが(笑)、大衆性の重要さについては、事あるごとに後輩たちには伝えるようにしています」と現状の課題を挙げつつ、新しいムーブメントが起こることへの期待を寄せた。

■「『シビル・ウォー アメリカ最後の日』には、本当にヤバいものに近づくリアリティが全編に感じられた」
最後に、最近観た作品で「“得体の知れないなにか”に近づくこと」を感じた作品があったか?と尋ねると、意外にもアレックス・ガーランド監督の『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(24)をピックアップした。

「『シビル・ウォー』は内戦状態に陥ったアメリカが舞台で、記者たちが大統領へのインタビューを敢行するためにワシントンD.C.へと向かう物語ですが、首都に近づくにつれ、無秩序に陥った街の狂った光景を目の当たりにしてゆく。この構成は『地獄の黙示録』に通じるところがあり、ジャングルの奥地で狂ってしまったカーツ大佐を大統領に置き換えたとも言えます。本当にヤバいものに近づくリアリティが全編に感じられて、変なアドレナリンが出てしまいました(笑)。あとは児童誘拐を扱った『サウンド・オブ・フリーダム』なども、ちょっと陰謀論的な危うさは感じるんですが、映画としての完成度は高かったですね」。

『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』に続いては、あまりにも有名な“ネット怪談”を題材にしたスマッシュヒット作の続編『きさらぎ駅 Re:』(初夏公開)、背筋によるカクヨム発のベストセラー小説を白石晃士監督が映画化した『近畿地方のある場所について』(2025年公開)、社会現象となった“異変”探し無限ループゲームを実写化した『8番出口』(2025年公開)など、ネット発の話題作が複数待機している国内のホラー映画シーン。高橋が待ち望んでいる世間を巻き込むようなインパクトのある作品は生まれるのか。このムーブメントの向かう先にも注目していきたい。

取材・文/平尾嘉浩
【関連記事】
・ 『リング』『呪怨』『犬鳴村』…ホラーの大ヒットが“冬”に続出する深いワケとは
・ 「第2回日本ホラー映画大賞」から約2年…『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』が東京国際映画祭でついに全世界お披露目!
・ デビュー25周年!“マスター・オブ・Jホラー”清水崇の軌跡…『呪怨』から『あのコはだぁれ?』へ
・ 「日本ホラー映画大賞」受賞作上映会に、ホラー映画界の新たな才能たちが集結!制作の舞台裏や次回作の構想を語り合う
・ 『呪怨』に憧れて上京し、映画監督に!Jホラーの“次世代”が清水崇監督と夢の対談「ようやく一歩踏みだせた」
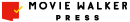
エンタメ 新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55





























