
ティミー・ハーン監督
母の愛と呪いは紙一重…フィリピン文化のリアルとカオスをノンジャンルに描く新世代「ウリリは黒魔術の夢をみた」監督インタビュー
4月5日(土) 1:00
提供:
わが子の成功を黒魔術でかなえようとした母の強い愛と、運命に翻弄された息子、そして現代フィリピンの文化と社会を反映させた物語をモノクローム映像で描いた「ウリリは黒魔術の夢をみた」が公開された。俳優、アート・ディレクター、脚本家、プロデューサーとフィリピン新時代のアーティストとしても注目を集めるティミー・ハーン監督の公式インタビューを映画.comが入手した。
<あらすじ>
ピナツボ火山の大噴火がフィリピン全土を揺るがした1991年、カルメンという女性とアメリカ人男性との間に赤ん坊が生まれる。カルメンは自分たちが大噴火を起こしたと信じるカルト集団の黒魔術に導かれ、息子に「プロのバスケ選手としてNBAで活躍する」運命を授け、自身の命を日本車ギャランに捧げる。NBAのスター選手の名を借りて「マイケル・ジョーダン・ウリリ」と名づけられた子どもは、才能あるプレイヤーへと成長。伝説の背番号「23」を背負い、恋人との肉欲とバスケ賭博に明け暮れる青春を過ごしていた。そんな中、ウリリにアメリカ行きのチャンスが舞い込むが、悪夢のような出来事が次々と降りかかる――。
―――どのような映画監督から影響を受けましたか?
フィリピン同世代の監督だと、ジョン・トレスやミハイル・レッドなどです。もちろんもっと上の世代のキドラット・タヒミックやラヴ・ディアスからも影響を受けていますが、子供の頃からケーブルテレビのHBOなどを見て育ってきて、またインターネットが始まった世代でもあるので、どちらかというと国内よりも海外の監督作品を観る機会の方が多かったですね。マーティン・スコセッシやウディ・アレン、マチュー・カソヴィッツなどもよく観ていました。日本の映画監督だと塚本晋也の「東京フィスト」、あとは黒沢清、三池崇史、大島渚監督など。日本のミュージシャンでは松原みきや竹内まりやといったシティ・ポップが好きです。
―――あなたが映画を撮り始めた時のことを教えてください。
マニラで学生だった頃のクラスメイトたちから受けた刺激が、映画に興味を持ったきっかけです。中でも今回の美術監督でもあるマイキー・レッドはとても近い関係性の友達でした。仲間の中にはミハイル・レッドを始めとするレッド・ファミリーもいましたし、そのコミュニティの中にいたロックス・リーとも仲良くなりました。ロック繋がりでいうと、本当は“ロッククライマー”になりたいという夢があったんですが、そういう環境に置かれたことで刺激を受けて、プロの映像作家になりたいと思うようになりました。
そうしているうちにデジタルフィルムやminiDVDなどを使ったインディペンデントフィルムに接する機会が多くなり、映画を撮り始めました。最初に使ったカメラはPanasonicのDVX100。初長編作品「郊外の爬虫類」は、16mmで撮ってVHSに変換しました。今回の「ウリリは黒魔術の夢をみた」はデジタルで撮影しています。カメラはSONYで(機種名は忘れました)、人物を効果的に描くことのできるHELIOSという古い特別なロシアのレンズを使っています。
―――この作品には要素がたくさんあり、一部の人には「混乱」という印象すら与えます。バスケ、麻薬、クリスチャン、呪い…。ホラーなのか、ラブストーリーなのか、スポーツドラマなのか。このカオスな状態がまさにフィリピンのリアルなアイデンティティを表しているようです。
コンセプトを考えている段階から、いろんなジャンルをマッシュアップした映画を作りたいと思っていました。僕は子供時代からホラーやコメディといった、フィリピンのメインストリームでありメジャーな商業映画ばかりみて育ってきました。そういう色んなものをひとつの映画の中でスムーズに繋げた作品を作りたかったんです。今までそういう映画をフィリピンで見たことがありませんでした。「実験」というと大袈裟かもしれませんが、フィリピンで実際に起きている出来事を物語にするなら、どういったスタイルが合うかをいろいろ試してみました。
マイケル・ジョーダン・ウリリはフィリピン人を代表している存在であり、彼の人生は様々なジャンルを通り過ぎていきます。アートハウス、スローフィルムなど、そのスタイル(ジャンル)はさまざまです。また最初は観客の想像と違うものにしたいという想いがありました。観ている人は最初スポーツフィルムかと思っていたら恋愛映画のようで、それからクライム映画や呪いが出てくるなど、どんどんジャンルが変わっていきます。でもナラティブによってジャンルは変わっていくものですし、そういう変化が「大人になる」ということなのではないでしょうか。たとえ主人公にどんな才能があったとしても、思い通りにはいかない。人生とはコントロールできないものなのです。
―――やや過激な表現も見られますが、これはフィリピンのリアルな光景なのでしょうか、それとも誇張表現なのでしょうか?
確かに過激ではあると思いますが、そこまで自分の映画がセンセーショナルとは思いません。それよりも本当の状況をそのまま見せて伝えることを重視しています。決して盛ってるわけではありません。ただしこれが現実そのものかと言われると、YESでありNOでもあります。映画的になるように強調して描いていますからね。表現としては強調してますが、物語のルーツは全て実際にある場所や事実の話です。
―――フィリピン国内の上映状況について。
今回、日本の劇場で上映されることは僕にとってとても光栄だと思っています。フィリピンは他の国と比べても年齢制限のセンサーシップ(上映に関する審査、日本では映倫に当たる)がとても厳しいんです。バギオで今年の3月に行われる上映会では、18歳以下は観ることが出来ません(*日本はR15+)。
フィリピンにおいて、この作品を劇場のスクリーンで上映することはかなり難しく、とても小さいアートハウスやギャラリーのようなところでのみ許されています。フィリピンの劇場は商業的な映画だけが上映できる場所で、とてもコンサバです。フィリピンはカトリックの国なので、宗教的なことが関係しているんです。例えばこの映画では妊婦がドラッグを吸っているシーンもありますしね。本当のことを見せているから、制限が厳しいのかもしれませんね。それがリアルなんですが、それを見せたくないんだと思います。
―――今回モノクロで撮影した理由を教えてください。
モノクロでないと、キャラクターを正しく表現できないと思ったからです。例えばウリリは黒人という設定ですが、実際の彼は本当の黒人ではないので、実は黒人というより、いかにもフィリピン人であるような肌の色をしています。でも白黒を使えば効果的に表現できます。レンズ(HELIOS)の選択も同じことです。このレンズはフォーカスが浅いので、キャラクターに集中できるのです。
今回のモノクロ表現は、いろんな作品から影響を受けています。例えばバスケのシーンはマーティン・スコセッシの「レイジング・ブル」、ドラッグのシーンはカソビッツの「憎しみ」、またラヴシーンはウッディ・アレンの「マンハッタン」などです。よくフィリピンの巨匠ラヴ・ディアスのモノクロ表現と比較されることもありますが、もちろんそれは嬉しいですが、海外からの影響の方が多いかもしれません。
―――チームの人数と制作日数は?
スタッフは、俳優を含めずに30人くらいのチームで制作しました。2015年から構想や執筆を始めて、最終的なアウトプットに至るまで多くの草稿を経て2018年に制作しました。3年かかりましたが、実際の撮影期間は10日間でした。制作会社の規模としては小さい方だと思います。
―――映画の舞台となる街「スービック」について。
映画の舞台は、米兵が滞在していた海軍基地があった、オロンガポ州のスービックという街です。ここはフィリピンのルソン島北部のピナツボ山の近くにある場所で、 火山が噴火したことで閉鎖したクラーク基地に連動して、スービック基地が閉鎖されたという歴史があります。マイケルの父親がカルメンの前から姿を消したのは、全て1991年に起こった出来事だったのです。
映画の設定としては、マイケルの母親(カルメン)と叔母(ロシェル)はスービックで働いていたダンサーであり娼婦でした。そこには米軍の軍隊がよく訪れていて、マイケルの父親(アーヴィング)もその一人でした。彼はバスケットボールとは無関係ですが、カルメンやマイケルにとってはアメリカンドリームの象徴でありオリジナなのです。カルメンとアーヴィングは激しい恋に落ち一緒にアメリカに行く約束もしていたのですが、米軍基地が閉鎖された時にその約束も一緒に消えてしまいました。
また皮肉なことにマイケルの父親は実はナイジェリア移民として米軍に入隊した人物で、本当のアメリカ人ではなかったのです。主人公であるウリリは、そんな米軍海海兵とフィリピン人女性の間に生まれた子供です。ウリリや彼の周囲の人たちがバスケットボールでの成功に強くこだわるのは、自分たちがアメリカとのコネクションがあると思い込んでいるからなのでしょう。
―――この映画にはピナツボ火山の噴火が重要なファクターとして登場しますが、スービックの米軍海軍基地閉鎖に対するあなたの記憶と関係しているのでしょうか?
僕が生まれたのが1997年で、ピナツボ火山の噴火は1999年。すごく小さい時のことだったのであまり覚えていませんが、当時僕はマニラに住んでいて、すごい地震を感じて外に出たら、マニラなのに外はたくさんの灰が積もっていたことだけは覚えています。映画の冒頭に映し出される火山は1991年に噴火する前のピナツボの実際の静止画をアニメーションにしたものです。
―――この作品でのバスケットボールはどういう意味を持つのでしょうか。
バスケットボールはアメリカによるコロニアルのイメージですよね。またフィリピン人は背が小さいから、どれだけ頑張っても代表にはなれないとうコンプレックスもあります。でも個人的にコロニアルやアメリカに対する感情は特にありません。もちろんネガティブなことが多いのは事実ですが、でもそれが現実なんだから、避けては通れないものであることは認めないといけません。それがいまの「僕」を作っているですから。白黒つけることはできないと思っています。
一方、作品の中でのウリリは、コロニアリズムに対する難しさや困難さを感じています。ウリリの人生にも、良いことと悪いことのいろんなバランスの問題を抱えてます。マンリケ一族はウリリに対して、「毒」を与えているとも言えます。マンリケは白人的風貌を持つフィリピン社会の中の富裕層で、ウリリはアメリカの血が混ざった風貌であり決して裕福とは言えません。その上で、マンリケもウリリも自分こそが真のフィリピン人であると声をあげています。あの二人の対決は、まさにコロニアリズムの対決を象徴していると言えます。とは言えポリティカルな作品というわけではないんですけどね。
―――母カルメンが命を捧げてまでウリリをバスケ選手にしようとした理由は?
彼女はマイケルのために自分の人生を投げ出しました。これはマイケルが自分よりも良い人生を送れるようにということと、またアメリカ植民地時代の基準で自分たちの名を上げられるために、という想いが込められています。多くのフィリピン人の親が自分の子供たちに対してこのような希望を抱くのは、植民地支配後の考え方の反映なのです。バスケットボールはフィリピンにおいて最も人気のあるスポーツで、マイケルはバスケットボール選手になってNBAでプレーする可能性があるので、カルメンはそれを望んでいました。
バスケットボールはアメリカ人が導入したスポーツなので、これも植民地支配後の影響を反映しています。ほとんどのフィリピン人は、世界的に高いレベルで競争するための身長という身体的なアドバンテージを欠いているにもかかわらず、バスケットボールに関しては情熱的で競争的な面があるのです。
―――日本車の三菱ギャランΣを登場させた理由について教えてください。
まずは僕自身が、日本車が好きだから!三菱、トヨタ、スズキの車はフィリピンでも有名です。僕の家にあった車はこれまで全て日本車でした。当時の日本車はフィリピンでとても人気があり、「ギャランΣ」もこの国を象徴する車のひとつです。映画で実際に使った車は、友人のお婆さんがブライダル・カーとして購入した新車です。これを娘つまり友人のお母さん(そして中学一年生の時の担任の先生でもありました)の世代に引き継がれ、今はそれを僕が譲り受けて使っています。
ルイスが映画の中で話しているTV CMは、1978年にフィリピンで放送されたものです。僕はリアルタイムで見ていませんが、お父さんからその話は聞いていました。車に血をかけるシーンがありますが、あれはチョコレートシロップを使っています。白黒で撮影する時はチョコレートシロップを使うといいんです。
―――映画の中で行われる黒魔術は、モデルまたは参考にしたものありますか。
これは架空のカルトとして、映画で見た習慣や儀式を参考にしました。また儀式の際に見たという「鳥」は、見る者の想像力にお任せしています。鳥は、信じる人々への希望と救いを象徴しています。
―――ナラティブのインスピレーションはどこから?
テレビが多いですね。ニコロディオンや、タガログの映画など。日本のアニメからも「幽遊白書」、「超電子バイオマン」、「パワーレンジャー」、「ボルテスV」など、いろんなメディアから影響を受けています。
―――今後の予定は?
これからも映画を作り続けたいと思っています。ドラッグやセックスも含め、実際に起きていることを描くのが僕の映画だから、それはこれからも描き続けると思います(笑)。次回作は日本での撮影を考えています。ホラー映画で、移民に関するストーリーです。日本に行くフィリピン人の移民と、フィリピンにくる日本人の移民。2つのカルチャーについてのスクリプトを最近書き始めています。音楽はまたSewage Workerにお願いしたいですね。僕はアーティストでもありますから、仕事としての映像制作をしながらも作品発表は続けていくつもりです。
【作品情報】
・ ウリリは黒魔術の夢をみた
【関連記事】
・ 【動画】「ウリリは黒魔術の夢をみた」予告編
・ 「ボルテスV レガシー」10月18日から劇場公開!日本の観客のためにフィリピン製作陣が用意した“超電磁編集版”
・ マニラでホームレス、高層マンションでセカンドライフフィリピン在住邦人2人のドキュメント「ベイウォーク」12月24日公開
<あらすじ>
ピナツボ火山の大噴火がフィリピン全土を揺るがした1991年、カルメンという女性とアメリカ人男性との間に赤ん坊が生まれる。カルメンは自分たちが大噴火を起こしたと信じるカルト集団の黒魔術に導かれ、息子に「プロのバスケ選手としてNBAで活躍する」運命を授け、自身の命を日本車ギャランに捧げる。NBAのスター選手の名を借りて「マイケル・ジョーダン・ウリリ」と名づけられた子どもは、才能あるプレイヤーへと成長。伝説の背番号「23」を背負い、恋人との肉欲とバスケ賭博に明け暮れる青春を過ごしていた。そんな中、ウリリにアメリカ行きのチャンスが舞い込むが、悪夢のような出来事が次々と降りかかる――。
―――どのような映画監督から影響を受けましたか?
フィリピン同世代の監督だと、ジョン・トレスやミハイル・レッドなどです。もちろんもっと上の世代のキドラット・タヒミックやラヴ・ディアスからも影響を受けていますが、子供の頃からケーブルテレビのHBOなどを見て育ってきて、またインターネットが始まった世代でもあるので、どちらかというと国内よりも海外の監督作品を観る機会の方が多かったですね。マーティン・スコセッシやウディ・アレン、マチュー・カソヴィッツなどもよく観ていました。日本の映画監督だと塚本晋也の「東京フィスト」、あとは黒沢清、三池崇史、大島渚監督など。日本のミュージシャンでは松原みきや竹内まりやといったシティ・ポップが好きです。
―――あなたが映画を撮り始めた時のことを教えてください。
マニラで学生だった頃のクラスメイトたちから受けた刺激が、映画に興味を持ったきっかけです。中でも今回の美術監督でもあるマイキー・レッドはとても近い関係性の友達でした。仲間の中にはミハイル・レッドを始めとするレッド・ファミリーもいましたし、そのコミュニティの中にいたロックス・リーとも仲良くなりました。ロック繋がりでいうと、本当は“ロッククライマー”になりたいという夢があったんですが、そういう環境に置かれたことで刺激を受けて、プロの映像作家になりたいと思うようになりました。
そうしているうちにデジタルフィルムやminiDVDなどを使ったインディペンデントフィルムに接する機会が多くなり、映画を撮り始めました。最初に使ったカメラはPanasonicのDVX100。初長編作品「郊外の爬虫類」は、16mmで撮ってVHSに変換しました。今回の「ウリリは黒魔術の夢をみた」はデジタルで撮影しています。カメラはSONYで(機種名は忘れました)、人物を効果的に描くことのできるHELIOSという古い特別なロシアのレンズを使っています。
―――この作品には要素がたくさんあり、一部の人には「混乱」という印象すら与えます。バスケ、麻薬、クリスチャン、呪い…。ホラーなのか、ラブストーリーなのか、スポーツドラマなのか。このカオスな状態がまさにフィリピンのリアルなアイデンティティを表しているようです。
コンセプトを考えている段階から、いろんなジャンルをマッシュアップした映画を作りたいと思っていました。僕は子供時代からホラーやコメディといった、フィリピンのメインストリームでありメジャーな商業映画ばかりみて育ってきました。そういう色んなものをひとつの映画の中でスムーズに繋げた作品を作りたかったんです。今までそういう映画をフィリピンで見たことがありませんでした。「実験」というと大袈裟かもしれませんが、フィリピンで実際に起きている出来事を物語にするなら、どういったスタイルが合うかをいろいろ試してみました。
マイケル・ジョーダン・ウリリはフィリピン人を代表している存在であり、彼の人生は様々なジャンルを通り過ぎていきます。アートハウス、スローフィルムなど、そのスタイル(ジャンル)はさまざまです。また最初は観客の想像と違うものにしたいという想いがありました。観ている人は最初スポーツフィルムかと思っていたら恋愛映画のようで、それからクライム映画や呪いが出てくるなど、どんどんジャンルが変わっていきます。でもナラティブによってジャンルは変わっていくものですし、そういう変化が「大人になる」ということなのではないでしょうか。たとえ主人公にどんな才能があったとしても、思い通りにはいかない。人生とはコントロールできないものなのです。
―――やや過激な表現も見られますが、これはフィリピンのリアルな光景なのでしょうか、それとも誇張表現なのでしょうか?
確かに過激ではあると思いますが、そこまで自分の映画がセンセーショナルとは思いません。それよりも本当の状況をそのまま見せて伝えることを重視しています。決して盛ってるわけではありません。ただしこれが現実そのものかと言われると、YESでありNOでもあります。映画的になるように強調して描いていますからね。表現としては強調してますが、物語のルーツは全て実際にある場所や事実の話です。
―――フィリピン国内の上映状況について。
今回、日本の劇場で上映されることは僕にとってとても光栄だと思っています。フィリピンは他の国と比べても年齢制限のセンサーシップ(上映に関する審査、日本では映倫に当たる)がとても厳しいんです。バギオで今年の3月に行われる上映会では、18歳以下は観ることが出来ません(*日本はR15+)。
フィリピンにおいて、この作品を劇場のスクリーンで上映することはかなり難しく、とても小さいアートハウスやギャラリーのようなところでのみ許されています。フィリピンの劇場は商業的な映画だけが上映できる場所で、とてもコンサバです。フィリピンはカトリックの国なので、宗教的なことが関係しているんです。例えばこの映画では妊婦がドラッグを吸っているシーンもありますしね。本当のことを見せているから、制限が厳しいのかもしれませんね。それがリアルなんですが、それを見せたくないんだと思います。
―――今回モノクロで撮影した理由を教えてください。
モノクロでないと、キャラクターを正しく表現できないと思ったからです。例えばウリリは黒人という設定ですが、実際の彼は本当の黒人ではないので、実は黒人というより、いかにもフィリピン人であるような肌の色をしています。でも白黒を使えば効果的に表現できます。レンズ(HELIOS)の選択も同じことです。このレンズはフォーカスが浅いので、キャラクターに集中できるのです。
今回のモノクロ表現は、いろんな作品から影響を受けています。例えばバスケのシーンはマーティン・スコセッシの「レイジング・ブル」、ドラッグのシーンはカソビッツの「憎しみ」、またラヴシーンはウッディ・アレンの「マンハッタン」などです。よくフィリピンの巨匠ラヴ・ディアスのモノクロ表現と比較されることもありますが、もちろんそれは嬉しいですが、海外からの影響の方が多いかもしれません。
―――チームの人数と制作日数は?
スタッフは、俳優を含めずに30人くらいのチームで制作しました。2015年から構想や執筆を始めて、最終的なアウトプットに至るまで多くの草稿を経て2018年に制作しました。3年かかりましたが、実際の撮影期間は10日間でした。制作会社の規模としては小さい方だと思います。
―――映画の舞台となる街「スービック」について。
映画の舞台は、米兵が滞在していた海軍基地があった、オロンガポ州のスービックという街です。ここはフィリピンのルソン島北部のピナツボ山の近くにある場所で、 火山が噴火したことで閉鎖したクラーク基地に連動して、スービック基地が閉鎖されたという歴史があります。マイケルの父親がカルメンの前から姿を消したのは、全て1991年に起こった出来事だったのです。
映画の設定としては、マイケルの母親(カルメン)と叔母(ロシェル)はスービックで働いていたダンサーであり娼婦でした。そこには米軍の軍隊がよく訪れていて、マイケルの父親(アーヴィング)もその一人でした。彼はバスケットボールとは無関係ですが、カルメンやマイケルにとってはアメリカンドリームの象徴でありオリジナなのです。カルメンとアーヴィングは激しい恋に落ち一緒にアメリカに行く約束もしていたのですが、米軍基地が閉鎖された時にその約束も一緒に消えてしまいました。
また皮肉なことにマイケルの父親は実はナイジェリア移民として米軍に入隊した人物で、本当のアメリカ人ではなかったのです。主人公であるウリリは、そんな米軍海海兵とフィリピン人女性の間に生まれた子供です。ウリリや彼の周囲の人たちがバスケットボールでの成功に強くこだわるのは、自分たちがアメリカとのコネクションがあると思い込んでいるからなのでしょう。
―――この映画にはピナツボ火山の噴火が重要なファクターとして登場しますが、スービックの米軍海軍基地閉鎖に対するあなたの記憶と関係しているのでしょうか?
僕が生まれたのが1997年で、ピナツボ火山の噴火は1999年。すごく小さい時のことだったのであまり覚えていませんが、当時僕はマニラに住んでいて、すごい地震を感じて外に出たら、マニラなのに外はたくさんの灰が積もっていたことだけは覚えています。映画の冒頭に映し出される火山は1991年に噴火する前のピナツボの実際の静止画をアニメーションにしたものです。
―――この作品でのバスケットボールはどういう意味を持つのでしょうか。
バスケットボールはアメリカによるコロニアルのイメージですよね。またフィリピン人は背が小さいから、どれだけ頑張っても代表にはなれないとうコンプレックスもあります。でも個人的にコロニアルやアメリカに対する感情は特にありません。もちろんネガティブなことが多いのは事実ですが、でもそれが現実なんだから、避けては通れないものであることは認めないといけません。それがいまの「僕」を作っているですから。白黒つけることはできないと思っています。
一方、作品の中でのウリリは、コロニアリズムに対する難しさや困難さを感じています。ウリリの人生にも、良いことと悪いことのいろんなバランスの問題を抱えてます。マンリケ一族はウリリに対して、「毒」を与えているとも言えます。マンリケは白人的風貌を持つフィリピン社会の中の富裕層で、ウリリはアメリカの血が混ざった風貌であり決して裕福とは言えません。その上で、マンリケもウリリも自分こそが真のフィリピン人であると声をあげています。あの二人の対決は、まさにコロニアリズムの対決を象徴していると言えます。とは言えポリティカルな作品というわけではないんですけどね。
―――母カルメンが命を捧げてまでウリリをバスケ選手にしようとした理由は?
彼女はマイケルのために自分の人生を投げ出しました。これはマイケルが自分よりも良い人生を送れるようにということと、またアメリカ植民地時代の基準で自分たちの名を上げられるために、という想いが込められています。多くのフィリピン人の親が自分の子供たちに対してこのような希望を抱くのは、植民地支配後の考え方の反映なのです。バスケットボールはフィリピンにおいて最も人気のあるスポーツで、マイケルはバスケットボール選手になってNBAでプレーする可能性があるので、カルメンはそれを望んでいました。
バスケットボールはアメリカ人が導入したスポーツなので、これも植民地支配後の影響を反映しています。ほとんどのフィリピン人は、世界的に高いレベルで競争するための身長という身体的なアドバンテージを欠いているにもかかわらず、バスケットボールに関しては情熱的で競争的な面があるのです。
―――日本車の三菱ギャランΣを登場させた理由について教えてください。
まずは僕自身が、日本車が好きだから!三菱、トヨタ、スズキの車はフィリピンでも有名です。僕の家にあった車はこれまで全て日本車でした。当時の日本車はフィリピンでとても人気があり、「ギャランΣ」もこの国を象徴する車のひとつです。映画で実際に使った車は、友人のお婆さんがブライダル・カーとして購入した新車です。これを娘つまり友人のお母さん(そして中学一年生の時の担任の先生でもありました)の世代に引き継がれ、今はそれを僕が譲り受けて使っています。
ルイスが映画の中で話しているTV CMは、1978年にフィリピンで放送されたものです。僕はリアルタイムで見ていませんが、お父さんからその話は聞いていました。車に血をかけるシーンがありますが、あれはチョコレートシロップを使っています。白黒で撮影する時はチョコレートシロップを使うといいんです。
―――映画の中で行われる黒魔術は、モデルまたは参考にしたものありますか。
これは架空のカルトとして、映画で見た習慣や儀式を参考にしました。また儀式の際に見たという「鳥」は、見る者の想像力にお任せしています。鳥は、信じる人々への希望と救いを象徴しています。
―――ナラティブのインスピレーションはどこから?
テレビが多いですね。ニコロディオンや、タガログの映画など。日本のアニメからも「幽遊白書」、「超電子バイオマン」、「パワーレンジャー」、「ボルテスV」など、いろんなメディアから影響を受けています。
―――今後の予定は?
これからも映画を作り続けたいと思っています。ドラッグやセックスも含め、実際に起きていることを描くのが僕の映画だから、それはこれからも描き続けると思います(笑)。次回作は日本での撮影を考えています。ホラー映画で、移民に関するストーリーです。日本に行くフィリピン人の移民と、フィリピンにくる日本人の移民。2つのカルチャーについてのスクリプトを最近書き始めています。音楽はまたSewage Workerにお願いしたいですね。僕はアーティストでもありますから、仕事としての映像制作をしながらも作品発表は続けていくつもりです。
【作品情報】
・ ウリリは黒魔術の夢をみた
【関連記事】
・ 【動画】「ウリリは黒魔術の夢をみた」予告編
・ 「ボルテスV レガシー」10月18日から劇場公開!日本の観客のためにフィリピン製作陣が用意した“超電磁編集版”
・ マニラでホームレス、高層マンションでセカンドライフフィリピン在住邦人2人のドキュメント「ベイウォーク」12月24日公開
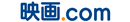
関連キーワード
エンタメ 新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55





























