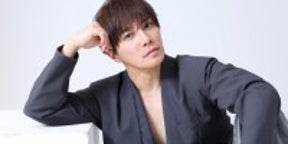入居時に「1ヶ月の家賃分」の「敷金」を払いました。なにも壊さず住んでいたら「敷金」はどれくらい返ってくるのでしょうか?
4月1日(火) 20:00
敷金とは
敷金とは、賃貸物件に入居する際に大家さんや管理会社に預けるお金のことです。敷金の定義は曖昧でしたが、2020年の民法改正により「賃貸債務その他の賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭」と明確に定められました。
敷金は、借主が家賃を滞納した場合や、設備や室内に故意または不注意で損害を与えた場合の修繕費用に使われます。借主に家賃の未払い、滞納、不注意や故意による汚損・毀損(きそん)がなければ、敷金は退去時に返還されます。
敷金の金額は物件によって異なりますが、一般的には家賃の1~2ヶ月分が相場です。
敷金は退去後に返ってくる
敷金は家賃滞納や原状回復費用が発生しない場合、基本的には退去後に返還されます。返還額や時期は、契約内容や物件の状態によって異なります。
ただし、退去時に必ずしも預けた全額が返ってくるわけではありません。
例えば、家賃の未払いがあった場合、その未払い分が敷金から差し引かれることになります。また、借主が負担すべき原状回復費用がある場合、その修繕にかかる費用が敷金から差し引かれます。
つまり、退去時に敷金がどの程度返還されるかは、家賃の支払い状況や物件の状態によって変わるため注意が必要です。場合によっては、敷金が返還されないだけでなく、追加で不足分を支払う必要が生じることもあります。
家賃をきちんと支払っている、故意や不注意による汚損・毀損がない、原状回復費用が発生しない場合には、基本的に敷金は全額返金されます。
礼金は返ってこない
賃貸物件に入居する際、敷金とは別に礼金の支払いを求められることもあります。礼金は、大家さんや物件のオーナーへの謝礼として支払うものであり、敷金とは異なり退去時に返還されることはありません。
礼金の金額は物件ごとに異なりますが、発生する場合は一般的に家賃の1~2ヶ月分が相場とされています。ただし、物件によっては礼金なしのケースもあるため、契約時にしっかりと確認することが大切です。
敷金が返ってくる時期
敷金が返還される時期は、一般的に退去後1~2ヶ月以内とされています。ただし、法律で具体的な期間が定められているわけではなく、返還時期は契約内容や物件の状況によって異なる場合があります。敷金返還の義務は、賃貸借契約が終了後に物件が貸主に返還され、債務精算が完了した時点で発生します。
その後、貸主や不動産会社が物件の原状回復状況を確認し、未払い家賃や修繕費用など必要な精算が終わった段階で、残額が指定の口座に振り込まれます。このプロセスには、数週間から数ヶ月かかる場合があります。つまり、敷金が退去日にすぐ返還されるわけではありません。
敷金トラブルを防ぐためのポイント
敷金トラブルを防ぐためのポイントは、以下のとおりです。
・入居時に室内の汚れや傷、不具合を確認して写真や動画で記録する
・退去時の立ち会いに参加して物件の状態を確認し、原状回復が発生する場合はその場で説明を受ける
・契約書や特約条項を確認し、原状回復の範囲や借主負担の条件を事前に把握しておく
・賃貸契約書や重要事項説明書をよく確認し、敷金や原状回復義務、特約条項について理解しておく
敷金トラブルを防ぐためには、入居時と退去時に借主・貸主、管理会社が立ち会い、物件の状態を一緒に確認することが大切です。入居時にすでにある傷や汚れを記録しておけば、退去時に自分の責任ではないことを証明できます。また、退去時に立ち会うことで、損耗や損傷に対する貸主の判断を直接確認でき、後々のトラブルを防ぐことが可能です。
契約書の内容を事前に確認し、退去時の原状回復の条件を把握しておくことも重要です。経年劣化や通常損耗は、原則として原状回復から除外されます。ただし、有効な特約条項で経年劣化等も借主負担と定められている場合は、退去時に想定以上の費用が発生する可能性があります。
敷金が返ってこないときの対処法
退去後に敷金が返還されず、理由に納得がいかない場合には、まず大家さんや不動産会社に連絡し、詳細を確認しましょう。敷金が返還されない理由や差し引かれた費用の内訳を明確にしてもらうことで、不当な控除が行われていないか確認できます。
それでも説明に納得できない場合や不当な請求が疑われる場合には、国民生活センターや市区町村の相談窓口、法テラスに相談することを検討しましょう。これらの機関では、専門的なアドバイスを受けることができます。専門家が客観的な立場からアドバイスを提供し、必要に応じて交渉方法や法的手続きについて案内をしてくれます。
敷金に関する契約内容を事前に確認しておこう!
敷金は基本的に退去時に返還されますが、返還額は家賃の未支払い分や借主が負担すべき原状回復費用を差し引いた後の残額となります。場合によっては、敷金で修繕費用や未払い家賃を賄いきれず、追加費用が発生することもあるため注意が必要です。また、契約書に記載された特約条項や精算内訳を確認し、不当な請求を防ぐことが重要です。
トラブルを避けるためにも、契約書や重要事項説明書で敷金の取り扱いや特約条項を事前に確認しておくことが重要です。疑問点があれば不動産会社や管理会社に相談し、事前に解消しておきましょう。
出典
法務省 賃貸借契約に関するルールの見直し
国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
「UR物件」に住むメリット・デメリット、そして思いがけないメリットとは?「築43年」のアパートに住もうか迷っています…家賃は23区で「5万4000円」ですがメリット・デメリットを教えてください
「家賃11万→18万円に値上げします」と突然の連絡! 同意がなければ家賃は変わらない? 知っておきたい「賃貸契約書」の見るべきポイントを、元不動産営業の筆者が解説します

新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55