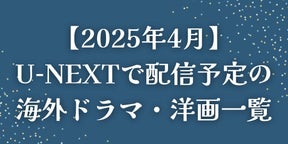「宝くじは大きく当てるもの。だから販売員は常に笑顔。その笑顔が運気をあげ、大きな当たりを呼ぶんですよ
部屋の隅に丸裸の死体が山積みに…100歳の宝くじ売り場店主が“シベリア抑留”から切り開いた壮絶半生
3月30日(日) 2:00
「源じいから買うと当たる気がするんだよね」
店のカウンター越しに、にぎやかな男性客の声がする。
「どうか大きく当ててください」
にこやかな笑顔で応じて、加藤源一さんが宝くじを手渡すと、その男性客は「長寿の福を分けてください」と、おもむろに源じいとグータッチをして去っていった。
「最近は本当に私の体に触れたがるお客さんが増えましてね」
こう笑う加藤さんを、本誌では親しみを込めて源じいと呼ぶ。源じいは1925年(大正14年)1月生まれ。今年で満100歳になった。
ここは静岡県藤枝市の郊外にある宝くじの店「丸源」。いまは周囲に住宅も増えたが、源じいがこの売り場を始めた1998年、73歳のころには、赤く宝くじの文字が目立つ売り場が、畑のただなかにぽつんと立っていて、遠くからもよく見えたという。
源じいは28年間、この売り場の店主として、いまも週に2~3日は必ず店頭に立つ。
開業から5年後、2003年の年末ジャンボで1等・前後賞3億円が出たのを皮切りに、これまでに出た億当たりは8本。総額では15億円超の大当たりを出し、年末ジャンボの時期には、駐車場に入りきれない車が道路に連なり“丸源渋滞”を引き起こすほどの人気売り場となっている。
「こんな片田舎にある売り場から、これほどの当たりが出るとは想像もしていなかったです。ただひとつ言えるのは、私はこの飯盒によって生かされてきた。すべては飯盒のおかげかなとは思いますね」(以下、語りはすべて源じい)
源じいは、いとおしそうに黒く古びた飯盒をなでながら、遠く昔に思いを馳せるように、自らの半生を語り始めた。
■爆弾を背負って、相手の戦車の下に潜り込む訓練を繰り返す日々
源じいが生まれたのは静岡県掛川市。米農家の次男で、14歳で当時の高等小学校を卒業後、静岡市内で手広く酒屋を営む「平喜商店」(現・静岡平喜酒造)に入店した。
「そのころは農家の次男の多くは住み込みの丁稚奉公に出たもので、私もその一人でした。慣れない商売でしたが、無我夢中で仕事に励んだものです」
そんな仕事への真面目な姿勢が認められ、1942年(昭和17年)に17歳で、現在の北朝鮮との国境に近い中国東北部・間島省延吉県図們街にあった「平喜商店」の支店「平喜洋行百貨店」に出向することになる。これが源じいの生涯を大きく変えるきっかけとなった。
「1932年(昭和7年)に、日本軍が占領していた中国東北部に満州国を建て、日本から多くの国民が開拓民として移住していました。図們の町にも日本人が大勢いて『平喜洋行百貨店』は生活物資や食料品、酒類を扱う百貨店でした」
当時の様子がわかる貴重な写真が源じいの手元にある。それが1944年1月に開かれた「平喜洋行百貨店」の新年会の際の集合写真だ。
「これらの写真が私の手元にあるのは、1944年に軍隊の召集令状が届き、現地・中国で入隊することになった際、身の回りの物を両親への手紙とともに“遺品”のつもりで、本土の掛川の実家に柳行李に詰めて送ったからです。当時は太平洋戦争の戦況が悪化し、満州からの郵便物はなかなか届かないことが多かったなか、奇跡的に無事に実家に届いていました」
こうして源じいは19歳で現在の中国黒竜江省・ハルビンにあった関東軍(満州国の日本陸軍はこう呼ばれていた)6261部隊に最年少兵として入隊。そこで待っていたのは壮絶な訓練だった。
「いつソ連(現・ロシア)軍が攻め込んでくるかわからない情勢のなか、爆弾を背負って、相手の戦車の下に潜り込む、まさに肉弾特攻の訓練を、毎日繰り返し繰り返しやっていました。小さいころから『お国のため』という教育を受けていましたから、なんの疑問も持たずに過ごしていたものです」
■氷点下40度の中で重労働。シベリアの収容所では毎日仲間が次々と亡くなって
入隊して1年余り、1945年8月8日にソ連は日本に宣戦布告。翌9日に満ソ国境を越えて侵攻した。
刻々と源じいの部隊のあるハルビンにもソ連軍が迫りくる8月15日に日本は無条件降伏をする。
「この日、中隊長が全隊員150名ほどを一堂に集めました」
源じいが平岡さんと名前を記憶している中隊長は、真新しい飯盒を1個ずつ全隊員に手渡して、こう訓示した。
「本日、天皇陛下のお言葉で、軍隊は武装解除、解散することになった。われわれ将校は君たちとは別々に行動することになる。君たちはこの飯盒を持って生き延び、何としても内地(日本)に帰って親孝行に尽くせ。もし迷うことがあったら、自分の“第一感”だけを頼りにして生き抜いてほしい」
冒頭、現在も源じいが大切に保管する飯盒は、このとき手渡されたものなのだ。
「食べることこそ生きること。飯盒に“生きる執念”を持てという思いを込めて平岡中隊長は全員に手渡したのではないでしょうか」
それからまもなくソ連軍がハルビンにも侵攻。源じいたち日本兵や軍属はソ連軍の捕虜となった。
これまで山崎豊子の小説『不毛地帯』ほか、数多くの体験者手記によって語り継がれてきた、過酷な戦後の歴史的出来事であるシベリア抑留のはじまりである。このときソ連軍は日本兵や民間人を捕虜とし、シベリアなどに強制連行し、強制労働を強いた。捕虜になった日本人は約57万人とされ、そのうちの5万人以上が亡くなった。
「武装解除した私たちは侵攻してきたソ連軍の捕虜となり、当初は『ダモイ(帰国)』と告げられ、日本に帰れるものと思っていたのです」
源じいたちの部隊は、この年9月にハルビンから横道河子まで列車で移動、そこから牡丹江までは徒歩で行軍した。
「10月になり、牡丹江からソ連軍の列車に乗せられました。このときはまだ内地に帰れると信じていたのですが、列車の向かう方向が北ではないかと、仲間たちが騒ぎ出したんですよ」
たしかに朝日が昇る東から見て、列車は北に向かっていた。ひとまず源じいたちの列車が着いたのはシベリアのハバロフスク。11月になり、よりシベリアの奥地であるテルマの収容所に移送された。
「テルマの収容所で過ごした最初の冬の4カ月は本当に言葉では表せないほど過酷なものでした。何日も氷点下40度になる日が続き、極寒の屋外で森林の伐採などの作業の日々。食事もとても食事と呼べるようなものではなく雑穀のみそ汁と黒パン1枚だけです。
つねに飢えていて、栄養失調や病気で毎日次々と仲間が亡くなっていきました。夜、寝ている私の横で仲間の一人が『銀飯(白米のこと)が食べたい』と叫んで翌朝には冷たくなっていたこともありましたよ。死体は丸裸でマネキンのように部屋の隅に山積みにされている状況。それは地獄の冬でした」
収容所に入って、最初の1年間は入浴した記憶がなく、しらみ、床じらみのせいで、全身がかゆく、一晩眠れないこともしばしば。生きていること自体がつらかったと漏らす。そんな源じいを支えたのは20歳という若さと、平岡中隊長の「なにがあっても“第一感”で生き抜け」という言葉だったという。
■シベリアの収容所内で元職人の戦友が名前を刻んでくれた飯盒はいまも源じいのもとに
「最初の冬が明けた1946年春に、私はテルマからモシカの収容所に移送。そこで私はロシア語の通訳をしている知り合いと出会うことができました。ロシア語を覚えることが収容所生活を生き抜くつえになるのではというのが、私の“第一感”。とにかく時間があれば必死で、最低限のロシア語の読み書きを教わりました」
モシカの収容所には軍隊に入るまで彫金の職人をしていたという人がいて、源じいの飯盒の蓋と胴の2カ所に「加藤源一」と名前を刻んでもらった。それは薄くなりかけてはいるが、いまも写真のようにはっきり判読できる。
「片言ですが、ロシア語ができるようになったことで、町の病院のロシア人医師に重宝がられ、収容所の患者との連絡員として、収容所から医師の住む官舎に移り住むことができました。まさに“第一感”が私を救ったと思っています」
1947年9月、源じいは内地帰還人員の一人に選ばれ、モシカを出発。平岡中隊長から手渡された飯盒を携えて、ナホトカ港から帰還船に乗り込んだ。
「帰還時は丸裸にされ、着の身着のままでしたから、なぜ、この飯盒を持って帰れたのか、その記憶がないんですよ。不思議です」
帰還船は京都府・舞鶴港に着く予定だったが、台風の影響で、北海道・函館港に着岸。17歳で満州に渡った源じいが再び、内地の土を踏んだのは函館の町だった。
「いっしょに帰還した戦友と函館山に登り、そこから函館の町を見下ろして、帰国できたことを実感し合いました。その場で国から支給された200円を握りしめ、市場の食堂でとにかくおなかいっぱいになるまでご飯を食べました(笑)」
数日をかけて、函館から静岡に帰ってくると、知らせを聞いた「平喜商店」の社長が静岡駅の改札で出迎えてくれたことも忘れられない思い出だ。その後「平喜商店」に復帰し、ようやく源じいの帰国後の人生はスタートした。
「1951年に『加藤酒店』という屋号で、静岡市梅屋町に店を出し独立。市内に同じ名の酒店があったことから『丸源酒店』に改名しました」
現在、96歳になる妻のはまこさんと結婚したのもこのころ。
「シベリア抑留を経験し、九死に一生を得たこの命、とにかく残りの人生を世の中のために生きようという思いが強く、仕事に専念したことから、家庭のことは妻に任せっきりで苦労をさせました」
■営んでいた酒店にサントリーの佐治敬三社長が訪れて。経営者としての道しるべに
戦後の経済成長期と重なったこともあり、源じいの酒販業は拡大の一途。1970年に店の前で撮影された写真には当時の従業員と源じい夫妻が並ぶ。
「ちょうどこの直前ですね。サントリーがビール事業に乗り出したものの、後発のため、キリン、アサヒ、サッポロの3社を前に苦戦していたんです。そのサントリーの若い営業さんが私のところに来て『なんとかサントリービールを扱ってくれませんか?』というので『社長が頼みに来てくれたら考える』と生意気な返事をしたんですよ。そうしたらほどなく、本当に当時の佐治敬三社長が店にやって来て。それは驚きましたが、武士に二言はありません。それ以来、私の店ではサントリービールをメインに扱うようになりました(笑)」
このときの佐治社長との出会いは、源じいの経営者としてのよい道しるべとなった。それがいまの宝くじ売り場にも受け継がれている。
「なんでも社長の私からやる。率先垂範ですね。お客さんへの笑顔の挨拶から、掃除、『ありがとうございます』の言葉まで、私が手本にならないといけません」
バブル景気がはじけた1990年後半になると、源じいの酒販業にも陰りが見えてきた。このとき、宝くじに活路を見いだしたのも、源じいの“第一感”だったという。
「佐治社長から教わったことのひとつに、サントリーの創業者・鳥井信治郎さんの言葉である『やってみなはれ』精神がありましてね。1998年に藤枝市のはずれの畑の中にこの売り場を出したのも、まさに『やってみなはれ』。まわりに建物がないから、とにかく看板が目立つというのが“第一感”でした。その狙いが当たって、開店からすぐにお客さんが来てくれるようになったんですよ」
■シベリアに抑留されていた人の娘さんとの出会いから自分の体験を積極的に話す決意を
じつは源じいは自分のシベリア抑留体験を積極的に語ってきたわけではない。源じいがシベリアから帰国した当時のソ連は共産主義圏の中心をなす国だった。そのため、帰国した源じいたちは抑留中の収容所生活で共産主義を教え込まれてきた“危険思想の持ち主”ではないかと疑いの目で見られることが少なくなかったからだ。
「確かに朝礼のときに『インターナショナル』(伝統的な共産革命の歌)を歌わされたりはしましたが、言葉が通じないし、生きるのにやっとのなかで、共産主義教育なんてできはしませんよ。でもやはり世間の目は厳しいものでした」
5年前、そんな源じいのもとに一人の女性が自分の著書を手に現れた。くしくも源じいと同い年で静岡市生まれの父・窪田一郎さんが満州に渡り、関東軍に召集され、シベリアに抑留された生涯を綴った『シベリアのバイオリン』(地湧社)の著者でピアニストの窪田由佳子さんだ。窪田さんは人づてに、父・一郎さんと同い年でシベリア抑留の経験をしている源じいのことを知り、本を手渡しに来たのだった。窪田さんはこう話す。
「父は1981年に55歳で心筋梗塞で亡くなるまで、娘の私にシベリア抑留中の話をよくしてくれていました。その父の話を綴ったのがこの本です。これを読んだ人から、同じ静岡市に父と同じ体験をしてまだ生きている人がいるよと教えられたのが源じいの存在。再び父に会うような気持ちで、源じいを訪ねたことをよく覚えています」
昨年『シベリアのバイオリン』は影絵を用いた絵本にもなった。
「シベリア抑留のきびしい現実と、父が現地で生きる希望としてバイオリンを手作りし、収容所で戦友同士で楽団を作って演奏した物語です。源じいは涙を浮かべながら読んでくださいました」
その窪田さんから、シベリア抑留体験者はもう残り少ないと教えられ、源じいは語り部として、その経験を積極的に外に向けて話そうと決心する。
「もう静岡県ではシベリア帰還者で生存しているのは源じいだけ。それだけにこんなにかくしゃくとしてお元気なのは信じられません」
と、窪田さんは目を細める。
現在、源じいには妻のはまこさんとの間に4人の子供がおり、4人の孫、そしてひ孫も2人いる好々爺だ。はまこさんは介護が必要になり、介護施設に入所。少し寂しくはなったが、毎朝5時に起きて、自宅の周辺を散歩するのが日課。その足取りはとても100歳とは思えないほどしっかりとしている。
「シベリアの過酷な収容所生活を生き抜き、酒販店を繁盛させ、いまは“億招きじい”とみなさんに喜ばれて。その原点であり、生き抜いてきた証しがこの黒ずんだ古い飯盒です。迷ったときは、常に自分の“第一感”に命を託してきました。今年は戦後80年。私は100歳の節目の年。必ずや、この売り場から億万長者を出しますよ。夢は大きくやってみなはれです」
この飯盒こそが、奇跡の大当たりを出し続ける「丸源」の命の源。源じいの目はそう語っていた。

関連キーワード
生活 新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55