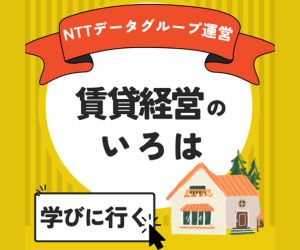土地を貸すと「取られる」可能性がある? これってどういうことですか? また、土地の賃借料に対する「税金」はどうなるのでしょうか?
3月29日(土) 1:00
土地活用を検討するなら
土地を貸すと取られる?
土地を貸し出す際に注意すべき点の1つは、借主に長期間使用されることで、最終的にその土地が戻ってこなくなるリスクがあることです。特に、日本の法律では「借地権」の保護が強く、一度他人に土地を貸すと、契約期間が満了しても簡単には貸主であっても返還を求めることができません。
例えば、借地借家法では「借地契約は最低30年間」とされており、一度契約を結ぶと、契約終了後でも借主からの更新要求を拒否することが難しくなります。また、借地権付きの土地は相続や売却の対象にもなり、借主が第三者に権利を譲渡してしまうケースもあります。
契約形態によっても異なる
土地を貸し出す際に、定期借地契約(契約期間が満了すると更新なしで必ず返還される契約)ではなく普通借地契約(更新が可能な契約)を結ぶと、借主が契約更新を続ける限り、貸主は返還を求めることが困難になります。
そのため、長期間にわたって収益を得たい場合でも、契約内容を慎重に検討しなければ、将来的に自分の土地を自由に使えなくなるリスクがあるのです。
土地を貸すことで発生するリスクを事前に把握し、適切な契約形態を選ぶことが、土地所有者にとって非常に重要です。
土地の賃借料に対する税金
土地を貸して得られた賃料収入に対しては、さまざまな税金が課されることになります。主にかかる税金には、所得税・住民税・事業税・固定資産税などがあります。
土地の賃貸収入は「不動産所得」として分類され、個人の場合は所得税・住民税の対象です。年間の賃料収入から必要経費(固定資産税や管理費など)を差し引いた金額に応じて、所得税が課税されます。所得税の税率は累進課税方式のため、収入が多いほど税負担も増加します。
また、土地の賃貸によって年間事業規模が一定以上と認められた場合、事業税(不動産貸付業にかかる税金)が課されることがあり、注意が必要です。例えば、個人がアパート経営をしており、貸している土地が5棟以上の建物を含む場合、事業税の課税対象となることがあります。
土地活用を検討するなら
契約時の注意点
土地を貸す際には、契約内容を慎重に決めなければ、将来的にトラブルが発生する可能性があります。特に、借地契約の種類や契約期間をはじめ、賃料の増減、原状回復義務などを契約書にしっかりと明記することが必要です。
まず、普通借地契約と定期借地契約のどちらを選ぶかが重要なポイントです。普通借地契約は契約更新が可能であるため、一度貸すと長期的に返還を求めることが難しくなります。一方、定期借地契約であれば、契約期間が終了すれば確実に土地が戻ってくるため、将来的な利用計画がある場合には定期借地契約を選ぶ方が安心です。
また、契約期間を設定する際には、借地借家法に基づく最低契約期間(普通借地契約では30年以上)を考慮する必要があります。短期貸しを希望する場合は、事業用定期借地契約(10年以上50年未満)など、柔軟な契約形態を選ぶとよいでしょう。
さらに、賃料の増減を明確にしておくことも大切です。特に長期契約では、物価上昇や地価の変動によって適正価格が変わる可能性があるため、一定の期間ごとに賃料を見直す条項を設けることが重要です。借主が契約終了時に土地を原状回復する義務を負うのかどうかを契約書に明記し、トラブルを防ぐようにしましょう。
土地を貸す前に慎重な契約が重要
土地を貸すことで安定した収益を得られますが、契約の仕方によっては返還を求めることが困難になったり、税金負担が増えたりするリスクがあるため、慎重に契約内容を決めることが不可欠です。
特に、借地契約の種類や期間、賃料の設定、原状回復義務の有無などを契約書にしっかりと明記し、将来的に不利にならないようにすることが重要になります。土地を賃貸する際には、リスクを最小限に抑える対策を講じてください。
出典
デジタル庁 e-Gov 借地借家法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
土地活用を検討するなら
【関連記事】
親から相続する予定の住宅。自分が住む以外の活用方法。両親の死後、実家が「空き家」に。 固定資産税が「6倍」にならないための登記と寄付の仕組みを解説
土地にかかる相続税はいくら? 計算方法や節税対策、活用できる特例・控除を紹介

新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55