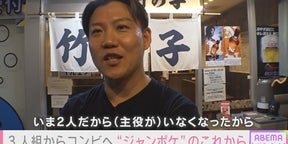(写真:Luce/PIXTA)
目の病気を防ぐ「食品」ランキング!ダントツおすすめの葉物野菜とは?
3月25日(火) 21:00
「年を重ねると視力の衰えが著しくなります。
それは徐々にというよりは45歳あたりで一度急激に低下し、次に60歳あたりで再び急激に低下するといったパターンになっています。
女性の場合は更年期や代謝能力の急な低下も視力の衰えに関連していると考えられます」
こう話すのは、『何歳からでも目が良くなる方法』(アスコム)の著者でブライトアイ代表の平賀広貴さん。平賀さんは、45歳の現在でも両目ともに視力2.0以上を維持しているという。
自分の視力をきっかけに目について研究していくうち、目によい生活習慣がわかってきたという平賀さん。
視力を維持する方法はさまざまあるが、運動や食事といった生活習慣の改善、特に食べるものを意識することで、視力の維持や改善が可能だという。
「目も体の一部です。人間の体が衰え始めるのは大体40代から。視力の衰えが現れるのもこのあたりからです。
40代以降は特に、タンパク質をしっかり取ること、そして血流をよくして毒出しをすることが大切です」(平賀さん、以下同)
代謝能力が落ちてくると、体が酸化、糖化しやすくなり、それが目の水晶体、毛細血管、網膜、目の筋肉である毛様体筋など、さまざまな働きに影響を及ぼすことになるのだという。
加齢とともに現れる目の症状を挙げてみよう。
まず、多くの人が悩まされる老眼。
40代に入ると徐々に近いものへのピントが合いにくくなり、小さい文字などが見えづらくなる。
これは、水晶体が硬くなり、目のピントを合わせる毛様体筋が衰えることで焦点が合いにくくなるから。
主な原因に血流不足による体の酸化が挙げられる。
高齢になると瞳が濁ってくる白内障は、水晶体の濁りが原因による目の病気だ。
ガラスのような水晶体が酸化することで濁り、見えづらくなったり、光をまぶしく感じるようになる。
酸化の原因には紫外線のほか、糖質過多の食事などが関係すると言われている。
視野が徐々に欠け、最悪の場合は失明する緑内障は、近視が進行すると発症率が上がる目の疾患で、一度なったら治りにくいとされている。
眼圧が上がることで、視神経が圧迫されてダメージを受け、視野が欠け始める。
加齢黄斑変性は、加齢とともに網膜の中心部にある黄斑に障害が生じて視野の中心が見えにくくなる。
これも酸化や血流不全、紫外線などが目に影響を及ぼす。
夜になると物が見えづらくなる夜盲症は、ビタミンAが欠乏して起こることでも知られている病気。
網膜にある色を感じる細胞と明暗を感じる細胞の機能低下によって起こる。
そのほかにも、目の表面が乾き、光がまぶしく感じたり、目に違和感を覚えるドライアイ、焦点の合っていない状態が続くことで頭痛や肩こりを引き起こす眼精疲労など、年齢とともに目のトラブルは増えてくる。
今回は、こうした症状を改善するのに必要な栄養素を平賀さんに教えてもらった。
どれもスーパーで買える日常的な食品ばかりだ。
■いろいろな食品をまんべんなく取ることが必要
リストの食品は機能性の高いものから順に並べているが、かといって、17位のごまの機能が低いわけではけっしてない。
「いろんな食品をまんべんなく取ることで、さまざまな目の作用により効果的に働いてくれます」
さて、食品の中でも特に優秀なのが、野菜・果物。野菜や果物に含まれるポリフェノールやフラボノイドなどのフィトケミカルには抗酸化作用があり、これが、水晶体、網膜、血管、目の筋肉などに働き、視力回復に働いてくれる。
「特に目によいとされる栄養素にルテインやゼアキサンチン、アスタキサンチン、βカロテンといったカロテノイド、ケルセチン、ポリフェノールなどがあります。
網膜を保護してくれたり、紫外線などで増える活性酸素から守ってくれるなどの働きがあるのですが、体内で合成することができないため、食べ物からしか取れない成分です」
そういう意味でダントツにおすすめしたいのが“ほうれん草”。
「ほうれん草は、ゼアキサンチン、ルテイン、ルチン、ケルセチンに加え、ビタミンA、ビタミンCも含んだ、目にとっては“超優良食品”です。
網膜を保護してくれる働き、血流改善、水晶体をきれいに保つ、目の酸化によるダメージを回復させるなど、目のさまざまな症状を改善させてくれる成分を豊富に含んでいます」
抗酸化力の強いポリフェノールがたっぷりな赤ワインも注目だ。ポリフェノールはぶどうの皮、ピーナツの皮などに多く含まれる。
「ぶどうも目によい食品なのですが、糖分が多いことから、中高年以降の人は食べすぎに注意が必要です。
その代わりに赤ワインをおすすめしています。ただ、赤ワインもアルコールですので、適度な量であることが原則です」
ほかにも抗酸化に効果的なビタミンCも積極的に取りたい。
「ビタミンCは水晶体の酸化を防ぎ、透明度を保つように働いてくれますので、白内障の予防には不可欠です」
■これからが旬の果物や緑黄色野菜でビタミンCを取ろう
ビタミンCを多く含む食材は、みかん、レモンなどの柑橘類、今が旬のいちごにも多く含まれる。
ほかにもキャベツ、ブロッコリー、にんじん、小松菜などにも豊富に含まれる。
取りたいビタミンはこれだけではない。
「ビタミンA・B・Eといったビタミン全般、食物繊維、オメガ3脂肪酸、ごまに含まれるゴマリグナンや、大豆に含まれるイソフラボンなどです」
ビタミンAは網膜で光を認識する力を高めてくれたり、粘膜や皮膚を整えてくれる。
「夜盲症など、加齢によって夕方以降に見えづらくなる人が増えますが、そういう人たちはぜひビタミンAを取ってほしいですね」
ビタミンAの多い食材はにんじん、ほうれん草、卵、レバー、みかんなど。
ビタミンB1・B2・B6・B12といったビタミンB群も目にとってうれしい栄養素だ。
ビタミンB1は、視神経を活性化し、目の周りの筋肉をしなやかにしてくれる。玄米、豚肉などに含まれている。
ビタミンB2は、皮膚や粘膜を作ってくれる。網膜の働きを助けて充血を解消したり、疲れ目を回復する働きがある。含む食品には、卵、レバーなど。
ビタミンB6 は、タンパク質や脂質の代謝を促してくれ、毛細血管の調整をしてくれる。青魚やレバーに多く含まれる。
ビタミンB12は血流促進、視神経の情報伝達をスムーズにしてくれる。乳製品やレバー、魚介類、納豆などがおすすめだ。
オメガ3脂肪酸は抗酸化作用に働くほか、網膜の細胞を守ったり、ピント機能の調整をする。青魚、くるみなどに多く含まれる。
食物繊維、ゴマリグナンは抗酸化作用に働いてくれる。
「このリストの複数の食品を組み合わせることで、最強の視力改善メニューが簡単にできあがります。
たとえば、ほうれん草のおひたしにごまやくるみをまぶして柑橘系の搾り汁をかけたり、ほうれん草とゆで卵ときのこを亜麻仁油で炒めたり……」
食材の組み合わせは自由。好きな食材でオリジナルの目によいメニューを作ってみるのも楽しそうだ。日々の食事に取り入れて、目を健康に保とう。
■目の病気を改善「食品ランキング」
■

生活 新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55