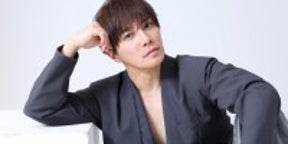「年金」を月に「10万円以上」もらえている世帯は「全体の何%」? 統計から解説
3月18日(火) 2:10
年金受給額の個人分布
年金には、20歳以上が加入する国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金がありますが、個人の状況によって支払っている年金額や受給額は異なる場合があります。
厚生労働省の「年金制度基礎調査(老齢年金受給者実態調査)令和4年」によると、令和3年度の老齢年金受給者の年金月額の分布は表1のとおりです。
表1
| 年金月額 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 5万円未満 | 287万1000人 | 8.4% |
| 5~10万円 | 1204万2000人 | 35.2% |
| 10~15万円 | 653万2000人 | 19.1% |
| 15~20万円 | 796万1000人 | 23.3% |
| 20万円以上 | 478万8000人 | 14.0% |
※e-Stat 政府統計の総合窓口「年金制度基礎調査(老齢年金受給者実態調査)令和4年」より筆者作成
このデータから、月額10万円以上の年金を受け取っている人の割合は、全体のおよそ56.4%であることが分かります。また、受給金額として最も多いのは「5〜10万円」の層で、全体の35.2%を占めています。
年金受給額の配偶者あり・なしの分布状況
年金の受給額は、単身か夫婦世帯かによっても大きく異なると考えられます。夫婦で年金を受給している世帯の、年金月額の分布を表2にまとめました。
表2
| 年金月額 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 108万4000人 | 5.0% |
| 10~15万円 | 221万2000人 | 10.1% |
| 15~20万円 | 279万9000人 | 12.8% |
| 20~25万円 | 573万6000人 | 26.3% |
| 25~30万円 | 680万2000人 | 31.2% |
| 30万円以上 | 316万9000人 | 14.5% |
※e-Stat 政府統計の総合窓口「年金制度基礎調査(老齢年金受給者実態調査)令和4年 表番号1」より筆者作成
夫婦で年金を受給している世帯のうち、月額10万円以上の年金をもらっている世帯は約95%と、ほとんどの世帯が10万円以上の年金を受け取っている状況です。一方、配偶者のいない単身世帯の年金受給額の分布は表3のとおりです。
表3
| 年金月額 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 5万円未満 | 117万1000人 | 9.8% |
| 5~10万円 | 338万3000人 | 28.2% |
| 10~15万円 | 326万9000人 | 27.3% |
| 15~20万円 | 292万6000人 | 24.4% |
| 20万円以上 | 121万5000人 | 10.1% |
※e-Stat 政府統計の総合窓口「年金制度基礎調査(老齢年金受給者実態調査)令和4年 表番号56」より筆者作成
単身者で10万円以上もらっている割合はおよそ61.8%です。夫婦世帯と比べると、低い金額帯の割合が増えている傾向がありますが、それでも半数以上が10万円以上を受給しているようです。
年金額に影響する要素
年金額には、加入期間、納付額、平均標準月額、受給開始年齢などが影響するとされています。
年金制度への加入期間が長いほど年金額は増え、保険料の納付額が多いほど年金額は増える傾向があるようです。厚生年金の場合、在職中の平均標準報酬月額が高いほど、多くの年金を受け取れる可能性があるでしょう。
また、年金の受給開始年齢を繰り下げると、その分年金額が上乗せされるといわれています。これらの要素を考慮しながら、老後の収入を早めに計画することが重要です。
将来年金を増やすための方法
将来の年金を増やすためには、いくつか方法があります。
まず、国民年金加入者(第1号被保険者)や任意加入被保険者は、「付加年金」に加入することが可能とされています。具体的には、毎月400円の付加保険料を納めることで、年金額を増やせるようです。
次に、民間の生命保険会社などが提供する個人年金保険に加入し、老後の生活資金の準備もするのもよいでしょう。
私的年金制度「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は自分で掛け金を拠出し、運用しながら積み立てることで、将来の年金を増やせる制度です。運用益は非課税というメリットもありますが、元本割れのリスクがある点は注意しましょう。
受給開始を遅らせる「繰り下げ受給」では、受給開始を1年遅らせるごとに年金額を8.4%増やすことができるとされており、最大75歳まで繰り下げることが可能なようです。これらの方法を活用し、将来の年金不足に備えていきましょう。
年金受給額は人それぞれ、早めの準備が大切
年金受給額は、加入期間や納付額、標準報酬月額など、さまざまな要素によって異なりますが、多くの人が月に10万円以上の年金を受け取っている可能性があります。
今回紹介した調査結果では、世帯別で比較すると、夫婦世帯は約95%、単身世帯は約62%と、半数以上が月10万円以上の年金をもらっているようです。
将来の年金を増やすためには、付加年金や個人年金、iDeCoなどの制度を活用したり、繰り下げ受給を検討したりするなどして、早めに準備していきましょう。
出典
e-Stat 政府統計の総合窓口年金制度基礎調査(老齢年金受給者実態調査)令和4年 表番号1
e-Stat 政府統計の総合窓口年金制度基礎調査(老齢年金受給者実態調査)令和4年 表番号56
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
年金を月20万円受け取るためには? より多くの年金を受け取るためにやってみること夫婦で「月30万円」の年金を受け取るために必要な年収は?
年金の受給は「70歳まで待つのがお得」って本当?「65歳・70歳・75歳」で比較

新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55