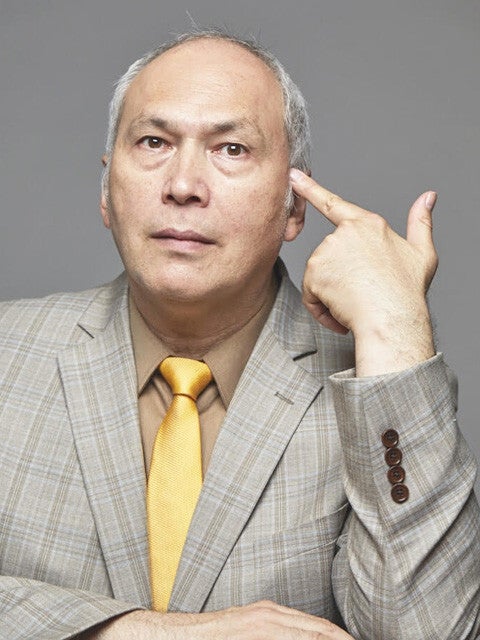
週刊プレイボーイでコラム「挑発的ニッポン革命計画」を連載中のモーリー・ロバートソン氏
モーリーの考察。「反エリート主義」がはびこる時代にこそ、知識層がやるべきこと
3月16日(日) 21:00
提供:
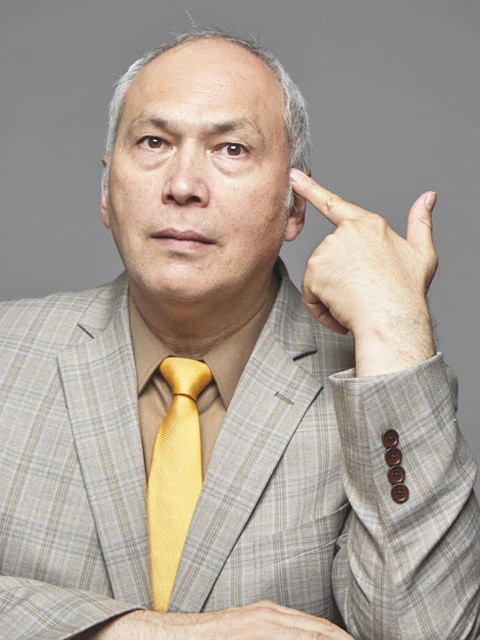 『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、世界中で吹き荒れる「反エリート」の嵐に対して、知識層と呼ばれる人々がとるべき行動や考え方について考察する。
『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、世界中で吹き荒れる「反エリート」の嵐に対して、知識層と呼ばれる人々がとるべき行動や考え方について考察する。
***
第1次世界大戦の敗戦を受けたドイツで革命が起き、国民主権、男女平等の普通選挙など20世紀の民主主義の指針となるワイマール憲法が成立したのは1919年。この波に乗り誕生した美術・建築の学校「Bauhaus(バウハウス)」には、男女関係なくみんなで新しいデザインを作ろうという理念に共感した若い女性たちが殺到、多様な価値観が交差し才能がきらめく場となりました。
しかし、女性の活躍を快(こころよ)く思わない層からの批判が圧力となり、公的な支援の削減が現実味を帯びると、バウハウスは方針を大きく転換。女性が専攻できる科目をごく一部のみに限定してしまいました。自由な創造の場だったはずのバウハウスは、その後ナチスのファシズムが拡大していく中で国家に取り込まれ、「機械的で冷たいデザインの象徴」という評価さえ受けています。
当時はメディアがまだ未発達で、デモクラシーを支える十分な情報が一般市民に流通しておらず、議論もなされないまま「心情」が動かされてファシズムが広がっていった面があります。そう考えると、情報インフラが発達し、開かれた言論の自由がある日本やアメリカの現代社会を "ファシズム前夜"などと称するのは、さすがに無理があるでしょう。
現代のアメリカにおけるドナルド・トランプやイーロン・マスクへの熱狂、日本の兵庫県知事選などで見られたポピュリズムの特徴は、"二重基準"が野放しになっていることです。攻撃対象となった人や組織には徹底的な検証や説明責任を要求する一方、ヒーローにはブラックボックスが許容され、透明性を求めない。
あるいは「日本のメディアはウソと欺瞞ばかり」と決まり文句で非難したり、「財務省解体」を強烈に支持する人々も、特定のヒーロー的な存在こそいませんが、論拠がブラックボックス化しているという点では似た部分があるかもしれません。
メディアの報道に関していえば、確かにスポンサーや特定の政治勢力などに"配慮"する場面はあります。しかしながら、その一方で記者たちが非常に丁寧な調査報道や、身を削るような取材を続けているケースもあります。つまり、実際のマスメディアの現場はひとつの「大きな力」に基づいて動いているわけではなく、いわば"都度都度"なのです。
それを「信用できない」とひとまとめに断じる人々の多くは、少なくとも現状ではマスメディアよりもはるかに信用できないような情報源を、自分にとって都合のいいように、気持ちよく受け入れているのです。
反知性主義や反エリート主義の流れは、そう簡単に食い止められるものではないかもしれません。そんな中、あえてナチス前夜のドイツから学ぶべきことを探そうとするなら、「"考える能力"のある人がサボると、社会全体が崩れる」ということでしょうか。
ややノブレス・オブリージュ的な考え方になりますが、他者や社会へと怒りを向けることで溜飲を下げている人々に対して、知識層が「バカなやつらに何を言っても変わらない」と諦め、自己利益に走ってしまうと、本当にポピュリズムが止まらなくなると思うのです。
エリート批判がはびこる時代だからこそ、知識人たちは「敵と味方」の構図に流されず、社会に発信していくべきではないかと強く感じています。
【関連記事】
■モーリーの提言。トランプ現象のようなポピュリズムに対抗する人間の武器は「大人の学び直し」?
■モーリーの指摘。フジテレビが見誤った「変化」の大きさを、トランプもプーチンも習近平も恐れている
■モーリーの提言。アメリカの大学入試でかつて起きた"事件"から日本が学ぶべきこと
■モーリーの警鐘。「理数系教育の世界的進歩から、日本は完全に取り残された」
■モーリーが解説。グローバリズムを利用したロシア・中国、グローバリズムに夢を見た欧米

生活 新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55





























