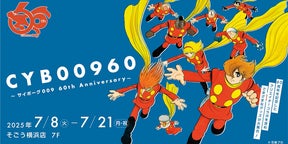年金生活の父が「ふるさと納税」しているそうです。働いていなくても利用できるのでしょうか?
3月12日(水) 19:20
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付を行うと、所得税と住民税が控除される制度です。寄付額のうち2000円を超える部分について、原則全額控除されます。
控除額には上限がありますが、仮にふるさと納税で1万円寄付した場合、8000円分の所得税と住民税が控除されます。返礼品として寄付した自治体の名産品などをもらえます。
節税になるわけではありませんが、返礼品に自己負担額(2000円)以上の価値がある場合、お得といえるでしょう。そのほか、ふるさと納税のメリットは以下の通りです。
・寄付金の使い道を選択できる:子育て支援や環境保全など、寄付金をよりいい社会のために活用する使い道の選択ができる
・自分の住んでいる自治体以外の地域を応援できる:地元や思い入れのある地域などの活性化につながる可能性がある
このように、ふるさと納税には多くのメリットがありますが、ふるさと納税をしてもらった自治体も地域の活性化や税収アップなどのメリットがあります。そのため、一般的に、ふるさと納税は寄付者にも自治体側にもメリットのある制度だといえるでしょう。
年金受給者でも利用できるの?
年金は条件を満たすと、課税対象になります。老後の年金は雑所得として扱われ、所得税が発生します。
所得税が発生する金額は年齢によって異なり、所得税がかかる金額は、65歳未満であれば108万円以上、65歳以上の方は158万円以上です。そのため、該当する方は、源泉徴収が行われ、税金が差し引かれた金額を支給されます。
課税対象者であれば、ふるさと納税によって控除が適用されるため、年金で生活している方にもメリットがあるでしょう。ちなみに、日本年金機構「収入が公的年金等の場合 所得金額の早見表」によると、公的年金収入のみの方の所得額は表1の通りです。
表1
| 収入額(年間額) | 所得額 | |
|---|---|---|
| 65歳以上の方 | 110万円以下 | 0円 |
| 158万円 | 48万円 | |
| 200万円 | 90万円 | |
| 205万円 | 95万円 | |
| 65歳未満の方 | 60万円以下 | 0円 |
| 108万円 | 48万円 | |
| 120万円 | 60万円 | |
| 135万円 | 73万7500円 | |
| 150万円 | 85万円 | |
| 160万円 | 92万5000円 | |
| 163万3000円 | 94万9750円 |
出典:日本年金機構「収入が公的年金等の場合 所得金額の早見表」を基に筆者作成
年金以外にも収入がある場合は所得額が変わりますが、年金のみであれば基本的に表1の金額が目安です。所得税を納めている年金受給者は、ふるさと納税を活用した方がお得に特産品などを手に入れられるでしょう。
年金受給者がふるさと納税を行う際のポイント
年金受給者がふるさと納税を行う際は、自分の控除限度額を確認しておくことが大切です。控除限度額を超えた場合、自己負担になったり、そもそも控除できなかったりするおそれがあります。
例えば、収入が公的年金のみかそうでないかで、控除限度額の上限は変わります。そのため、パート収入や家賃収入のある方は特に注意が必要です。
また、ふるさと納税は所得税や住民税が控除される制度であり、控除の対象になる収入がなければただ寄付をしているだけになりかねません。そのため、自身の収入と控除限度額は必ず確認しておきましょう。
あわせて、申請を忘れずに行うことも大切です。ワンストップ特例制度(※)もしくは、確定申告をしなければ、控除は受けられません。
※確定申告をせずにふるさと納税による寄付金控除を受けられる制度
ふるさと納税では一部ワンストップ特例制度を活用できない場合もあるため、自身が寄付した際に申請していなければ確定申告を行いましょう。
年金によって所得税が発生する場合はふるさと納税のメリットを受けられる
年金受給者で、ふるさと納税のメリットを受けられる対象は、公的年金の収入で所得税が発生する方や、年金とそのほかの収入をあわせた所得に税金がかかっている方です。所得税の金額は年齢や年金収入によっても異なるため、日本年金機構のホームページなどで税額の目安を確認してもいいでしょう。
また、収入によって、ふるさと納税で控除される税金の金額は変わります。控除額を超えた分は自己負担になるため、メリットを受けるには、自身の控除限度額にあわせてふるさと納税を利用することが大切です。
出典
日本年金機構 収入が公的年金等の場合 所得金額の早見表(1ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
世帯年収700万円です。ふるさと納税をした場合の控除額はいくらですか?「ふるさと納税」控除金額の上限は? 年収別にご紹介します
「どれでも2000円」と勘違いしてたくさん「ふるさと納税」してしまいました。オーバーした分はどうなるのでしょうか?

新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55