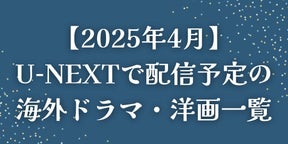来年定年退職するのですが、「退職金」は税金が引かれるのですか? ローン返済の計画を立てたいのですが、仕組みが分かりません。
3月10日(月) 17:30
退職金にかかる税金
基本的に、退職金には税金がかかります。受け取った退職金は退職所得として扱われ、その金額に応じた所得税や住民税などを支払わなければなりません。
また、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、正しい税金額が源泉徴収されます。そのため、基本的には確定申告を行う必要はありません。反対に、「退職所得の受給に関する報告書」を勤務先に提出しない場合は、退職金額の20.42%が源泉徴収されます。この場合は、確定申告を行って清算することで、納めすぎた税金が還付される可能性があります。
なお、退職金の受取時には退職所得控除を受けることが可能です。控除額が額面上の退職金額を上回れば、税金の支払いを避けて退職金を受け取れます。つまり、実質的に非課税となるわけです。退職所得控除を受けるには、「退職所得の受給に関する報告書」を勤務先に提出することが必要です。
退職所得控除を算出するには2種類の計算方法がありますが、どちらの計算方法を用いるかは勤続年数で区別されます。
勤続年数が20年以下の場合は、40万円に勤続年数を掛けたものが控除額です。なお、最低控除額は80万円です。勤続年数が15年の場合は控除額が600万円になるため、退職金額が600万円以下であれば税金がかかりません。
勤続年数が20年を超えている場合は、70万円×(勤続年数-20年)+800万円の計算結果が控除額になります。仮に勤続年数が30年の場合は、控除額が1500万円になります。つまり、額面上の退職金が1500万円以下であれば、税金がかかりません。
退職金にかかる税金は、上記の控除後の金額を基に算出されます。額面上の退職金額が控除額を下回れば、税金はかかりません。
そのため、退職金の金額と勤続年数によっては、退職金の受取時に税金を支払う必要がないケースもあります。自身の勤続年数を基に、退職所得控除額を算出してみてください。支払うべき税金額や、受け取れる年金額が明確になります。
退職金額の平均
厚生労働省の中央労働委員会が発表した「令和5年賃金事情等総合調査」では、令和4年度における退職金支給額の平均が退職事由別にまとめられています。定年退職の場合は1878万3000円、会社都合では1399万9000円、自己都合の場合は487万5000円です。
税金を支払わずに1878万3000円の退職金を得るためには、勤続年数が36年である必要があります。勤続年数が36年であれば、退職所得控除額は1920万円と、退職金額が退職所得控除額を下回ることが理由です。
また、同調査では、男性の定年退職者における退職金支給額の平均が、学歴と勤続年数別で記載されています。大学卒で勤続35年の場合における退職金支給額の平均は1867万6000円、満勤勤続の場合は2139万6000円です。対して、高校卒の場合は勤続35年で1319万8000円、満勤勤続で2019万9000円です。あくまで平均額ですが、同じ勤続年数であれば、大学卒のほうが退職金は多いことが分かります。
退職金に税金はかかる
基本的に、退職金には税金がかかります。しかし、退職所得控除の金額次第では、税金を支払わずに退職金を受け取ることも可能です。非課税で退職金を受け取るためには、勤続年数などを基に算出される退職所得控除額が、額面上の退職金額を上回る必要があります。つまり、実際に退職金に税金がかかるかどうかは、勤続年数と退職金の金額次第といえます。
出典
国税庁 退職金と税
厚生労働省 中央労働委員会 賃金事情等総合調査 「令和5年退職金、年金及び定年制事情調査」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
退職金を受け取った翌年、住民税がとんでもないことに…。事前にできる対策って?退職するなら65歳よりも、64歳と11ヶ月のほうがお得? いったいどういうこと?
59歳で貯蓄は「2500万」です。60歳でリタイアしても暮らしていけますか?

新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55