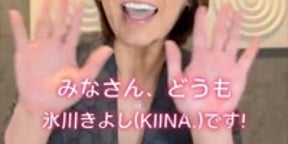「定年後」に必要な「生活費」はどれくらい? 「二世帯住宅」で暮らす場合の費用分担のポイントなどを詳しく解説。
3月10日(月) 1:10
定年後に必要な生活費
定年後の生活費について考えるために、65歳以上の単身無職世帯の平均家計収支を参考にしてみます。総務省統計局の2023年データによれば、これらの世帯の毎月の実収入は12万6905円ですが、支出が収入を上回り、3万768円が不足している状況です。
この不足分を貯金などからまかなえるのであればよいですが、もし貯金が心もとないという場合には、パートなどで収入を得るなどして、毎月最低でも約16万円の生活費を確保する必要があるといえるでしょう。なお、収支の詳細は以下の通りです。
【65歳以上の単身無職世帯の収支概要】
・収入の内訳
社会保障給付:11万8230円
その他収入:8675円
・支出の内訳
食費:4万103円
住居費:1万2564円
光熱・水道費:1万4436円
交通・通信費:1万5086円
交際費:1万5990円
その他支出:3万821円
税金や保険料などの非消費支出:1万2243円
このように、生活費は収入を大きく超える場合が多く、計画的な準備が必要となる可能性があります。
二世帯生活の課題
二世帯で暮らし始めると、水道代や光熱費、食費といった支出を正確に分けるのは難しいかもしれません。水道代や光熱費に関しては、多くの場合支払いは口座振替で管理されますが、その際に負担の割合が曖昧になったり、支払い忘れが生じたりすることもあります。
このような状況が続けば、家計負担が偏り、不満が蓄積する原因になる可能性があります。それが原因で、感情的な対立に発展するケースも考えられるでしょう。
二世帯住宅の共有部分と費用分担のポイント
二世帯住宅では、それぞれの世帯が独立して暮らしているように見えても、実際には共有する部分が意外と多く存在するといわれています。共有部分の費用を各世帯で分担できれば、経済的な負担を軽減できる可能性があります。
例えば、完全同居型の二世帯住宅では、電気代や水道代などの光熱費はすべて共通の支出となります。また、食事が一緒であれば、食費も共有項目に含まれます。ほかにも、インターネットの通信費や新聞代をはじめ、固定資産税も共有部分として挙げられるでしょう。
なお、一部だけ共有する構造の二世帯住宅は、独立した部分の費用分担がしやすい反面、共有部分の使用量を明確にするのは難しいことがあります。
どのような住居スタイルであっても、意外と共有部分は多いものです。どこが共有に該当するのかを事前に確認しておくことで、費用分担のルール作りやトラブル防止に役立つ可能性があります。
お金の問題は事前に丁寧な話し合いを
お金の問題は、親子間であってもトラブルの原因になりやすいものです。二世帯住宅で暮らす場合も、親子の収入状況や働き方の違いが、生活費用の負担に対して不均衡を引き起こすことがあります。
親世帯と子世帯の生活費の負担割合が変動するケースとして、以下のような状況が考えられます。
・親世帯が現役で働いており、親世帯が負担している
・親世帯が高齢で収入が減少したため、子世帯が負担している
このように、生活費の負担が変動する状況は、当初は小さな差でも、時間が経つにつれて大きな不公平感に発展することがあります。場合によっては、世帯間の関係に亀裂を生じさせることも考えられるでしょう。
こうした問題を避けるためには、二世帯住宅を選ぶ段階で、費用負担に関する具体的なルールを決めておくことが重要です。お金に関する取り決めは、同居生活において避けられないテーマだと考えられます。暮らし始めた後でトラブルが発生しないよう、事前に十分な話し合いを重ね、ルールを明確にしておくことが求められます。
なお、意見に違いが生じた場合には、率直なコミュニケーションを大切にし、互いに納得できる解決策を見つける姿勢が必要です。こうした取り組みが、二世帯住宅での円満な生活を築く鍵となる可能性があります。
生活費の分担や共有部分の費用負担について明確なルールを決めることが必要不可欠
定年後に子どもの家で暮らす場合、生活費の分担や共有部分の費用負担についての明確なルールを決めることが必要不可欠だと考えられます。特に、水道代や光熱費、食費といった支出は、二世帯住宅特有の課題としてトラブルに発展する可能性があります。
家計のバランスを保つためには、親子それぞれの収入状況や生活スタイルを考慮した柔軟なルール作りと、問題が起きた際の円滑なコミュニケーションが欠かせません。また、事前に費用分担について丁寧に話し合い、双方が納得する取り決めをしておくことで、不必要な衝突を防げる可能性があるでしょう。
安心で快適な二世帯生活を実現するためには、「助け合い」と「話し合い」の姿勢を大切にし、日々の暮らしをともに築いていくことが成功の鍵となる可能性があります。
出典
総務省統計局家計調査報告〔家計収支編〕2023年(令和5年)平均結果の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
老後貧困に陥らないために、50代の時点で「1500万円の貯金」があります。これって普通ですか?65歳以上で貯蓄が「2000万円」ある世帯はどれくらい? 最低限必要な貯蓄額はいくら?
「私は年金だけで大丈夫」そう言えるのは現役時代の年収がいくらの人? 「老後に必要な生活費」をもとに検証

新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55