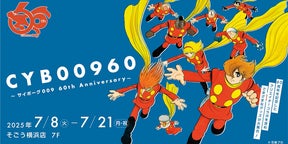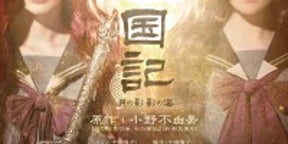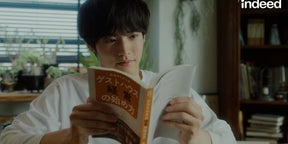生命保険は「貯蓄」にも使える?保障・運用・節税まで幅広く活用できる理由とは
2月22日(土) 12:50
生命保険の機能と生命保険料の構造
生命保険には、保障機能、資産運用機能、資金調達機能など、さまざまな機能があります。なぜこのように多彩な機能があるかは、生命保険料の構造に根差しています。生命保険料の構成は次のとおりです。
1.純保険料
:保険料の支払いの原資になるもの
死亡保険料
:死亡保険金支払の財源となる部分
生存保険料
:満期保険金、解約返戻金支払の財源となる部分
2.付加保険料 :保険会社の事務処理に加え、保険の仕組みを維持・管理するための費用
死亡保険料・生存保険料は、予定死亡率・予定利率を基礎として計算します。
また、付加保険料は予定事業費率を基礎として計算します。死亡保険料に比重を置くと、保障機能が強い保険になります。代表的なものは、死亡保障に特化した定期保険および終身保険です。
これに対し、生存保険料に比重を置くと保障機能だけでなく、貯蓄機能も兼ね備えた保険になります。代表的なものは、養老保険、個人年金保険、学資保険などです。
さらに生命保険は税務面でも優遇されているので、そこに比重を置くと、節税機能を重視した保険になります。代表的な例は、契約者が自分自身を被保険者にして相続人を保険金受取人にする、終身保険です。これにより、「500万円×法定相続人」の数に相当する非課税枠が適用され、相続税を節税することができます。
また、変額保険(資産運用保険)に加入して、満期保険金または解約返戻金を一時金で受け取ると「一時所得」となり、大幅な節税が実現できます。
生命保険料を決める3要素
生命保険料は先述のとおり、予定死亡率、予定利率、予定事業率によって決まります。
予定死亡率
保険会社は、生命表に基づいて年齢ごとに「何人が死亡し、何人が生き残るか」を予測します。それをもとに将来の保険金に充てる保険料の計算を行いますが、その際に使用する死亡率を「予定死亡率」といいます。
予定利率
保険料の一部は、将来の保険金の支払いに備えて、保険会社に積み立てられ、運用されます。保険会社はある一定の運用収益を見込んで、保険料を設定します。
予定利率を高く見込めば、運用利益率が高くなるので、保険料を安く設定できます。すなわち、保険料に比べて大きな死亡保険金や満期保険金を受け取ることができますが、予定利率は保険契約が終了するまで維持されなくてはいけないので、安全性・確実性を重視して決められます。
保険会社の予定利率は、金融庁が発表する国債利回りをベースにした「標準利率」をもとに、各保険会社が決定します。2017年7月以降現在まで、標準利率は年0.25%と低く設定されているので、予定利率もかなり低いレベルになっています。
予定事業費率
保険事業の運営上必要とする経費である、「付加保険料」を算出するのに用いられます。いわば、保険をアレンジするためのコストということができます。
保険料の運用
生命保険は一般的に「定額保険」といわれ、運用成果に関係なく、保険金額・給付金額・年金額などが一定になるように設計されています。
すなわち、実際の死亡率・運用利率・事業費率が、予定死亡率・予定利率・予定事業費率と異なっても、その差額は保険会社が吸収したり、配当金として契約者に分配したりして、契約者には契約どおりの支払いを行う仕組みになっています。
生存保険料の運用は予定利率により行われますが、先に述べたように予定利率はかなり低いレベルに抑えられています。従って、養老保険、学資保険、個人年金保険などの、満期保険金を支払う保険の利回りは、かなり低いレベルになっています。
これを補うために変額保険(資産運用保険)があります。
変額保険とは名前のとおり、満期保険金額・解約返戻金額が変動することを前提に、保険会社が外貨・株式・債券・投資信託などへ保険料を投資して運用し、運用の成果を契約者に還元する仕組みの保険です。うまくいけば、定額保険の予定利率をはるかに超える利回りを得ることもできますが、そうでない場合は元本割れのリスクもあります。
これは定額保険とは全く違う保険なので、定額保険とは切り離した特別口座で運用されます。
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表CFPファイナンシャルプランナー
【関連記事】
死亡保険金に相続税がかかる場合って?生命保険でどこまで非課税になるの?満期保険金を受け取ったら確定申告は必要? ペナルティーを受けないために知っておきたいこと
学資保険の祝い金や満期保険金は受け取り方によって税金が変わる? 賢い受け取り方とは?

新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55