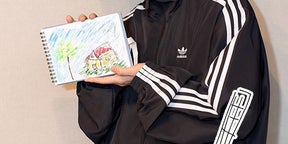実家で昔のチラシを見ていたら「消費税」の記載がなくてびっくり! 昭和は消費税がなかったの? 4500万円の住宅を「410万円」安く買えてたって本当?
2月15日(土) 19:20
消費税の歴史
消費税が日本で導入されたのは1989年で、税率は3%でした。1997年に5%に引き上げられ、2014年には8%、2019年には10%まで引き上げられました。つまり、36年前までは消費税はかからなかったということです。
消費税が導入される前は、物品税などの個別消費税が採用されており、物品の種類によって異なる税率が適用されていました。消費税の導入により、個別消費税の多くは廃止されましたが、現在でも酒類・たばこ・揮発油などに対する個別消費税は存続しています。
消費税は何に使われている?
現在の消費税率である10%の内訳は、消費税7.8%、地方消費税2.2%となっています。7.8%の内、1.52%は地方交付税分とされており、実質的には地方に3.72%分配されていることになります。残りの6.28%は社会保障費(年金・介護・医療・少子化対策)の財源に充てられています。
消費税は以下のような理由で安定的な財源として考えられています。
●現役世代など特定の世代に負担が偏らない
●景気(経済動向)などの変化に左右されにくい
●経済活動に対する影響が小さい
社会保障制度は基本的に保険料による支えあいになりますが、少子高齢化が非常に速いスピードで進む日本においては、現役世代の負担や国の借金がどんどん大きくなってしまいます。それを防ぐために、全世代が負担する安定的な社会保障の財源や地方を支える財源として消費税による税収が使われています。
もし消費税がなかったら、物価はどうなる?
仮に消費税がなかったら、現在のモノ・サービスの価格はどうなるのでしょうか?
例えば、税込み230円の牛乳は213円(軽減税率の8%を適用)、税込み1万円の衣服は9091円、1ヶ月分の食費が8万円(税率8%)だった場合、7万4075円となります。
それでは高額商品に消費税が適用されない場合、価格はどうなるでしょうか?
税込み100万円の腕時計は約91万円となり、400万円の新車は約364万円となります。4500万円の住宅であれば、約4091万円と、410万円も価格が下がり、そのお金で新車が購入できるほどです。
消費税が適用されているモノ・サービスを1ヶ月で20万円分購入すれば、月に約1万8000円、1年間で約22万円の消費税を払っている計算(税率10%で計算)となります。普段の買い物ではあまり気にならないかもしれませんが、高額商品や年間で換算すると消費税の負担額の多さに気づくのではないでしょうか。
まとめ
消費税の歴史はまだ浅いですが、導入開始から30年で3%から10%まで引き上げられ、その多くは、地方交付税や年金・医療介護などの社会保障に使われています。
消費税がなければ、当然モノ・サービスの価格は低下するので、消費者としてはうれしい反面、税収減により、年金の減額や医療・介護費の負担増、子育て支援が減るほか、地方のインフラや地方自治体のサービスが低下することも予想されます。
消費税をなるべく払いたくないと思うかもしれませんが、その税収により恩恵を受けている部分もあることを理解しておきたいところです。
出典
財務省 消費税の使途に関する資料
国税庁 税の歴史
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
定年退職の時点で「貯蓄4000万」の世帯は全国にどのくらいいる?65歳以上で貯蓄が「2000万円」ある世帯はどれくらい? 最低限必要な貯蓄額はいくら?
60歳で貯金0円!しかも年金は5万円のみ・・生活できるの?

新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55