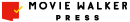ソフィア・コッポラが第76回アカデミー賞で脚本賞のオスカーを受賞した『ロスト・イン・トランスレーション』/[c]2003, Focus Features all rights reserved
GWはアニエス・ヴァルダ、ソフィア・コッポラらの傑作をイッキ見!いま観るべき女性映画作家4人を振り返る
4月26日(金) 12:30
近年、往年の映画作家たちのレトロスペクティブ上映が好評を博している。例えば2022年から開始されたウォン・カーウァイの特集上映では連日満席のヒットを記録したが、注目すべきはかつて作品に親しんでいた層のみならず、20代などの若い世代も劇場に足を運んだことだろう。レトロスペクティブ上映はそうして、新たな世代と名作との出逢いの場ともなっている。最近では『アル中女の肖像』(79)などで知られるドイツのウルリケ・オッティンガーや、ケリー・ライカートらの名前を引き合いに出しつつ称賛されてきたアメリカのニナ・メンケスをはじめ、映画史において重要とされながらも日本ではなかなか日の目を浴びてこなかった女性映画作家たちの特集上映が立てつづけに組まれ、いま再評価の波にある。レトロスペクティブ上映は当時、劇場公開の機会に恵まれてこなかった不遇の作家たちをも掬い上げているのだ。そんなレトロスぺクティブ上映で取り上げられる名作が、いまなら配信で楽しめる。今回は、Amazon Prime Video チャンネル「スターチャンネルEX」で配信中の作品から、自宅でのレトロスペクティブ上映を提案していきたい。
【写真で見る】GWは女性映像作家たちの傑作映画を自宅で!アニエス・ヴァルダ、ソフィア・コッポラなど名監督がずらり

■“女性監督”のパイオニア、アニエス・ヴァルダ


長編デビュー作の『ラ・ポワント・クールト』(54)でキャリアを開始し、“女性監督”のパイオニアとして映画史を切り拓いてきたアニエス・ヴァルダ。放浪者だった少女モナ(サンドリーヌ・ボネール)の最期の痕跡を追う『冬の旅(1985)』(85)は、批評家などからヴァルダのフィルモグラフィにおける最高傑作として絶賛されてきた。ドキュメンタリー映画も数多く手掛けたヴァルダはこの『冬の旅(1985)』以前にも、癌の検査結果を聞くまでの女性の時間を追体験させる『5時から7時までのクレオ』(61)や、妻が夫から不倫の事実を告白されて一家に亀裂が入る『幸福(しあわせ)』(64)といった劇映画において、常に女性の死の気配を招き入れてきた。場面が切り替わる瞬間に画面が原色に染め上げられるほど色彩が横溢する『幸福(しあわせ)』は、荒む冬の枯れた景色の『冬の旅(1985)』と画調としては対極にあるが、どちらも厳しいまなざしで女性の生が置かれた不遇を告発している作品だといえるだろう。

『冬の旅(1985)』は劇中で移動撮影を効果的に繰り返すため、直向きに歩きつづけるモナの姿に最も残像効果を施す。最期まで創作活動に身を捧げながら2019年にこの世を去ったヴァルダの遺作『アニエスによるヴァルダ』(19)で、彼女は移動撮影装置に自ら乗りながらこの移動ショットについて、洋文では通常左から右に読むために右から左へと移行する運動は違和感を喚起させること、移動ショットの終わりが次のショットとリンクしていること、そうして「自分にしか分からない謎」を映像に残したかったことを語った。ヴァルダの映画は強いメッセージ性を抱え込んでいながら、映画としての技巧性や形式美もまた豊かにある。貧困と社会の周縁に置かれた人々を描くドキュメンタリー映画『落穂拾い』(00)でヴァルダが「芸術家が試みるのはすべて“自画像”だ」というように、ヴァルダ自身の片鱗も作品の随所に認められるが、どこにもない生き方で歩きつづけた崇高な放浪者たるモナの精神を、不寛容な世界のしがらみから逃れたいと願う私たち自身もまた、宿しているに違いない。


■異なる世代の女性同士の関係性を描かせたら並ぶ者なしのメーサーロシュ・マールタ


ヴァルダはまた、女性で初めてベルリン国際映画祭金熊賞を受賞するなど国際的な映画監督でありながらも、日本では長らく本格的な劇場公開の機会に恵まれてこなかったハンガリーの映画作家メーサーロシュ・マールタを評価していた一人だった。マールタのフィルモグラフィでは、とくに異なる世代の女性同士の関係性が特別な輝きを放つ。“母”になりたい女性と“妻”になりたい女性の交差が描かれた『アダプション/ある母と娘の記録』(75)はマールタにとって最重要作の一本であり、“結婚”と“子ども”のテーマを俎上に載せる。工場勤務で未亡人のカタ(ベレク・カティ)は、別の相手と結婚関係にある恋人に「子どもが欲しい」と打ち明けるが、家庭を壊したくないその恋人はカタを拒絶してしまう。その矢先、カタは若くして恋人との結婚を熱望しているアンナ(ヴィーグ・ジェンジェヴェール)を気に留め、次第に仲を深めてゆく。多義的な結末は、“結婚”や“子ども”が女にとって最上の幸せであるはずだとする社会通念を揺るがすようでもあり、マールタはそうして女たちを異性愛規範に基づく伝統的な家族像への信仰から逸脱させてみせている。

世代の異なる女性2人の関係性は、『マリとユリ』(77)で再び変奏される。工員寮の責任者を務めるマリ(マリナ・ヴラディ)は、モンゴルへの出張を決めた夫との長年の結婚生活に抑圧されており、彼女は寮に子どもと住まわせてやることになったユリ(モノリ・リリ)を“初めて本音で話せる女性”と慕う。シャワーを浴びているマリと服のまま闖入してきたユリが濡れながら笑い合う瞬間は、映画のなかで数少ない多幸感あふれる場面のひとつとして心を震わす。マールタ映画において男女の関係は不安定でかつ脆弱性が取り巻くが、一方で女性同士の関係は友情ともロマンスともつかぬ形容し難い親密さが芳醇に漂う。また、マールタは妊娠や出産を重要な主題として扱うだけでない。『ナイン・マンス』(76)では撮影当時妊娠していた主演俳優のモノリ・リリの分娩までも実際に映画に収めさえしており、その映画史に残る記録的瞬間も見逃せない。

■実験的なスタイルで魅了したシャンタル・アケルマン

主婦の1日の家事労働を遅延した時間のなかカメラで捉えたフェミニズム映画の金字塔『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』(75)で知られるベルギーの映画作家シャンタル・アケルマンは、ほかにも実験的なスタイルの映画を数多く世に送りだした。例えばドキュメンタリー映画『家からの手紙』(77)は、ニューヨークのどこか荒涼とした風景を映しだしながら、アケルマンが断続的に母親からの手紙を朗読してゆく。そこにはアケルマンも、その母も実際に姿を現すことはない。その後、アケルマンにとって遺作となったドキュメンタリー映画『ノー・ホーム・ムーヴィー』(15)では、ポーランド系ユダヤ人でアウシュヴィッツ強制収容所を生き残った母の日常にフォーカスが当てられている。


多くの時間が固定カメラによる長回しのショットで映され、定点観察的に様々な夜の人間模様が綴られてゆく『一晩中』(82)は、『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』や、三部からなる構成的な厳格さを携えた『私、あなた、彼、彼女』(74)などと等しく形式を重んじた作品群に連なるだろう。カロリーヌ・シャンプティエの撮影が美しいことはもはや言うまでもなく、人生の大事なモメントがすべて夜にしか起こらないのではないかという幻夢へと観客を誘う。

静寂とした『一晩中』とは月と太陽、陰と陽の関係といえるほどに対極的なアケルマンにとって唯一のミュージカル映画『ゴールデン・エイティーズ』(86)は美容院や服飾店などパリのブティック街を舞台に、色恋沙汰しかなくなってしまったかのような世界が仮構される。人と人はすれ違いざまに何度もぶつかるほど画面に鮨詰めにされ、鮮やかな色彩が飛び交う過剰さによって彩られる装飾性に胸が躍る。アケルマンがそのデビュー作『街をぶっ飛ばせ』(68)で発露させていた衝動的なエネルギーも彷彿とさせる『ゴールデン・エイティーズ』は「人生はうまくいくもの」と観る者をエンパワメントすると同時に、彼女のフィルモグラフィの多様さを知らしめる快作である。


■“ガーリーカルチャー”といえばソフィア・コッポラ


美しき姉妹たちが次々と自殺を遂げてゆく『ヴァージン・スーサイズ』(99)や、遊び心に満ちた独創的な伝記映画『マリー・アントワネット』(06)などで知られ、“ガーリーカルチャー”の代名詞ともいえる映画作家であるソフィア・コッポラ。名作『ゴッドファーザー』(72)を監督したフランシス・フォード・コッポラを父に持ち、『SOMEWHERE』(10)など自身のフィルモグラフィにおいてもセレブリティの孤独に焦点を当てたパーソナルな要素が含まれる作品も多い。クリント・イーストウッドが主演した『白い肌の異常な夜』(71)でも映像化されたトーマス・カリナンの小説「The Beguiled」をコッポラが新たに女性視点で翻案した『The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』(17)では、女子寄宿学校に負傷した北軍兵士の男が招き入れられ、男/女のあわいで支配/被支配のスリリングな攻防戦が繰り広げられてゆく。


■少女と女性の揺れ動く過渡期を繊細にスクリーンに刻んだ『プリシラ』

新作『プリシラ』(公開中)では、エルヴィス・プレスリー唯一の妻であったプリシラ・プレスリーの視点から知られざるラブロマンスが描かれている。『The Beguiled』と『プリシラ』はルックはまるで違えども、画面の底流には捕食者と被捕食者の性的闘争があるようであり、1つの屋敷や家に女性が隔離されている舞台もまたコッポラお馴染みの設定だろう。また、異国の地で2人が出逢うオープニングは、東京という異国の地で心許ないアメリカ人の男女が同じ時間を共有する『ロスト・イン・トランスレーション』(03)の再来も感じさせる。『プリシラ』は稀有なシンデレラストーリーでありながらも、そこにはありふれた感情が豊かに詰まっている。コッポラの映画だとすぐにわかる煌びやかな世界観は顕在でありつつ、少女がひとつの失恋を通じて大人の階段を上る、これまでで最もほろ苦い作品となった。コッポラは現代を代表する映画作家の一人として、少女と女性の揺れ動く過渡期を繊細にスクリーンに刻みつづけている。

今回は、女性映画作家たちの作品を取り上げたが、Amazon Prime Video チャンネル「スターチャンネルEX」なら、ほかにもアスガー・ファルハディ、ヴィム・ヴェンダース、ライナー・ヴェルナー・ファスビンダーらの貴重なレトロスペクティブ作品が堪能し放題。さらに映画の世界に深く足を踏み入れてゆくために、これを機にぜひご鑑賞いただきたい。
文/児玉美月
【関連記事】
・ 『プリシラ』エルヴィス色に染まるプリシラを映しだす本編チラ見せ&著名人から絶賛コメント続々
・ スターのシャイな一面を切り取るロマンティックな本編チラ見せ『プリシラ』コラボTシャツも発売
・ 歌にモノマネに司会に監督業まで!イタリアの国民的人気女優パオラ・コルテッレージってどんな人?
・ 「イタリア娯楽映画の進行形」シリーズ第2弾はパオラ・コルテッレージ特集!『あゝ無慈悲』など貴重なタイトルを一挙放送
・ 「宇宙空母ブルーノア」主題歌・川崎麻世が明かす、「ヤマト」からのプレッシャーと過酷な70年代アイドル事情
【写真で見る】GWは女性映像作家たちの傑作映画を自宅で!アニエス・ヴァルダ、ソフィア・コッポラなど名監督がずらり

■“女性監督”のパイオニア、アニエス・ヴァルダ


長編デビュー作の『ラ・ポワント・クールト』(54)でキャリアを開始し、“女性監督”のパイオニアとして映画史を切り拓いてきたアニエス・ヴァルダ。放浪者だった少女モナ(サンドリーヌ・ボネール)の最期の痕跡を追う『冬の旅(1985)』(85)は、批評家などからヴァルダのフィルモグラフィにおける最高傑作として絶賛されてきた。ドキュメンタリー映画も数多く手掛けたヴァルダはこの『冬の旅(1985)』以前にも、癌の検査結果を聞くまでの女性の時間を追体験させる『5時から7時までのクレオ』(61)や、妻が夫から不倫の事実を告白されて一家に亀裂が入る『幸福(しあわせ)』(64)といった劇映画において、常に女性の死の気配を招き入れてきた。場面が切り替わる瞬間に画面が原色に染め上げられるほど色彩が横溢する『幸福(しあわせ)』は、荒む冬の枯れた景色の『冬の旅(1985)』と画調としては対極にあるが、どちらも厳しいまなざしで女性の生が置かれた不遇を告発している作品だといえるだろう。

『冬の旅(1985)』は劇中で移動撮影を効果的に繰り返すため、直向きに歩きつづけるモナの姿に最も残像効果を施す。最期まで創作活動に身を捧げながら2019年にこの世を去ったヴァルダの遺作『アニエスによるヴァルダ』(19)で、彼女は移動撮影装置に自ら乗りながらこの移動ショットについて、洋文では通常左から右に読むために右から左へと移行する運動は違和感を喚起させること、移動ショットの終わりが次のショットとリンクしていること、そうして「自分にしか分からない謎」を映像に残したかったことを語った。ヴァルダの映画は強いメッセージ性を抱え込んでいながら、映画としての技巧性や形式美もまた豊かにある。貧困と社会の周縁に置かれた人々を描くドキュメンタリー映画『落穂拾い』(00)でヴァルダが「芸術家が試みるのはすべて“自画像”だ」というように、ヴァルダ自身の片鱗も作品の随所に認められるが、どこにもない生き方で歩きつづけた崇高な放浪者たるモナの精神を、不寛容な世界のしがらみから逃れたいと願う私たち自身もまた、宿しているに違いない。


■異なる世代の女性同士の関係性を描かせたら並ぶ者なしのメーサーロシュ・マールタ


ヴァルダはまた、女性で初めてベルリン国際映画祭金熊賞を受賞するなど国際的な映画監督でありながらも、日本では長らく本格的な劇場公開の機会に恵まれてこなかったハンガリーの映画作家メーサーロシュ・マールタを評価していた一人だった。マールタのフィルモグラフィでは、とくに異なる世代の女性同士の関係性が特別な輝きを放つ。“母”になりたい女性と“妻”になりたい女性の交差が描かれた『アダプション/ある母と娘の記録』(75)はマールタにとって最重要作の一本であり、“結婚”と“子ども”のテーマを俎上に載せる。工場勤務で未亡人のカタ(ベレク・カティ)は、別の相手と結婚関係にある恋人に「子どもが欲しい」と打ち明けるが、家庭を壊したくないその恋人はカタを拒絶してしまう。その矢先、カタは若くして恋人との結婚を熱望しているアンナ(ヴィーグ・ジェンジェヴェール)を気に留め、次第に仲を深めてゆく。多義的な結末は、“結婚”や“子ども”が女にとって最上の幸せであるはずだとする社会通念を揺るがすようでもあり、マールタはそうして女たちを異性愛規範に基づく伝統的な家族像への信仰から逸脱させてみせている。

世代の異なる女性2人の関係性は、『マリとユリ』(77)で再び変奏される。工員寮の責任者を務めるマリ(マリナ・ヴラディ)は、モンゴルへの出張を決めた夫との長年の結婚生活に抑圧されており、彼女は寮に子どもと住まわせてやることになったユリ(モノリ・リリ)を“初めて本音で話せる女性”と慕う。シャワーを浴びているマリと服のまま闖入してきたユリが濡れながら笑い合う瞬間は、映画のなかで数少ない多幸感あふれる場面のひとつとして心を震わす。マールタ映画において男女の関係は不安定でかつ脆弱性が取り巻くが、一方で女性同士の関係は友情ともロマンスともつかぬ形容し難い親密さが芳醇に漂う。また、マールタは妊娠や出産を重要な主題として扱うだけでない。『ナイン・マンス』(76)では撮影当時妊娠していた主演俳優のモノリ・リリの分娩までも実際に映画に収めさえしており、その映画史に残る記録的瞬間も見逃せない。

■実験的なスタイルで魅了したシャンタル・アケルマン

主婦の1日の家事労働を遅延した時間のなかカメラで捉えたフェミニズム映画の金字塔『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』(75)で知られるベルギーの映画作家シャンタル・アケルマンは、ほかにも実験的なスタイルの映画を数多く世に送りだした。例えばドキュメンタリー映画『家からの手紙』(77)は、ニューヨークのどこか荒涼とした風景を映しだしながら、アケルマンが断続的に母親からの手紙を朗読してゆく。そこにはアケルマンも、その母も実際に姿を現すことはない。その後、アケルマンにとって遺作となったドキュメンタリー映画『ノー・ホーム・ムーヴィー』(15)では、ポーランド系ユダヤ人でアウシュヴィッツ強制収容所を生き残った母の日常にフォーカスが当てられている。


多くの時間が固定カメラによる長回しのショットで映され、定点観察的に様々な夜の人間模様が綴られてゆく『一晩中』(82)は、『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』や、三部からなる構成的な厳格さを携えた『私、あなた、彼、彼女』(74)などと等しく形式を重んじた作品群に連なるだろう。カロリーヌ・シャンプティエの撮影が美しいことはもはや言うまでもなく、人生の大事なモメントがすべて夜にしか起こらないのではないかという幻夢へと観客を誘う。

静寂とした『一晩中』とは月と太陽、陰と陽の関係といえるほどに対極的なアケルマンにとって唯一のミュージカル映画『ゴールデン・エイティーズ』(86)は美容院や服飾店などパリのブティック街を舞台に、色恋沙汰しかなくなってしまったかのような世界が仮構される。人と人はすれ違いざまに何度もぶつかるほど画面に鮨詰めにされ、鮮やかな色彩が飛び交う過剰さによって彩られる装飾性に胸が躍る。アケルマンがそのデビュー作『街をぶっ飛ばせ』(68)で発露させていた衝動的なエネルギーも彷彿とさせる『ゴールデン・エイティーズ』は「人生はうまくいくもの」と観る者をエンパワメントすると同時に、彼女のフィルモグラフィの多様さを知らしめる快作である。


■“ガーリーカルチャー”といえばソフィア・コッポラ


美しき姉妹たちが次々と自殺を遂げてゆく『ヴァージン・スーサイズ』(99)や、遊び心に満ちた独創的な伝記映画『マリー・アントワネット』(06)などで知られ、“ガーリーカルチャー”の代名詞ともいえる映画作家であるソフィア・コッポラ。名作『ゴッドファーザー』(72)を監督したフランシス・フォード・コッポラを父に持ち、『SOMEWHERE』(10)など自身のフィルモグラフィにおいてもセレブリティの孤独に焦点を当てたパーソナルな要素が含まれる作品も多い。クリント・イーストウッドが主演した『白い肌の異常な夜』(71)でも映像化されたトーマス・カリナンの小説「The Beguiled」をコッポラが新たに女性視点で翻案した『The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』(17)では、女子寄宿学校に負傷した北軍兵士の男が招き入れられ、男/女のあわいで支配/被支配のスリリングな攻防戦が繰り広げられてゆく。


■少女と女性の揺れ動く過渡期を繊細にスクリーンに刻んだ『プリシラ』

新作『プリシラ』(公開中)では、エルヴィス・プレスリー唯一の妻であったプリシラ・プレスリーの視点から知られざるラブロマンスが描かれている。『The Beguiled』と『プリシラ』はルックはまるで違えども、画面の底流には捕食者と被捕食者の性的闘争があるようであり、1つの屋敷や家に女性が隔離されている舞台もまたコッポラお馴染みの設定だろう。また、異国の地で2人が出逢うオープニングは、東京という異国の地で心許ないアメリカ人の男女が同じ時間を共有する『ロスト・イン・トランスレーション』(03)の再来も感じさせる。『プリシラ』は稀有なシンデレラストーリーでありながらも、そこにはありふれた感情が豊かに詰まっている。コッポラの映画だとすぐにわかる煌びやかな世界観は顕在でありつつ、少女がひとつの失恋を通じて大人の階段を上る、これまでで最もほろ苦い作品となった。コッポラは現代を代表する映画作家の一人として、少女と女性の揺れ動く過渡期を繊細にスクリーンに刻みつづけている。

今回は、女性映画作家たちの作品を取り上げたが、Amazon Prime Video チャンネル「スターチャンネルEX」なら、ほかにもアスガー・ファルハディ、ヴィム・ヴェンダース、ライナー・ヴェルナー・ファスビンダーらの貴重なレトロスペクティブ作品が堪能し放題。さらに映画の世界に深く足を踏み入れてゆくために、これを機にぜひご鑑賞いただきたい。
文/児玉美月
【関連記事】
・ 『プリシラ』エルヴィス色に染まるプリシラを映しだす本編チラ見せ&著名人から絶賛コメント続々
・ スターのシャイな一面を切り取るロマンティックな本編チラ見せ『プリシラ』コラボTシャツも発売
・ 歌にモノマネに司会に監督業まで!イタリアの国民的人気女優パオラ・コルテッレージってどんな人?
・ 「イタリア娯楽映画の進行形」シリーズ第2弾はパオラ・コルテッレージ特集!『あゝ無慈悲』など貴重なタイトルを一挙放送
・ 「宇宙空母ブルーノア」主題歌・川崎麻世が明かす、「ヤマト」からのプレッシャーと過酷な70年代アイドル事情