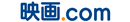アンヌ=ソフィー・バイイ監督
発達に遅れのある息子を一人で育てる母が恋に落ち、息子の恋人は妊娠――母として、女として揺れる心と母子の絆を繊細に描く「私のすべて」監督インタビュー
2月14日(土) 8:00
提供:
横浜フランス映画祭2025で「My Everything」のタイトルで上映され好評を博した「私のすべて」(公開中)。人生を息子に捧げてきた主人公の心と体の解放にエールを送り、彼らの新たな人生のはじまりのときを祝福する物語だ。このほど、アンヌ=ソフィー・バイイ監督のインタビューが公開された。
若くして授かった発達に遅れのある30歳過ぎの息子ジョエル(シャルル・ペッシア・ガレット)をずっとひとりで育ててきた。ジョエルは障害者のための職業作業所で働いている。互いを支え合い、いたわりながら暮らしてきた二人。ところがある日、モナは、ジョエルと同じ施設で働くオセアン(ジュリー・フロジェ)が彼の子を妊娠したと聞かされる。二人の関係を何も知らなかったモナは動揺し、母子の絆も揺らぎはじめる――。
本作は、「犬の裁判」(2024)で共同脚本を務めたフランスのバイイ監督の長編デビュー作。プレミア上映されたベネチア国際映画祭ではオーサーズ・アンダー40 賞最優秀監督賞含む3冠を受賞。「落下の解剖学」(2023)などを手掛け、気鋭監督を次々と生み出してきたプロデューサーのダヴィド・ティオンが新たに見出した才能だ。
――突然の子離れを迫られ動揺する母モナを演じたのは、TV シリーズ「エージェント物語」のノエミ役でブレイクしたフランスの人気俳優、ロール・カラミーです。彼女を起用した経緯について教えてください。
もともとこのシナリオを書いたときは彼女を想定していませんでした。最初のシナリオはもう少し年齢が上の方を主役に考えていたので、ジョエルは35歳、母親は60歳を想定していました。キャスティングはまず息子のジョエル役から始めました。障害を持っていて、且つきちんと演じることができる人を探すには、少し時間がかかると思ったのです。
先にジョエル役のキャスティングを進める間にジョエルの年齢が27~30歳ぐらいの設定に変わって、母親の年齢も少し若い設定になりました。その段階でロールのことを考えました。ロールは、フランスでは有名で、彼女の作品、それからお芝居もたくさん見ていました。彼女の感情表現には強い力があり、極限の状態に身を置いて演じることができる能力は、ジョン・カサベテス作品のジーナ・ローランズを思わせるほどです。初長編作品なので、私が直接、キャスティングすることはできないので、まずはモナ役は彼女がいいと提案をしました。それから彼女に会って、たくさん話をして、撮影に関しての説明をしました。
――モナの息子ジョエルを演じたのは、障害を持つ俳優としてはじめてセザール賞有望若手男優賞の一次候補に選出されたシャルル・ペッシア・ガレット、ジョエルの恋人オセアンは演技未経験で、施設での即興ワークショップで見出されたジュリー・フロジェです。障害を持つ当事者を起用することは当初から決めていましたか?
当事者を起用したいというのがプロデューサーにお願いした唯一の条件でした。そのためには「撮影期間が長くなります」ということをプロデューサーにお願いして受け入れてもらいました。彼らはちょっと疲れやすかったりするので、長時間の撮影はできません。でも、彼らが演じるということはすごく重要なこと。ひとつの代表として政治的な意味もあるし、映画的な要素をすごくたくさん持ってらっしゃるんですよね。視線とか、動き方とか。ジョエルを演じたシャルルもオセアンを演じたジュリーもすごく魅力的で、絵になる人たちです。
――演出する上で撮影中のスケジュールなど工夫した事はありますか?
まず撮影でははじめてのことではないかと思うのですが、時間の延長はなしです。もう一つはマルゴ・アルグド=ブジェステクさんというアクセシビリティ・コーディネーターの方に入ってもらいました。フランスでも新しいポストで彼女が第一人者なのですが、映画の撮影現場の管理ができて、尚且つ障害者のケアができるトレーニングを受けた人です。障害者の施設で訓練士もしていて、映画制作のこともよく知っている。彼女がシャルルとジュリーに関して対応してくれました。
シャルルに関しては動きや疲れやすさに気をつけました。ジュリーの方は、音に対して超敏感なので、彼女のおかげで撮影現場はとても静かだったのですが、彼女は自分が撮影をしているとき以外は音を遮断するヘッドフォンをしていました。面白かったのが、ラッシュを見たら、そのヘッドフォンをとり忘れて演技しているときもあって(笑) 最後のシーンは最後に撮影したのですが、フランスではクランクアップのとき皆で拍手をするのが慣例です。拍手の前にアシスタントがダッシュで慌ててジュリーにヘッドフォンをかぶせて、そのあと皆で静かに拍手しました。撮影の慣習は変わらないけど、皆で適応するという感じでしたね。
――あなあの初長編監督作品ですが、フランス映画界におけるジェンダーバランスについて教えて下さい。
ジェンダーバランスについては業界の中の一部の人たちの努力もあって、以前より若い女性の監督が仕事をしやすくなっているのは確かです。ただ全体的に見ると、女性監督の映画の方が予算が少ないです。1作目は結構やらせてもらえるのですが、2作目、3作目になると女性監督が少なくなっていきます。そして子供が生まれると姿が見えなくなっていく……というようなことはありますので。この作品のプロデューサーは、「落下の解剖学」のプロデューサーでもあったので、若い女性の監督をすごく牽引してくれている方です。言いたいことを言わせてくれますし、そういう意味
では希望もあります。今後続けていく上で、予算がもっとつくことと、キャリアを続けていけるような環境作りが必要ではないかと思います。
――学生時代は演劇と政治学を学んだそうですが、政治学を学んだのは社会を変えていきたいという思いがあったのですか?
政治を勉強したのは、私は若い女性としてすごく政治に期待をしていたんです。今はあまり期待しなくなりましたが。社会への問題提起は映画を作りながらやっていく方向に変わっています。政治家を目指すということはありません。映画を作ったり、他の人のシナリオを書いたりすることによって、少しでも観る人の意識が変わったり、社会的な変化を促すことができるのではと思っています。ジェンダーの問題も色々なテーマの中で重要なテーマのひとつです。
――主人公のモナは息子をケアする母親であると同時に恋もする女性です。一人の人間の多様な面のバランスについてどう捉えていますか?日本では「お母さん」「妻」「娘」など社会的な役割に縛られてしまう事が多いのですが。
私は俳優をしていたのですが、古典の作品の中での女性像はほぼ3つにわけられています。処女か母親か娼婦です。大袈裟かもしれませんが、ほぼ3つに分けられる。だけど私は、人物像に色々な逆説、パラドックスを入れていくのがすごく好きで。例えば母親になるとすごく期待される母親像がある。そしてそれに母親自身が制約されていくわけです。たくさんの事ができなくなることが多い。そういう母親である女性は、逆に言えばすごく奥が深くおもしろい。ひとりひとりの母親がドラマになるような人生を生きているわけですから。「こうしなければいけない」という命令のようなものの中で存在していくのはすごく大変で……モナの場合は、息子に障害があって、シングルで育てているという、更なる制約がある中で変化をしていく。描く上ですごく興味を引かれるテーマだと思いました。
――日本の観客にメッセージをお願いします。
日本の社会とこの映画がどのように響きあうのか好奇心を持っています。日本の社会のことをあまりよく知らないので。それぞれの社会に周縁の人たちがいるわけですが、実は接する機会は多くない。自分とは「違う」と感じる人たちが、どのような存在なのか、この映画とどのように関わっていくのか。みなさんがどう感じるのか知りたいと思っています。この映画を見て自分や周りの人が少し自由になれると思ってもらえたら嬉しいです。
「私のすべて」はヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国順次公開。
【作品情報】
・ 私のすべて
【関連記事】
・ 【動画】「私のすべて」予告編
若くして授かった発達に遅れのある30歳過ぎの息子ジョエル(シャルル・ペッシア・ガレット)をずっとひとりで育ててきた。ジョエルは障害者のための職業作業所で働いている。互いを支え合い、いたわりながら暮らしてきた二人。ところがある日、モナは、ジョエルと同じ施設で働くオセアン(ジュリー・フロジェ)が彼の子を妊娠したと聞かされる。二人の関係を何も知らなかったモナは動揺し、母子の絆も揺らぎはじめる――。
本作は、「犬の裁判」(2024)で共同脚本を務めたフランスのバイイ監督の長編デビュー作。プレミア上映されたベネチア国際映画祭ではオーサーズ・アンダー40 賞最優秀監督賞含む3冠を受賞。「落下の解剖学」(2023)などを手掛け、気鋭監督を次々と生み出してきたプロデューサーのダヴィド・ティオンが新たに見出した才能だ。
――突然の子離れを迫られ動揺する母モナを演じたのは、TV シリーズ「エージェント物語」のノエミ役でブレイクしたフランスの人気俳優、ロール・カラミーです。彼女を起用した経緯について教えてください。
もともとこのシナリオを書いたときは彼女を想定していませんでした。最初のシナリオはもう少し年齢が上の方を主役に考えていたので、ジョエルは35歳、母親は60歳を想定していました。キャスティングはまず息子のジョエル役から始めました。障害を持っていて、且つきちんと演じることができる人を探すには、少し時間がかかると思ったのです。
先にジョエル役のキャスティングを進める間にジョエルの年齢が27~30歳ぐらいの設定に変わって、母親の年齢も少し若い設定になりました。その段階でロールのことを考えました。ロールは、フランスでは有名で、彼女の作品、それからお芝居もたくさん見ていました。彼女の感情表現には強い力があり、極限の状態に身を置いて演じることができる能力は、ジョン・カサベテス作品のジーナ・ローランズを思わせるほどです。初長編作品なので、私が直接、キャスティングすることはできないので、まずはモナ役は彼女がいいと提案をしました。それから彼女に会って、たくさん話をして、撮影に関しての説明をしました。
――モナの息子ジョエルを演じたのは、障害を持つ俳優としてはじめてセザール賞有望若手男優賞の一次候補に選出されたシャルル・ペッシア・ガレット、ジョエルの恋人オセアンは演技未経験で、施設での即興ワークショップで見出されたジュリー・フロジェです。障害を持つ当事者を起用することは当初から決めていましたか?
当事者を起用したいというのがプロデューサーにお願いした唯一の条件でした。そのためには「撮影期間が長くなります」ということをプロデューサーにお願いして受け入れてもらいました。彼らはちょっと疲れやすかったりするので、長時間の撮影はできません。でも、彼らが演じるということはすごく重要なこと。ひとつの代表として政治的な意味もあるし、映画的な要素をすごくたくさん持ってらっしゃるんですよね。視線とか、動き方とか。ジョエルを演じたシャルルもオセアンを演じたジュリーもすごく魅力的で、絵になる人たちです。
――演出する上で撮影中のスケジュールなど工夫した事はありますか?
まず撮影でははじめてのことではないかと思うのですが、時間の延長はなしです。もう一つはマルゴ・アルグド=ブジェステクさんというアクセシビリティ・コーディネーターの方に入ってもらいました。フランスでも新しいポストで彼女が第一人者なのですが、映画の撮影現場の管理ができて、尚且つ障害者のケアができるトレーニングを受けた人です。障害者の施設で訓練士もしていて、映画制作のこともよく知っている。彼女がシャルルとジュリーに関して対応してくれました。
シャルルに関しては動きや疲れやすさに気をつけました。ジュリーの方は、音に対して超敏感なので、彼女のおかげで撮影現場はとても静かだったのですが、彼女は自分が撮影をしているとき以外は音を遮断するヘッドフォンをしていました。面白かったのが、ラッシュを見たら、そのヘッドフォンをとり忘れて演技しているときもあって(笑) 最後のシーンは最後に撮影したのですが、フランスではクランクアップのとき皆で拍手をするのが慣例です。拍手の前にアシスタントがダッシュで慌ててジュリーにヘッドフォンをかぶせて、そのあと皆で静かに拍手しました。撮影の慣習は変わらないけど、皆で適応するという感じでしたね。
――あなあの初長編監督作品ですが、フランス映画界におけるジェンダーバランスについて教えて下さい。
ジェンダーバランスについては業界の中の一部の人たちの努力もあって、以前より若い女性の監督が仕事をしやすくなっているのは確かです。ただ全体的に見ると、女性監督の映画の方が予算が少ないです。1作目は結構やらせてもらえるのですが、2作目、3作目になると女性監督が少なくなっていきます。そして子供が生まれると姿が見えなくなっていく……というようなことはありますので。この作品のプロデューサーは、「落下の解剖学」のプロデューサーでもあったので、若い女性の監督をすごく牽引してくれている方です。言いたいことを言わせてくれますし、そういう意味
では希望もあります。今後続けていく上で、予算がもっとつくことと、キャリアを続けていけるような環境作りが必要ではないかと思います。
――学生時代は演劇と政治学を学んだそうですが、政治学を学んだのは社会を変えていきたいという思いがあったのですか?
政治を勉強したのは、私は若い女性としてすごく政治に期待をしていたんです。今はあまり期待しなくなりましたが。社会への問題提起は映画を作りながらやっていく方向に変わっています。政治家を目指すということはありません。映画を作ったり、他の人のシナリオを書いたりすることによって、少しでも観る人の意識が変わったり、社会的な変化を促すことができるのではと思っています。ジェンダーの問題も色々なテーマの中で重要なテーマのひとつです。
――主人公のモナは息子をケアする母親であると同時に恋もする女性です。一人の人間の多様な面のバランスについてどう捉えていますか?日本では「お母さん」「妻」「娘」など社会的な役割に縛られてしまう事が多いのですが。
私は俳優をしていたのですが、古典の作品の中での女性像はほぼ3つにわけられています。処女か母親か娼婦です。大袈裟かもしれませんが、ほぼ3つに分けられる。だけど私は、人物像に色々な逆説、パラドックスを入れていくのがすごく好きで。例えば母親になるとすごく期待される母親像がある。そしてそれに母親自身が制約されていくわけです。たくさんの事ができなくなることが多い。そういう母親である女性は、逆に言えばすごく奥が深くおもしろい。ひとりひとりの母親がドラマになるような人生を生きているわけですから。「こうしなければいけない」という命令のようなものの中で存在していくのはすごく大変で……モナの場合は、息子に障害があって、シングルで育てているという、更なる制約がある中で変化をしていく。描く上ですごく興味を引かれるテーマだと思いました。
――日本の観客にメッセージをお願いします。
日本の社会とこの映画がどのように響きあうのか好奇心を持っています。日本の社会のことをあまりよく知らないので。それぞれの社会に周縁の人たちがいるわけですが、実は接する機会は多くない。自分とは「違う」と感じる人たちが、どのような存在なのか、この映画とどのように関わっていくのか。みなさんがどう感じるのか知りたいと思っています。この映画を見て自分や周りの人が少し自由になれると思ってもらえたら嬉しいです。
「私のすべて」はヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国順次公開。
【作品情報】
・ 私のすべて
【関連記事】
・ 【動画】「私のすべて」予告編