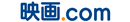公開中
【佐々木俊尚コラム:ドキュメンタリーの時代】「落語家の業」
12月15日(月) 14:00
提供:
現在73歳になる落語家、快楽亭ブラックの半生を描いた作品。昭和時代の残照とはこういう生き様のことを言うのだろうか。乱暴で無作法だったあの時代のにおいがぷんぷんしているドキュメンタリーであり、そのにおいに惹かれるかそれとも拒絶するかで、本作の評価はまっぷたつに分かれそうだ。
・ 【動画】「落語家の業」予告編
快楽亭ブラックは1952年、米軍兵士と日本人女性とのあいだに生まれた。その破天荒すぎる人生は、本作で実にリアルに描写されている。十代のころに立川談志(この人もほんとうに破天荒だった。不世出の落語家だったが、2011年に75歳で亡くなっている)に入門。白人青年役でテレビ番組にも出演し、なんと名優笠智衆とも共演するが、師匠から預かった金を競馬に使い込んだことが発覚して破門。この時点でまだ二十歳ぐらいである。
数年後に立川談志門下に復帰でき、明治・大正時代に活躍した外国人落語家の二代目として快楽亭ブラックを襲名した。ところが莫大な借金が発覚してまたも立川談志門下を退会し、さらにその直後には心筋梗塞や大動脈瘤乖離で倒れ、緊急手術で一命をとりとめた。
最近だと、弟子が交際している女性をシモネタにしてYouTubeでしゃべり、名誉毀損で訴えられて裁判になり敗訴。30万円の慰謝料の支払いを命じられたが、銀行口座には31万円しかない。そこで全額を競馬の有馬記念につぎ込んで……という滅茶苦茶ぶりである。
こういう話が本作にはてんこ盛りで出てくる。そのほとんどすべてが映像に残っているのもすごい。クライマックスは、名古屋の大須演芸場が家賃滞納で裁判所の強制執行になるシーンだろう。ここを拠点にしていた快楽亭ブラックは、強制執行のその日その時間に演芸場の舞台に出て、執行官を待ち構える。「待ってました!とかけ声を掛けましょう」と観客を煽り、苦虫をかみつぶしたような執行官がやってきて……。このシーンをつぶさに愉しむだけでも、本作の価値はあるだろう。
歴史を振り返れば、1990年代には「鬼畜系」というサブカルチャーのジャンルがあり、反道徳的な文化をことさらに誇示することが流行った。鬼畜系にかぎらず、あのころまでは一般社会のアウトサイダーであること、倫理や道徳を突き抜けて奔放に生きることはとてもカッコ良かった。コンプライアンスなどという言葉はまだ存在せず、軌道から外れて無頼に生きることが社会的にも許容されていた。
そうした過去に郷愁を感じ、あるいは若い世代でも憧れを感じる人は少なくない。昭和を題材にしてヒットした2024年の「不適切にもほどがある!」(TBS系)はまさにそういう欲望をピンポイントでうまく突いたテレビドラマだった。
とはいえ「ふてほど」はあくまでもフィクションであり、描かれた人物もセットも再現されたものに過ぎない。内容はきちんと2020年代のコンプライアンスに沿って作られている。だから安心して観ることができたのだ。
いっぽうで本作は、快楽亭ブラックという生身の人物をありのままに描いている。そのリアリティを目の当たりにすると、現代のわれわれは「あまりに不健康そう。もっと身体を大事にされたほうが良いのでは」などと余計な心配をしてしまう。奔放な行動も「まわりに迷惑をかけているのでは」と周囲の人への配慮のほうに気持ちが行ってしまう。
早逝したシンガー尾崎豊の1983年の名曲「15の夜」に、「盗んだバイクで走り出す」という歌詞がある。これに当時のファンたちはアウトサイダー的なカッコ良さを見いだしたが、現代の若者が聴くと「バイク盗まれた人かわいそう……」という感想になってしまうという話がある。本作を観たときに感じる、なんともいえないむず痒さや違和感のようなものは、まさにそういう現代と過去の価値観のズレにあるのかもしれない。
■「落語家の業」
2025年/日本
監督:榎園喬介
12月13日からユーロスペースほか全国順次公開
【作品情報】
・ 落語家の業
【関連記事】
・ 【最新版】本当に面白いおすすめ映画ランキングTOP30絶対に何度も見るべき“傑作”を紹介
・ Netflixで観てほしいおすすめの人気映画30選~編集部厳選~
・ 【本当に怖い映画30選】トラウマ&衝撃作を“ジャンル不問”で編集部が厳選
・ 【動画】「落語家の業」予告編
快楽亭ブラックは1952年、米軍兵士と日本人女性とのあいだに生まれた。その破天荒すぎる人生は、本作で実にリアルに描写されている。十代のころに立川談志(この人もほんとうに破天荒だった。不世出の落語家だったが、2011年に75歳で亡くなっている)に入門。白人青年役でテレビ番組にも出演し、なんと名優笠智衆とも共演するが、師匠から預かった金を競馬に使い込んだことが発覚して破門。この時点でまだ二十歳ぐらいである。
数年後に立川談志門下に復帰でき、明治・大正時代に活躍した外国人落語家の二代目として快楽亭ブラックを襲名した。ところが莫大な借金が発覚してまたも立川談志門下を退会し、さらにその直後には心筋梗塞や大動脈瘤乖離で倒れ、緊急手術で一命をとりとめた。
最近だと、弟子が交際している女性をシモネタにしてYouTubeでしゃべり、名誉毀損で訴えられて裁判になり敗訴。30万円の慰謝料の支払いを命じられたが、銀行口座には31万円しかない。そこで全額を競馬の有馬記念につぎ込んで……という滅茶苦茶ぶりである。
こういう話が本作にはてんこ盛りで出てくる。そのほとんどすべてが映像に残っているのもすごい。クライマックスは、名古屋の大須演芸場が家賃滞納で裁判所の強制執行になるシーンだろう。ここを拠点にしていた快楽亭ブラックは、強制執行のその日その時間に演芸場の舞台に出て、執行官を待ち構える。「待ってました!とかけ声を掛けましょう」と観客を煽り、苦虫をかみつぶしたような執行官がやってきて……。このシーンをつぶさに愉しむだけでも、本作の価値はあるだろう。
歴史を振り返れば、1990年代には「鬼畜系」というサブカルチャーのジャンルがあり、反道徳的な文化をことさらに誇示することが流行った。鬼畜系にかぎらず、あのころまでは一般社会のアウトサイダーであること、倫理や道徳を突き抜けて奔放に生きることはとてもカッコ良かった。コンプライアンスなどという言葉はまだ存在せず、軌道から外れて無頼に生きることが社会的にも許容されていた。
そうした過去に郷愁を感じ、あるいは若い世代でも憧れを感じる人は少なくない。昭和を題材にしてヒットした2024年の「不適切にもほどがある!」(TBS系)はまさにそういう欲望をピンポイントでうまく突いたテレビドラマだった。
とはいえ「ふてほど」はあくまでもフィクションであり、描かれた人物もセットも再現されたものに過ぎない。内容はきちんと2020年代のコンプライアンスに沿って作られている。だから安心して観ることができたのだ。
いっぽうで本作は、快楽亭ブラックという生身の人物をありのままに描いている。そのリアリティを目の当たりにすると、現代のわれわれは「あまりに不健康そう。もっと身体を大事にされたほうが良いのでは」などと余計な心配をしてしまう。奔放な行動も「まわりに迷惑をかけているのでは」と周囲の人への配慮のほうに気持ちが行ってしまう。
早逝したシンガー尾崎豊の1983年の名曲「15の夜」に、「盗んだバイクで走り出す」という歌詞がある。これに当時のファンたちはアウトサイダー的なカッコ良さを見いだしたが、現代の若者が聴くと「バイク盗まれた人かわいそう……」という感想になってしまうという話がある。本作を観たときに感じる、なんともいえないむず痒さや違和感のようなものは、まさにそういう現代と過去の価値観のズレにあるのかもしれない。
■「落語家の業」
2025年/日本
監督:榎園喬介
12月13日からユーロスペースほか全国順次公開
【作品情報】
・ 落語家の業
【関連記事】
・ 【最新版】本当に面白いおすすめ映画ランキングTOP30絶対に何度も見るべき“傑作”を紹介
・ Netflixで観てほしいおすすめの人気映画30選~編集部厳選~
・ 【本当に怖い映画30選】トラウマ&衝撃作を“ジャンル不問”で編集部が厳選