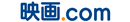本作が初共演となったマイケル・キートンとアル・パチーノ
マイケル・キートン、映画作りの醍醐味を語る監督・主演・製作の渾身作「殺し屋のプロット」【独占インタビュー】
12月5日(金) 9:00
提供:
老ヒットマンが人生最期の完全犯罪に挑む「殺し屋のプロット」で、監督・製作・主演を務めたマイケル・キートンのインタビューを映画.comが独占入手した。一人三役を担った渾身作を完成させたキートンが思う、映画作りの醍醐味とはーー。
・ 【フォトギャラリー】「殺し屋のプロット」メイキング写真
本作は、病によって記憶を失いつつある孤高の老ヒットマンが、人生最期の完全犯罪に挑むLAネオ・ノワール。キートンにとってキャリアの集大成とも言える渾身作。共演にはアル・パチーノをはじめ、マーシャ・ゲイ・ハーデン、ジェームズ・マースデン、ヨアンナ・クーリクら豪華キャストが集結。孤独な殺し屋の“終幕”を描き出す本作は、古典的なフィルム・ノワールのエッセンスを現代に継承する作品として、米バラエティでも「デヴィッド・フィンチャー監督『ザ・キラー』を凌駕するLAネオ・ノワール」と絶賛された注目作だ。
キートンが演じるのは、2つの博士号を取得している元大学教師で、元陸軍偵察部隊の将校という異色の経歴を持つ殺し屋ノックス。ある日、ノックスは急速に記憶を失う病だと診断され、殺し屋としての引退を決意する。しかし、その矢先、疎遠だった息子マイルズが彼の元を訪れる。マイルズはひょんなことから殺人を犯してしまい、助けを求めに来たのだった。次第に記憶が失われていくなか、愛する息子のために、ノックスは人生最期の完全犯罪に挑む。
「殺し屋のプロット」は、12月5日からkino cinema新宿ほか全国公開。キートンのインタビュー全文は以下の通り。
――最初に脚本を読んだときの印象と、この作品を引き受けた理由を教えてください。
読んでみて、「素晴らしい脚本だ。いつ撮ろう?」と思ったことを覚えている。脚本を読んでも、そのとき別の撮影をしていたり、プライベートで何かあったりして、一旦保留にすることは珍しくない。でも、この物語は頭から離れなかった。この映画はひとつのカテゴリーに収まらない。ノワールであると同時に家族の物語でもある。そして気付いたんだ。その“どこにも属さない感じ”こそ、この作品の魅力だと。
――殺し屋という役柄を演じるうえで、大事にしたことを教えてください。
今回、殺し屋の映画を撮ることになったけど、“殺し屋映画”をやりたいと思っていたわけじゃないんだ。というのも、すでに他の人たちが撮っているし、それ以上のものは撮れないと思っていたからね。でもこの脚本は違った。殺し屋という仕事はノックスにとってただの生業にすぎず、映画の中心は人間関係になっている。疎遠になった息子(ジェームズ・マースデン)や前妻(マーシャ・ゲイ・ハーデン)、そして良き友人でありメンターでもあるゼイヴィア(アル・パチーノ)とのね。
劇中でノックスは16年ぶりに息子と再会するが、病が急速に進行していると聞かされたばかりで、残された時間はわずかしかない。それでも行動するのは、和解のためだけでなく、息子を守るためなんだ。そこにドラマがあると思うよ。
――アル・パチーノとの初共演や、ほかのキャストとの関わりはいかがでしたか?
自分の“役者談義”はあまり面白くないと思っている。演技論を語ることが好きじゃないんだ。そういうことを話している自分の声を聞くのが好きではない。でも、他の俳優には興味がある。アル(・パチーノ)とは電話で話し始めたのが最初だった。登場人物についてあれこれと話したが、驚くほど気楽で気取らない会話だった。映画作りについての堅苦しい話はなく、自然だったんだ。
他のキャストも本当に素晴らしかった。マーシャ・ゲイ・ハーデンは、演じる上で行き詰まったときに、「ああ、あの人に頼めばなんとかしてくれる」と思える存在だ。「このシーンは無理だな」って思っても、彼女が演じると結局上手くいってしまうんだよ。
ジェームズ・マースデンに関しては、今回きっと度肝を抜かれると思うよ。素晴らしい演技だったし、彼は本当にいい奴なんだ。私との仕事のせいで彼が悪い影響を受けていないといいけど(笑)。
刑事役を演じたスージー・ナカムラは、出演作を何本か見たことがあって、いつも笑わされていた。この役にはコメディの経験がある人がほしいと思っていたのでピッタリだったね。面白い人というのは、ある種の知性を持っていて、こちらが予想しないことをしてくれる。皮肉屋で、自然体なのに笑える。男を怖がらず、自分を貫く女性。そんなイメージの役だったね。
――監督として現場に立ったとき、どんな挑戦がありましたか?
私はバカ正直なんだ。だから、撮影がタイトでリソースが限られていることを最初から関係者全員に伝えたよ。リハーサルの時間が無く、急遽撮影に入るしかなかった。予算も限られていて、撮影も25日間しかなかった。慌ただしく準備を進め、誰が空いているか確認し、すべてが上手くいくよう祈るしかなかった。制作過程は、本当に複雑でね。だから私は今回の映画を「ジェンガ・ムービー」と呼んでいたんだ。一部でも欠けたら、ストーリーは崩壊してしまうからね。
それでも、監督と主演と製作を兼ねることで、効率的に動ける部分もあったよ。自分のキャラクターを理解しているから、より早く動けるし、自分自身と議論する必要はないからね。ただ反省点は、自分自身に十分時間をかけられていなかったこと。他の俳優のときは、ちゃんと芝居を見て細かく目を配るのに、カメラが私の方を向いているときは、ちらっとモニターを見て「大丈夫」と言うだけだった。そこは気をつけなくちゃいけなかったね。
――監督・俳優・製作として参加した本作を振り返って、どのように感じていますか?
撮影については、ロケ地がLAということが、まず嬉しかったね。バレーの外れに「ここ誰が住んでるんだ?」って感じの場所があるだろう。昼間の2時にそういう寂れたモールを見てると不思議な気分になるんだ。あれがいいんだよ。
やっぱり物語を語るという行為には、ほかに代えがたい魅力がある。映像でしか伝えられないことや、言葉にせずとも伝わるものがある。そこが一番好きな部分だね。そして何より誇りに思っているのは、登場人物たちに命を吹き込んでくれた素晴らしい俳優たちの存在だ。彼らと一緒に仕事ができたことを、心から光栄に思っている。
【作品情報】
・ 殺し屋のプロット
【関連記事】
・ 【動画】「殺し屋のプロット」予告編
・ マイケル・キートン監督・主演・製作×アル・パチーノ共演「殺し屋のプロット」12月5日公開決定!
・ コッポラがAFI生涯功労賞を受賞盟友スピルバーグとルーカスが祝福
(C) 2023 HIDDEN HILL LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
・ 【フォトギャラリー】「殺し屋のプロット」メイキング写真
本作は、病によって記憶を失いつつある孤高の老ヒットマンが、人生最期の完全犯罪に挑むLAネオ・ノワール。キートンにとってキャリアの集大成とも言える渾身作。共演にはアル・パチーノをはじめ、マーシャ・ゲイ・ハーデン、ジェームズ・マースデン、ヨアンナ・クーリクら豪華キャストが集結。孤独な殺し屋の“終幕”を描き出す本作は、古典的なフィルム・ノワールのエッセンスを現代に継承する作品として、米バラエティでも「デヴィッド・フィンチャー監督『ザ・キラー』を凌駕するLAネオ・ノワール」と絶賛された注目作だ。
キートンが演じるのは、2つの博士号を取得している元大学教師で、元陸軍偵察部隊の将校という異色の経歴を持つ殺し屋ノックス。ある日、ノックスは急速に記憶を失う病だと診断され、殺し屋としての引退を決意する。しかし、その矢先、疎遠だった息子マイルズが彼の元を訪れる。マイルズはひょんなことから殺人を犯してしまい、助けを求めに来たのだった。次第に記憶が失われていくなか、愛する息子のために、ノックスは人生最期の完全犯罪に挑む。
「殺し屋のプロット」は、12月5日からkino cinema新宿ほか全国公開。キートンのインタビュー全文は以下の通り。
――最初に脚本を読んだときの印象と、この作品を引き受けた理由を教えてください。
読んでみて、「素晴らしい脚本だ。いつ撮ろう?」と思ったことを覚えている。脚本を読んでも、そのとき別の撮影をしていたり、プライベートで何かあったりして、一旦保留にすることは珍しくない。でも、この物語は頭から離れなかった。この映画はひとつのカテゴリーに収まらない。ノワールであると同時に家族の物語でもある。そして気付いたんだ。その“どこにも属さない感じ”こそ、この作品の魅力だと。
――殺し屋という役柄を演じるうえで、大事にしたことを教えてください。
今回、殺し屋の映画を撮ることになったけど、“殺し屋映画”をやりたいと思っていたわけじゃないんだ。というのも、すでに他の人たちが撮っているし、それ以上のものは撮れないと思っていたからね。でもこの脚本は違った。殺し屋という仕事はノックスにとってただの生業にすぎず、映画の中心は人間関係になっている。疎遠になった息子(ジェームズ・マースデン)や前妻(マーシャ・ゲイ・ハーデン)、そして良き友人でありメンターでもあるゼイヴィア(アル・パチーノ)とのね。
劇中でノックスは16年ぶりに息子と再会するが、病が急速に進行していると聞かされたばかりで、残された時間はわずかしかない。それでも行動するのは、和解のためだけでなく、息子を守るためなんだ。そこにドラマがあると思うよ。
――アル・パチーノとの初共演や、ほかのキャストとの関わりはいかがでしたか?
自分の“役者談義”はあまり面白くないと思っている。演技論を語ることが好きじゃないんだ。そういうことを話している自分の声を聞くのが好きではない。でも、他の俳優には興味がある。アル(・パチーノ)とは電話で話し始めたのが最初だった。登場人物についてあれこれと話したが、驚くほど気楽で気取らない会話だった。映画作りについての堅苦しい話はなく、自然だったんだ。
他のキャストも本当に素晴らしかった。マーシャ・ゲイ・ハーデンは、演じる上で行き詰まったときに、「ああ、あの人に頼めばなんとかしてくれる」と思える存在だ。「このシーンは無理だな」って思っても、彼女が演じると結局上手くいってしまうんだよ。
ジェームズ・マースデンに関しては、今回きっと度肝を抜かれると思うよ。素晴らしい演技だったし、彼は本当にいい奴なんだ。私との仕事のせいで彼が悪い影響を受けていないといいけど(笑)。
刑事役を演じたスージー・ナカムラは、出演作を何本か見たことがあって、いつも笑わされていた。この役にはコメディの経験がある人がほしいと思っていたのでピッタリだったね。面白い人というのは、ある種の知性を持っていて、こちらが予想しないことをしてくれる。皮肉屋で、自然体なのに笑える。男を怖がらず、自分を貫く女性。そんなイメージの役だったね。
――監督として現場に立ったとき、どんな挑戦がありましたか?
私はバカ正直なんだ。だから、撮影がタイトでリソースが限られていることを最初から関係者全員に伝えたよ。リハーサルの時間が無く、急遽撮影に入るしかなかった。予算も限られていて、撮影も25日間しかなかった。慌ただしく準備を進め、誰が空いているか確認し、すべてが上手くいくよう祈るしかなかった。制作過程は、本当に複雑でね。だから私は今回の映画を「ジェンガ・ムービー」と呼んでいたんだ。一部でも欠けたら、ストーリーは崩壊してしまうからね。
それでも、監督と主演と製作を兼ねることで、効率的に動ける部分もあったよ。自分のキャラクターを理解しているから、より早く動けるし、自分自身と議論する必要はないからね。ただ反省点は、自分自身に十分時間をかけられていなかったこと。他の俳優のときは、ちゃんと芝居を見て細かく目を配るのに、カメラが私の方を向いているときは、ちらっとモニターを見て「大丈夫」と言うだけだった。そこは気をつけなくちゃいけなかったね。
――監督・俳優・製作として参加した本作を振り返って、どのように感じていますか?
撮影については、ロケ地がLAということが、まず嬉しかったね。バレーの外れに「ここ誰が住んでるんだ?」って感じの場所があるだろう。昼間の2時にそういう寂れたモールを見てると不思議な気分になるんだ。あれがいいんだよ。
やっぱり物語を語るという行為には、ほかに代えがたい魅力がある。映像でしか伝えられないことや、言葉にせずとも伝わるものがある。そこが一番好きな部分だね。そして何より誇りに思っているのは、登場人物たちに命を吹き込んでくれた素晴らしい俳優たちの存在だ。彼らと一緒に仕事ができたことを、心から光栄に思っている。
【作品情報】
・ 殺し屋のプロット
【関連記事】
・ 【動画】「殺し屋のプロット」予告編
・ マイケル・キートン監督・主演・製作×アル・パチーノ共演「殺し屋のプロット」12月5日公開決定!
・ コッポラがAFI生涯功労賞を受賞盟友スピルバーグとルーカスが祝福
(C) 2023 HIDDEN HILL LLC. ALL RIGHTS RESERVED.