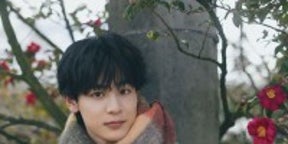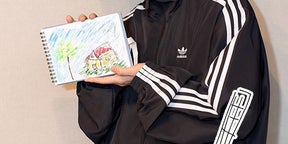子ども2人の入学時期が重なり「学費赤字」になりそう…!学費は年収の何割あるべき?
4月2日(水) 19:00
年収が低いほど重い教育費負担
株式会社日本政策金融公庫が公表した令和3年度「教育費負担の実態調査結果」によると、世帯年収に占める在学費用(子ども全員にかかる費用の合計)の割合は、平均で14.9%となっています。また、年収ごとの教育費負担の割合は表1の通りです。
表1
| 世帯年収 | 在学費用の割合 |
|---|---|
| 200万円以上400万円未満 | 26.7% |
| 400万円以上600万円未満 | 21.1% |
| 600万円以上800万円未満 | 15.5% |
| 800万円以上 | 11.6% |
出典:株式会社日本政策金融公庫「子ども1人当たりにかける教育費用(高校入学から大学卒業まで)は減少~令和3年度『教育費負担の実態調査結果』~」を基に筆者作成
この結果から、世帯年収が低いほど、収入に対する教育費の負担割合が高くなる傾向にあることが分かります。
子どもの学年が上がるほど教育費負担は増加傾向
ソニー生命保険株式会社は、大学生以下の子どもがいる20歳以上の男女に対し「子どもの教育資金に関する調査」をインターネットリサーチで実施しました。子どもの教育費負担調査結果は表2の通りです。
表2
| 就学段階 | 教育費の負担を重いと感じる割合 |
|---|---|
| 未就学児 | 56.5% |
| 小学生 | 58.1% |
| 中高生 | 71.4% |
| 大学生等 | 81.3% |
出典:ソニー生命保険株式会社「子どもの教育資金に関する調査2023」を基に筆者作成
学年が上がるにつれて、教育費に対する負担が増していることが分かります。また、「子どもの受験や進学に対して不安を感じるか」という質問では、中高生の親の8割以上が「不安がある」と回答しています。
3歳差違いの子ども2人が進学する場合
3歳差の子ども2人が、公立の中学校・高校、国立大学へ進学する場合の年間学費は、表3の通りです。
表3
| 1子 | 高1 | 高2 | 高3 | 大1 | 大2 | 大3 | 大4 |
| 2子 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | 大1 |
| 合計学費 | 約116万円 | 約90万円 | 約110万円 | 約145万円 | 約99万円 | 約99万円 | 約107万円 |
出典:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」と「令和3年度子供の学習費調査」を基に筆者作成
高校や大学の進学が重なれば、学費の負担が大きくなることが分かります。なお、1人目が大学1年生、2人目が高校1年生になる年(約145万円)が最も高額です。それ以降も年間100万円前後の学費負担が続くため、計画的な資金の準備が必要です。
教育費のねん出方法
子どもの教育費を確保するには、多額の資金が必要です。各家庭はどのようにして教育費をねん出しているのでしょうか。株式会社日本政策金融公庫の同資料によると、表4の通りです。
表4
| 対応方法 | 割合 |
|---|---|
| 教育費以外の支出を削っている | 28.6% |
| 子ども(在学者本人)がアルバイトをしている | 21.5% |
| 奨学金を受けている | 19.2% |
| 預貯金や保険などを取り崩している | 18.8% |
出典:株式会社日本政策金融公庫「子ども1人当たりにかける教育費用(高校入学から大学卒業まで)は減少~令和3年度『教育費負担の実態調査結果』~」を基に筆者作成
教育費をねん出するために、家計のやりくりを工夫したり、子どもがアルバイトをしたりしているようです。
教育費のピークに備える! 家計負担を軽減するための対策
子どもが高校や大学に進学する時期には教育費がかさむでしょう。家計への負担が一気に増すため、経済的に厳しくなる家庭も少なくありません。貯蓄が底をついてしまわないよう、計画的な準備が求められます。
早めに家計を見直したり、教育資金を確保したりすることが大切です。また、必要に応じて奨学金や教育ローンを活用するなど、事前に対策を講じておくことが重要です。
奨学金は計画的に利用を
大学進学にかかる費用が不足する場合には、奨学金を活用できます。多くの学生が利用する独立行政法人日本学生支援機構の奨学金には、「給付型」「貸与型第1種(無利子)」「貸与型第2種(有利子)」の3種類があります。
給付型は親の収入基準が厳しく、第1種には収入基準に加えて学力基準も設けられているため、比較的利用しやすいのは第2種の貸与型奨学金でしょう。
申し込みは高校3年生の春に行われる説明会のあとから可能で、志望校や必要な金額が決まっていなくても申し込めます。そのため、早めに手続きを済ませておくと安心です。
ただし、奨学金の振り込みは大学入学後となるため、入学金などの初期費用には使えない点に注意が必要です。また、借り過ぎると卒業後の返済負担が大きくなるため、必要な額を慎重に検討しましょう。
世帯年収に占める在学費用の割合は平均14.9%
株式会社日本政策金融公庫の調査によると、世帯年収に占める在学費用の割合は平均14.9%とされています。ただし、年収によって負担の重さは異なります。年収が低いほど教育費の負担が重くなる傾向があるため、子ども2人が同時に進学する場合は特に注意が必要です。
また、ソニー生命保険株式会社の調査では、子どもの成長とともに教育費の負担が増すことも明らかになっています。2人の子どもの年齢が3歳差であれば、高校と大学の入学が重なることが考えられます。
大学進学時には子どもの学費がピークを迎えるため、貯蓄や奨学金、教育ローンなどの活用も視野に入れながら、計画的に準備を進めることが大切です。
出典
株式会社日本政策金融公庫子供1人当たりにかける教育費用(高校入学から大学卒業まで)は減少~令和3年度「教育費負担の実態調査結果」~(8、12ページ)
ソニー生命保険株式会社子どもの教育資金に関する調査2023
文部科学省
国公私立大学の授業料等の推移
令和3年度子供の学習費調査2.調査結果の概要(3)学年別
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
年収1000万円と世帯年収1000万円では税負担がこんなに違う。いったいなぜ?2020年4月から始まる「大学無償化」対象になる世帯の年収基準はいくら?
子どもを育てるにはいくらの年収があれば「安心」?子育て世帯の「平均年収」はどのくらい?

新着ニュース
合わせて読みたい記事
編集部のおすすめ記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55