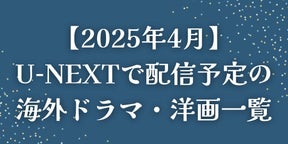「退職金」の平均額ってどのくらい?「1000万円」貰える人はどのくらいいる?
2月21日(金) 1:50
退職金制度とは
退職金制度とは、一定期間以上勤務した従業員に対し、勤続年数や在職中の業績に応じて支給される制度です。支給開始の条件や計算方法は企業ごとに異なり、統一された基準は存在しません。
退職給付制度を導入している企業
令和4年の1年間で、退職金や年金などの退職給付制度を導入している企業は全体の74.9%となりました。また、勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業に限定すると、退職給付制度を設けている企業の割合は29.2%となっています。
これらの企業における退職者の理由を見ると、「定年退職」が最も多く、全体の56.5%を占めています。一方で、「会社都合による退職」は6.1%、「自己都合による退職」は31.7%、「早期退職制度を利用した退職」は5.7%です。
令和4年度 退職金の平均支給額
厚生労働省(中央労働委員会)「令和5年退職金、年金及び定年制事情調査」によると令和4年度 退職金の平均支給額は表1の通りです。
表1
| 退職事由 | 産業全体(万円) | 製造業(万円) |
|---|---|---|
| 定年退職 | 1878.3 | 1843.3 |
| 会社都合 | 1399.9 | 1154.3 |
| 自己都合 | 487.5 | 481.2 |
出典:厚生労働省(中央労働委員会)「令和5年退職金、年金及び定年制事情調査」令和4年度 退職金の平均支給額を基に筆者作成
男性定年退職者の退職金支給額(学歴・勤続年数別)
令和4年度における男性定年退職者の退職金支給額は、学歴や勤続年数によって異なります。調査対象となった産業全体および製造業の平均額は表2の通りです。
表2
| 学歴 | 勤続年数 | 産業全体(万円) | 製造業(万円) |
|---|---|---|---|
| 大学卒 | 35年 | 1867.6 | 1841.0 |
| 大学卒 | 満期勤続 | 2139.6 | 2105.5 |
| 高校卒 | 35年 | 1319.8 | 1283.2 |
| 高校卒 | 満期勤続 | 2019.9 | 1941.5 |
出典:厚生労働省(中央労働委員会)「令和5年退職金、年金及び定年制事情調査」勤続年数、学歴別定年退職者の平均退職金額(男性)を基に筆者作成
厚生労働省の調査結果を基に、「1000万円以上の退職金を受け取れる人」がどの程度いるのかを考察
厚生労働省の調査結果をもとに、1000万円以上の退職金を受け取れる人の割合について考察します。
令和4年度のデータを見ると、退職金の平均額は定年退職者で1878.3万円(産業全体)となっており、1000万円を超える水準です。製造業に限っても1843.3万円となっており、大半の定年退職者が1000万円以上を受け取る可能性が高いといえます。
会社都合退職者の場合も、産業全体の平均は1399.9万円となっていることから、多くの人が1000万円以上の退職金を受け取ると考えられます。
一方、自己都合退職では産業全体の平均が487.5万円、製造業では481.2万円と、1000万円には遠く及びません。自己都合退職では、1000万円以上の退職金を得ることは難しいといえます。
学歴や勤続年数別にみると、大学卒・高校卒ともに満期勤続の場合、退職金は2000万円前後に達しているため、この層も1000万円以上を受け取る可能性が高いでしょう。また、高校卒で35年勤続した場合でも、産業全体で1319.8万円となっており、1000万円を超える水準です。
ただし、勤続年数が20年以下の場合は、1000万円には届かない可能性が高いでしょう。以上のことから、定年退職者や長期勤続者の大半は1000万円以上の退職金を受け取る傾向があるといえます。
一方で、自己都合退職者や勤続年数が短い場合は1000万円に達するのは困難です。したがって、1000万円以上の退職金を得る層は比較的多いものの、勤続年数や退職理由によって大きく異なることがわかります。
厚生労働省令和4年の調査では退職金の平均額1878.3万円
厚生労働省令和4年の調査では退職金の平均額1878.3万円でした。
令和4年の調査では、退職給付制度を導入している企業は74.9%、勤続20年以上・45歳以上の退職者がいる企業では29.2%にとどまります。
一方で、自己都合退職や勤続年数が短い場合は1000万円に達しにくいです。退職理由や勤続年数によって大きく異なりますが、長期勤続すれば1000万円以上を受け取る可能性は高いでしょう。
出典
厚生労働省令和5年就労条件総合調査結果の概況退職給付(一時金・年金)の支給実態
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
退職金を受け取った翌年、住民税がとんでもないことに…。事前にできる対策って?退職するなら65歳よりも、64歳と11ヶ月のほうがお得? いったいどういうこと?
59歳で貯蓄は「2500万」です。60歳でリタイアしても暮らしていけますか?

新着ニュース
合わせて読みたい記事
エンタメ アクセスランキング
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55