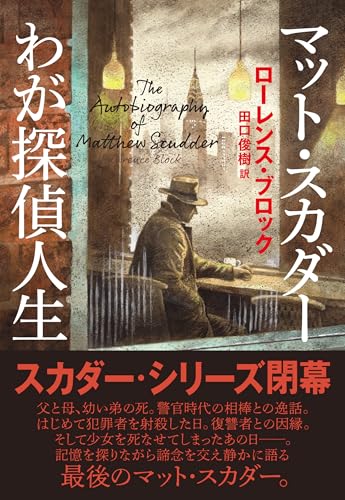
『マット・スカダー わが探偵人生』ローレンス・ブロック,田口俊樹二見書房
【今週はこれを読め! ミステリー編】シリーズ掉尾を飾る自叙伝小説〜ローレンス・ブロック『マット・スカダーわが探偵人生』
12月4日(水) 16:53
犯罪小説史上、極めて重要な意味を持つ一冊となった。
ローレンス・ブロック『マット・スカダーわが探偵人生』(田口俊樹訳。二見書房)は不思議な本である。ニューヨーク派を代表する犯罪小説作家であるローレンス・ブロックは、長い下積み時代を送ったのち、1976年に元警察官でライセンスを持たない私立探偵のマット・スカダーが登場する長篇第一作『過去からの弔鐘』(二見文庫)を上梓した。同作に始まるシリーズは第五長篇『八百万の死にざま』(ハヤカワ・ミステリ文庫)が映画化されたこともあって広範な読者層を獲得し、ブロックの看板作品となる。ブロックは1977年の『泥棒は選べない』(ハヤカワ・ミステリ文庫)に始まる泥棒バーニイ・ローデンバー・シリーズが好調で人気作家の仲間入りを果たしていたのだが、『八百万の死にざま』でその地位を確固たるものにしたのである。
そのマット・スカダーは『八百万の死にざま』で自身がアルコール依存症であることを告白し、以降断酒するようになる。日本には依存症の面を押し出した作品が先に紹介されたこともあり、この変化がシリーズの味を損なうのではないかと危惧する声も上がったが、まったくの杞憂であり、後述するように現代を代表する一人称私立探偵小説の連作になっていく。以来このシリーズは現在までに17作の長篇と1冊の短篇集が刊行されており、ファンは長い年月をスカダーと共に生きてきたのである。
『マット・スカダーわが探偵人生』が第18長篇ということになる。おそらく掉尾を飾る一冊となるだろう。題名が物語るように、これは作中人物であるマット・スカダーが自身の生涯を顧みることを思い立ち、パソコンのwordに打ち込んだ自叙伝という体裁の物語なのである。不思議な本と書いたのはそこで、作中人物による自叙伝の例は、少なくとも一冊にまとまるような分量のものは思い出せない。ローレンス・ブロックによる序文はついているものの、作者は一歩引いた立場をとっている。どうやらスカダーは途中原稿をブロックに送っているらしく、時折苦情が入ったり、注文がつけられたりする。
本書によればスカダーは「一九三八年九月七日生まれの乙女座」で、「チャールズ・ルイス・スカダーとクローディア・コリンズ・スカダーの第一子として、グランドコンコースのブロンクス産婦人科病院で生まれた」のだという。序盤で大事な情報は、彼に一九四一年十二月四日生まれのジョゼフ・ジェレマイア・スカダーという弟がいたが、日本が真珠湾攻撃をした二日後の十二月九日に亡くなったということである。この死がスカダー家に暗い翳を落とし、心を変えてしまった可能性があるとスカダーは書く。これを読んでブロックは悲鳴を上げる。弟がいるなんて言わなかったじゃないか、と。このやりとりでまず笑うのである。
『わが探偵人生』と言うものの、内容はスカダーの前半生、つまりニューヨーク市警に奉職し、そこを辞めるまでの年月に限定されている。逆に言えば、そこでの体験が私立探偵マット・スカダーを形成したということでもある。
スカダーが警察官を辞めた理由についてはシリーズでもたびたび言及されてきた。強盗に向けて撃った銃弾がエストレリータ・リベラを殺してしまったのである。職務責任は問われなかったが、スカダーはバッジと拳銃を返還した。家族との関係もとうに破綻しており、そこから一回彼はどん底まで沈んでいく。アルコール依存症であることを言語化したのはいわゆる底打ちである。この堕落と再生の物語は、先輩作家であるドナルド・E・ウェストレイクがタッカー・コウ名義で表した元刑事ミッチ・トビン・シリーズから影響を受けているのではないかと思っていた時期があるのだが、定かではない。もし機会があれば、ハヤカワ・ミステリから出ている『刑事くずれ』に始まる諸作を読んでみていただきたい。
作中で重要な役割を演じるキャラクターは、警察官時代の先輩で、長くコンビを組んだヴィンス・マハフィである。マハフィは新米だったスカダーに交通法規違反を見逃す代わりに賄賂をとる現場を見せ、分け前を渡すという形で彼を試す。スカダーはそれを受け取るのである。軽犯罪を一つずつ取り締まれば厳格に法を守れるかもしれないが、それぞれの仕事は増える。だったら潤滑剤を投入したほうが丸く収まることもある、というわけである。
そこに白黒をつけるのではなくスカダーは、誰もがすべきこと、できるだけのことをしていたのだ、と考える。ここが非常に重要である。人間は有限の存在で、自分の見える位置の、手の届くことができるだけだ、という認識があるからである。スカダーはそうした立場に自分を置き、手の届く範囲で不公平を是正してきた探偵だ。決して等身大よりも高い位置から人間を見ようとしない。自分の目で見える高さに社会を見るための窓を設け、そこから得られたことで意志を決めてきた。一人称私立探偵小説で最も大事なものはこの、社会を見るための等身大の視点である。それがどういうものかを一冊の分量で書いたのが本書なのだ。
警察官として初めて射殺したルーフ・タガートという男について、スカダーは述懐する。
──タガートにしても自らできるだけのことをしていたのだろう。生まれながらにしろ、幼少期の育ち方にしろ、それらが彼の非人間性を増幅したのだろう。彼は彼で配られたカードで勝負していたのだろう。
──そう、私と同じように。
マハフィともう一人重要な登場人物がいる。1990年の『墓場への切符』(二見文庫)に登場するジェイムズ・レオ・モットリーだ。彼は偏執的な憎悪を燃やす犯罪者で、スカダーに復讐するために複数の人間を殺害している。『墓場への切符』は彼との死闘を描く物語であり、スカダーはここで大きく法を踏み外す形で自身の正義を貫徹している。それまでの作品でもたびたび示されてきた、等身大の法の守護者としての顔が明確になった記念すべき作品である。余談ながらモットリーとの闘いは、現夫人であるエレイン・マーデルとスカダーを結び付けることにもなった。
モットリーに代表される、自らが対峙することになった悪の存在に対し、スカダーは不作為の罪について考える。あのとき自分が手を下していれば、救われた命があったかもしれないのに、と。ここにマット・スカダー・サーガの特徴が表れている。犯罪は社会がそうあったがために必然的に生み出される歪みのようなものとして作品の中ではとらえられる。スカダーはその歪みを是正するための小さな機会を与えられた存在なのだ。その位置にたまたま立った者がどうすべきかを彼は半世紀以上にわたってずっと考えてきた。
『マット・スカダーわが探偵人生』は自叙伝小説としておもしろい読物である。執筆に当たってスカダーは逡巡し、時には書いたパラグラフをすべて削除した、と告白することもある。そうしたモノローグを読む楽しみが本書第一の魅力である。その中で犯罪とは何かということへの考察がずっと重ねられていく。スカダーによる、そして彼の記録者であったブロックによる、壮大な答え合わせの物語なのである。犯罪小説に少しでも関心のある方は、ぜひお読みいただきたいと思う。スカダー・シリーズは未読でも。もし気に入ったら、どの長篇でもいいから戻って読んでみるといいのだ。きっとスカダーを気に入る。
(杉江松恋)
『マット・スカダー わが探偵人生』
著者:ローレンス・ブロック,田口俊樹
出版社:二見書房
>>Amazonで見る
【関連記事】
・ 【今週はこれを読め! ミステリー編】夜を描く落語ミステリー〜愛川晶『モウ半分、クダサイ』
・ 【今週はこれを読め! ミステリー編】「えっ」と驚くジェローム・ルブリ『魔女の檻』がおもしろい!
・ 【今週はこれを読め! ミステリー編】想像を超えた展開になだれ込む〜ジャン=クリストフ・グランジェ『ミゼレーレ』
