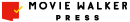大森時生×酒井善三「フィクショナル」、作品に込めたテーマとは?
闇バイト、BL、ディープフェイク…大森時生が放つ「フィクショナル」、酒井善三監督が明かした黒沢清への憧憬
11月18日(月) 19:30
この夏に約7万人が足を運んだ展覧会「行方不明展」や「TXQ FICTION /イシナガキクエを探しています」などを手掛けた“フェイク・ドキュメンタリー”ブームの立役者、大森時生がプロデュースを務めたドラマ作品「フィクショナル」が、シモキタ - エキマエ - シネマ K2ほかにて劇場公開中。
【写真を見る】プロパガンダとフィルムノワール、そしてエロティシズムが融合…ミステリアスなドラマはこうして生まれた
1話3分以内のショートドラマを配信するアプリ「BUMP」で30話に分割された状態で配信が行われた本作だが、メガホンをとった酒井善三監督が「初めから一本の作品として作っています」と語るように、今回上映されるひとつなぎの状態こそが、制作者の意図したものなのだという。PRESS HORRORでは酒井監督を直撃し、ミステリアスな作品に込めた想いを尋ねた。
■「『SIX HACK』でやりきれなかったことを全部詰め込んだ」
物語はうだつの上がらない映像制作業者の神保(清水尚弥)が、大学時代の先輩である及川(木村文)から連絡を受けて彼の元へ向かうところから始まる。及川に特別な感情を抱いていた神保は彼と一緒に仕事ができることに気分が湧き立つのだが、その仕事は怪しい“闇バイト”で、ディープフェイク映像の下請けだった。やがて迫り来る自身の“仕事”の影響と責任に押しつぶされていく神保は、徐々にリアルとフェイクの境目へと堕ちていくこととなる。

酒井監督が大森とタッグを組むのは、2023年に放送されたフェイクバラエティ番組「SIX HACK」以来。同番組は“偉くなるためのハックをお伝えする”という趣旨でスタジオトークが繰り広げられる、一見普通のトークバラエティ番組。しかし徐々に陰謀論と不可解な洗脳映像に侵食されていき、全6回の予定が3回で打ち切り、第4回では再現映像を用いた検証ドラマが展開するという視聴者を巻き込んだ斬新な構成で、さまざまな憶測を生むなど話題を集めた。
「前々から、大森さんとは『ドラマをやりたい』と話をしていましたが、ついに実現しました」と語る酒井監督は、「僕にとって『フィクショナル』は、『SIX HACK』の時にやりきれなかったことを全部詰め込んだ、ある意味で“弔い合戦”のような作品でもあります」と並々ならぬ思いを明かす。常に新しいタイプの“フェイク・ドキュメンタリー”を生みだし続ける大森のもとで、あえて“フェイク”を作る者たちの物語を描く。この挑戦的な企画を「絶対にやりたい」とアピールしたところ、大森からは二つ返事でゴーサインが出たのだとか。

作品の題材である“ディープフェイク”は、他者への攻撃を意図し、AI技術を用いて写真や動画、音声などを改竄する行為のこと。自ら脚本も手掛けた酒井監督は、本作の企画が動きだした昨年10月から現在もなお続いているパレスチナとイスラエルの紛争が、本作のアイデアの原点であることを明かす。
「パレスチナ問題はこれまでもずっとありましたが、なかなか外目に触れる機会はありませんでした。ところが、いざこのようなかたちで僕のような人間や世界中に知られても、まったく事態は変わらない。そのことに大きなショックを受けたんです。同時に無数のプロパガンダ映像が出回り、どの情報が正しいのかすら不透明な状態に陥ってしまった。インターネットの普及ですべてが明らかになるはずの時代でもこういうことが起きてしまう。それを作る側の視点で描いたらどうなるのか。そう考えたことが始まりでした」。

ディープフェイクとして悪用されるケースに限らず、急速に進歩をつづけるAI技術はいま、映画やドラマなどのパブリックなメディアにも取り入れられつつある。そうしたなかアメリカでは、昨年の俳優組合によるストライキでも俳優たちの権利が保障されるよう求めたり、日本でも有志の声優たちが音声の無断生成に異議を唱える運動を開始するなど、業界全体の将来に向けた喫緊の課題の一つともなっている。
「発明された以上は、使われることを避ける方法はない。でもある程度でも使わざるを得なくなっていくとなれば、映像を作ること自体の概念が変わってくるように感じています」。酒井監督は、映像制作に従事する者の一人として懸念を示す。「ですが、AIで血の通ったおもしろい作品ができるとも言いがたい。誰が作っているのか、そもそも作り手は存在するのかすら怪しくなってくるとなると、それはとても恐ろしいことではないでしょうか」。
■「“水滴”を口に含むことで、満たされない欲求を表現した」
本作はディープフェイクの脅威を描くスリラー的側面と同時に、主人公の神保が先輩である及川に対して淡い感情を抱いている、いわば“BL(=ボーイズラブ)ドラマ”としての側面も有している。

しかしながら、“BLドラマ”としてプロモーションがされると決まったのは、撮影が終了する直前のことだったという。「大森さんから内容に関しては一任されていたので、僕も作品の売り出しかたについてはすべてお任せすることにしました」と、大森へ厚い信頼を寄せる酒井監督。「当初からボーイズラブとしての要素は含まれていましたので、あらためてシナリオや演出を変える必要もありませんでしたから」。
先述のようにディープフェイクと、それを作りだす者によるサイコスリラーを描くにあたり、酒井監督のなかでは「男性を通して、エロティシズムを表現する」というヴィジョンが最初から存在していたという。「官能的でエロティックなもの。抗いがたい欲求をどのように描いていくか。エロティックという言葉を聞くと、裸体を見せたり触れ合ったりするイメージが持たれがちですが、可視化された露骨な表現はちっともエロティックではない。映像という見えるものだからこそ、エロティシズムは秘められたものであるべきだと感じていました」。

その言葉通り、劇中には神保から及川に向けられた好意を直接的に示す描写やセリフは存在せず、ただ両者のあいだにただよう空気感のみをもって、その秘められた感情が表現されていく。視線やごくわずかな所作。とりわけBUMPでの配信公開時に視聴者から大きな反響を集めていたのは、物語の序盤、及川の部屋で作業をしている神保が、及川から受け取ったコップから零れた水滴を舐めとるしぐさである。
「脚本の段階からすでにあったシーンです。リアリズムで言うと、『乾杯する時に手をあげたら水滴が落ちるのでは?』というところですが、そこは映画ならではの嘘っぱち、ご愛嬌です(笑)」と、反響の大きさに照れくさそうな表情を浮かべる酒井監督。「あのシーンで意図していたのは、2人の“再会の印”のようなものです。回想シーンが挟まれ、神保がそれを思い出しながら及川から受け取った水滴を口に含むことで、彼の満たされない欲求を表現しようと考えました」。

そのうえでヒントとなったのは、1940年代から1950年代にかけてハリウッドやフランスの、主に犯罪映画で取り入れられた“フィルムノワール”の様式美だという。「フィルムノワールには往々にして、男性を惑わす“ファム・ファタール”と呼ばれる女性が存在します。そのイメージを男性に置き換えてみたというだけ。男性同士だからこう描こうと決め打ちするのではなく、異性間でも成立するものを性別を変え、あくまでも内在する欲求として描写することに定めたのです」。
そして「“BLドラマ”として、フィルムノワールとして、さまざまな要素を取り入れていますが、そうした枠組みのなかに閉じ込めずにジャンルオーバーなものとして楽しんでいただきたいと思っています。なにもないシーンがないように、さまざまなディテールを入れています。一度観ておもしろいと感じていただけたら、二度目はまた違う視点で楽しんでもらえたらうれしいですね」と期待を寄せた。

■「僕らの世代で、黒沢さんから影響を受けていない人はいない」
多くの名だたる映画人を輩出してきた映画美学校を経て、2021年に発表した中編『カウンセラー』が「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭」の国内コンペティション部門SKIPシティアワードに輝いた酒井監督。今回『フィクショナル』の劇場公開にあわせ、『カウンセラー』のリバイバル上映も決定している。

心理カウンセラーの主人公の倉田のもとに、予約なしで相談に訪れた一人の女性。「妖怪が見えるんです」という彼女が語る暗い物語に翻弄され、次第に不安の渦へと堕ちていくさまを描いた『カウンセラー』は、『Cloud クラウド』(公開中)などで知られる黒沢清監督が「近年もっとも不気味な映画といってもいいだろう」と熱烈な賛辞を送った一本。さらに黒沢監督は、今年8月に公開された中編『Chime』(公開中)を手掛けるにあたり、『カウンセラー』から影響を受けたことも明かしている。
「黒沢さんが僕の作品から影響を受けるなんて…そんなことが生きていて本当に起こりうるのかと思うくらい、本当に畏れ多い話です」と恐縮しっぱなしの酒井監督。「僕らの世代の演出家で、黒沢さんから影響を受けていない人はいないと思います」と語るように、酒井監督自身も以前から黒沢監督の作品群から多大な影響を受けてきたと明かす。
「実は『フィクショナル』には『Cloud クラウド』に参加していたスタッフさんが何人もいて、完成したあとになって『似てるよね』と指摘されて途方に暮れていました…。もっと早く言ってくれよと。でも、知らず知らずのうちに寄っていってしまうというのは、それだけ僕が黒沢さんから影響を受けているということなんだと思います」。
黒沢監督が1990年代に手掛けたVシネマの「勝手にしやがれ!!」シリーズをはじめ、「観られる作品は全部鑑賞しています」と豪語する酒井監督は、あらためて黒沢監督への強い憧れを語る。「娯楽映画、つまり様々なジャンル映画として、独特な作家性を求められるような立場になってからも、アートな方向、個性への評価に止まることをせずに、常に自分のなかでのおもしろさを実験していく、エンタテイナーであり続ける姿勢を尊敬しています」。
そして「黒沢さんはそれでも強烈な作家性を出せる人ですが、僕には個性らしい個性がない。だからこそ、誰が観てもおもしろいと思えるもの、娯楽性の強い作品に積極的に取り組んでいきたいと考えています」と、映像作家としてのさらなる飛躍を誓った。

取材・文/久保田和馬
【関連記事】
・ 「レジェンドホラー映画祭」を独占レポート!大森時生・梨・近藤亮太が集結、清水崇は“恐怖の原点”を語る
・ 大森時生が考える、“ファウンド・フッテージ”の未来予想図。「このテープ」「行方不明展」から『悪魔と夜ふかし』へ
・ 「イシナガキクエ」大森時生が『悪魔と夜ふかし』試写会に登壇!「新しいファウンド・フッテージ作品になっています」
・ 「行方不明展」潜入レポート。「怪文書展」「イシナガキクエ」の仕掛け人らが放つ展覧会の“手ざわり”
・ 「イシナガキクエを実体化する実験のようだった」考察を生んだ“正体”は? 大森時生×近藤亮太が明かす「TXQ FICTION」の舞台裏
【写真を見る】プロパガンダとフィルムノワール、そしてエロティシズムが融合…ミステリアスなドラマはこうして生まれた
1話3分以内のショートドラマを配信するアプリ「BUMP」で30話に分割された状態で配信が行われた本作だが、メガホンをとった酒井善三監督が「初めから一本の作品として作っています」と語るように、今回上映されるひとつなぎの状態こそが、制作者の意図したものなのだという。PRESS HORRORでは酒井監督を直撃し、ミステリアスな作品に込めた想いを尋ねた。
■「『SIX HACK』でやりきれなかったことを全部詰め込んだ」
物語はうだつの上がらない映像制作業者の神保(清水尚弥)が、大学時代の先輩である及川(木村文)から連絡を受けて彼の元へ向かうところから始まる。及川に特別な感情を抱いていた神保は彼と一緒に仕事ができることに気分が湧き立つのだが、その仕事は怪しい“闇バイト”で、ディープフェイク映像の下請けだった。やがて迫り来る自身の“仕事”の影響と責任に押しつぶされていく神保は、徐々にリアルとフェイクの境目へと堕ちていくこととなる。

酒井監督が大森とタッグを組むのは、2023年に放送されたフェイクバラエティ番組「SIX HACK」以来。同番組は“偉くなるためのハックをお伝えする”という趣旨でスタジオトークが繰り広げられる、一見普通のトークバラエティ番組。しかし徐々に陰謀論と不可解な洗脳映像に侵食されていき、全6回の予定が3回で打ち切り、第4回では再現映像を用いた検証ドラマが展開するという視聴者を巻き込んだ斬新な構成で、さまざまな憶測を生むなど話題を集めた。
「前々から、大森さんとは『ドラマをやりたい』と話をしていましたが、ついに実現しました」と語る酒井監督は、「僕にとって『フィクショナル』は、『SIX HACK』の時にやりきれなかったことを全部詰め込んだ、ある意味で“弔い合戦”のような作品でもあります」と並々ならぬ思いを明かす。常に新しいタイプの“フェイク・ドキュメンタリー”を生みだし続ける大森のもとで、あえて“フェイク”を作る者たちの物語を描く。この挑戦的な企画を「絶対にやりたい」とアピールしたところ、大森からは二つ返事でゴーサインが出たのだとか。

作品の題材である“ディープフェイク”は、他者への攻撃を意図し、AI技術を用いて写真や動画、音声などを改竄する行為のこと。自ら脚本も手掛けた酒井監督は、本作の企画が動きだした昨年10月から現在もなお続いているパレスチナとイスラエルの紛争が、本作のアイデアの原点であることを明かす。
「パレスチナ問題はこれまでもずっとありましたが、なかなか外目に触れる機会はありませんでした。ところが、いざこのようなかたちで僕のような人間や世界中に知られても、まったく事態は変わらない。そのことに大きなショックを受けたんです。同時に無数のプロパガンダ映像が出回り、どの情報が正しいのかすら不透明な状態に陥ってしまった。インターネットの普及ですべてが明らかになるはずの時代でもこういうことが起きてしまう。それを作る側の視点で描いたらどうなるのか。そう考えたことが始まりでした」。

ディープフェイクとして悪用されるケースに限らず、急速に進歩をつづけるAI技術はいま、映画やドラマなどのパブリックなメディアにも取り入れられつつある。そうしたなかアメリカでは、昨年の俳優組合によるストライキでも俳優たちの権利が保障されるよう求めたり、日本でも有志の声優たちが音声の無断生成に異議を唱える運動を開始するなど、業界全体の将来に向けた喫緊の課題の一つともなっている。
「発明された以上は、使われることを避ける方法はない。でもある程度でも使わざるを得なくなっていくとなれば、映像を作ること自体の概念が変わってくるように感じています」。酒井監督は、映像制作に従事する者の一人として懸念を示す。「ですが、AIで血の通ったおもしろい作品ができるとも言いがたい。誰が作っているのか、そもそも作り手は存在するのかすら怪しくなってくるとなると、それはとても恐ろしいことではないでしょうか」。
■「“水滴”を口に含むことで、満たされない欲求を表現した」
本作はディープフェイクの脅威を描くスリラー的側面と同時に、主人公の神保が先輩である及川に対して淡い感情を抱いている、いわば“BL(=ボーイズラブ)ドラマ”としての側面も有している。

しかしながら、“BLドラマ”としてプロモーションがされると決まったのは、撮影が終了する直前のことだったという。「大森さんから内容に関しては一任されていたので、僕も作品の売り出しかたについてはすべてお任せすることにしました」と、大森へ厚い信頼を寄せる酒井監督。「当初からボーイズラブとしての要素は含まれていましたので、あらためてシナリオや演出を変える必要もありませんでしたから」。
先述のようにディープフェイクと、それを作りだす者によるサイコスリラーを描くにあたり、酒井監督のなかでは「男性を通して、エロティシズムを表現する」というヴィジョンが最初から存在していたという。「官能的でエロティックなもの。抗いがたい欲求をどのように描いていくか。エロティックという言葉を聞くと、裸体を見せたり触れ合ったりするイメージが持たれがちですが、可視化された露骨な表現はちっともエロティックではない。映像という見えるものだからこそ、エロティシズムは秘められたものであるべきだと感じていました」。

その言葉通り、劇中には神保から及川に向けられた好意を直接的に示す描写やセリフは存在せず、ただ両者のあいだにただよう空気感のみをもって、その秘められた感情が表現されていく。視線やごくわずかな所作。とりわけBUMPでの配信公開時に視聴者から大きな反響を集めていたのは、物語の序盤、及川の部屋で作業をしている神保が、及川から受け取ったコップから零れた水滴を舐めとるしぐさである。
「脚本の段階からすでにあったシーンです。リアリズムで言うと、『乾杯する時に手をあげたら水滴が落ちるのでは?』というところですが、そこは映画ならではの嘘っぱち、ご愛嬌です(笑)」と、反響の大きさに照れくさそうな表情を浮かべる酒井監督。「あのシーンで意図していたのは、2人の“再会の印”のようなものです。回想シーンが挟まれ、神保がそれを思い出しながら及川から受け取った水滴を口に含むことで、彼の満たされない欲求を表現しようと考えました」。

そのうえでヒントとなったのは、1940年代から1950年代にかけてハリウッドやフランスの、主に犯罪映画で取り入れられた“フィルムノワール”の様式美だという。「フィルムノワールには往々にして、男性を惑わす“ファム・ファタール”と呼ばれる女性が存在します。そのイメージを男性に置き換えてみたというだけ。男性同士だからこう描こうと決め打ちするのではなく、異性間でも成立するものを性別を変え、あくまでも内在する欲求として描写することに定めたのです」。
そして「“BLドラマ”として、フィルムノワールとして、さまざまな要素を取り入れていますが、そうした枠組みのなかに閉じ込めずにジャンルオーバーなものとして楽しんでいただきたいと思っています。なにもないシーンがないように、さまざまなディテールを入れています。一度観ておもしろいと感じていただけたら、二度目はまた違う視点で楽しんでもらえたらうれしいですね」と期待を寄せた。

■「僕らの世代で、黒沢さんから影響を受けていない人はいない」
多くの名だたる映画人を輩出してきた映画美学校を経て、2021年に発表した中編『カウンセラー』が「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭」の国内コンペティション部門SKIPシティアワードに輝いた酒井監督。今回『フィクショナル』の劇場公開にあわせ、『カウンセラー』のリバイバル上映も決定している。

心理カウンセラーの主人公の倉田のもとに、予約なしで相談に訪れた一人の女性。「妖怪が見えるんです」という彼女が語る暗い物語に翻弄され、次第に不安の渦へと堕ちていくさまを描いた『カウンセラー』は、『Cloud クラウド』(公開中)などで知られる黒沢清監督が「近年もっとも不気味な映画といってもいいだろう」と熱烈な賛辞を送った一本。さらに黒沢監督は、今年8月に公開された中編『Chime』(公開中)を手掛けるにあたり、『カウンセラー』から影響を受けたことも明かしている。
「黒沢さんが僕の作品から影響を受けるなんて…そんなことが生きていて本当に起こりうるのかと思うくらい、本当に畏れ多い話です」と恐縮しっぱなしの酒井監督。「僕らの世代の演出家で、黒沢さんから影響を受けていない人はいないと思います」と語るように、酒井監督自身も以前から黒沢監督の作品群から多大な影響を受けてきたと明かす。
「実は『フィクショナル』には『Cloud クラウド』に参加していたスタッフさんが何人もいて、完成したあとになって『似てるよね』と指摘されて途方に暮れていました…。もっと早く言ってくれよと。でも、知らず知らずのうちに寄っていってしまうというのは、それだけ僕が黒沢さんから影響を受けているということなんだと思います」。
黒沢監督が1990年代に手掛けたVシネマの「勝手にしやがれ!!」シリーズをはじめ、「観られる作品は全部鑑賞しています」と豪語する酒井監督は、あらためて黒沢監督への強い憧れを語る。「娯楽映画、つまり様々なジャンル映画として、独特な作家性を求められるような立場になってからも、アートな方向、個性への評価に止まることをせずに、常に自分のなかでのおもしろさを実験していく、エンタテイナーであり続ける姿勢を尊敬しています」。
そして「黒沢さんはそれでも強烈な作家性を出せる人ですが、僕には個性らしい個性がない。だからこそ、誰が観てもおもしろいと思えるもの、娯楽性の強い作品に積極的に取り組んでいきたいと考えています」と、映像作家としてのさらなる飛躍を誓った。

取材・文/久保田和馬
【関連記事】
・ 「レジェンドホラー映画祭」を独占レポート!大森時生・梨・近藤亮太が集結、清水崇は“恐怖の原点”を語る
・ 大森時生が考える、“ファウンド・フッテージ”の未来予想図。「このテープ」「行方不明展」から『悪魔と夜ふかし』へ
・ 「イシナガキクエ」大森時生が『悪魔と夜ふかし』試写会に登壇!「新しいファウンド・フッテージ作品になっています」
・ 「行方不明展」潜入レポート。「怪文書展」「イシナガキクエ」の仕掛け人らが放つ展覧会の“手ざわり”
・ 「イシナガキクエを実体化する実験のようだった」考察を生んだ“正体”は? 大森時生×近藤亮太が明かす「TXQ FICTION」の舞台裏