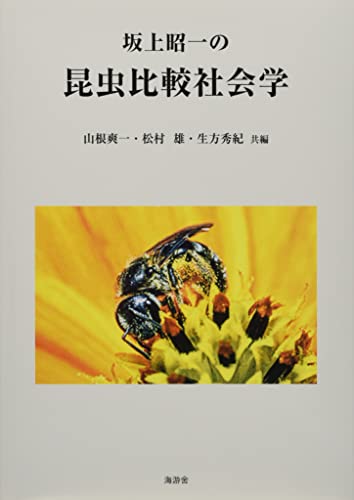
昆虫学者たちが、現在なにを考え、なにをしようとしているかを語る一般向けエッセー集
昆虫学者たちが、現在なにを考え、なにをしようとしているかを語る一般向けエッセー集
5月4日(土) 6:00
提供:
 『坂上昭一の昆虫比較社会学』(海游舎)著者:山根 爽一Amazon |honto |その他の書店
『坂上昭一の昆虫比較社会学』(海游舎)著者:山根 爽一Amazon |honto |その他の書店◆専門学者によるオマージュエッセー集
表題から見ると専門書みたいだが、じつは違う。「坂上昭一の」とついているのは、全体が故坂上昭一へのオマージュだからであって、実際の内容は坂上に縁のあった三十人ほどの昆虫学者たちの坂上への敬意を込めたエッセー集である。
四部構成になっており、第一部は「坂上昭一の生涯と研究業績」、第二部は「進化生物学者から見た坂上昭一」、第三部は「共同研究者と坂上昭一」、第四部は「門下生から見た人間坂上昭一」である。それぞれの文章はさすがに研究者が書いたものだから、簡潔かつ要領よく、文末に参考文献が付けられている。
坂上は北大の昆虫学教室の出身で、ハチの生態を研究した。評者は若い頃に「子孫を伝えない性質を、いかにして子孫に伝えたか」という表題の坂上の論考を岩波書店の『科学』で見て、「そういう問題の立て方もあるか」と一驚した覚えがある。
ハチの巣はほとんど働きバチで占められており、これはメスで、しかも子を産まず、代わりに女王バチの産んだ子、つまり姉妹を育てるということは、ほとんど周知の事実であろう。こうした奇妙な社会が進化の過程でいかにして成立したか、読者はそれに答えられるであろうか。
たとえばミツバチの世界を例に考えてみよう。こうした精緻な社会が成立する以前の状況を考えるには、ミツバチに近縁と思われるハナバチの仲間の生活にヒントが見られるのではないだろうか。
自然淘汰(とうた)説で進化を説明しようとすると、一般の人は適者生存とか、弱肉強食のような個体単位の考え方をすることが多い。ミツバチの社会はそれでは説明ができない。まったく歯が立たないと言ってもいい。
坂上の時代から現在に至るまで、最も有効な仮説は血縁選択説である。これは遺伝子の選択を基本に考えるもので、ついにはドーキンス流の利己的遺伝子の考えにまで行き着くことになる。
坂上の生きた時代は、ファーブルやダーウィンの頃とは違い、生物学に革命的な変化が起きた時代であって、「遺伝子」や「ゲノム」、「DNA」といった、日常言語にはない概念が主流を占めるようになった。それと同時に日本社会でも敗戦により社会的に急激な変化が生じた。坂上より若い世代は、この衝撃が感覚的には理解しがたいであろう。むしろこうした変化を当然のこととして受け止めていると思う。
ファーブルの時代には、自己の観察や思考を日常言語の範囲内で記述できたが、二十世紀中葉にDNAの化学構造が解明されると、元来は実験室内部の作業であった部分の生物学が野外での出来事の解釈に多大の影響を与えることになった。生物学が科学として日常の素朴な世界を離れて独立したと言ってもいい。
ここはその是非を問う場ではない。
本書は坂上に縁のあった専門の昆虫学者たちが、現在なにを考え、なにをしようとしているかを報告したもので、日常なにをしているのか、常人や家族ですら理解しづらい昆虫学者たちが、一般に向けて語りかけたという意味で、稀有(けう)な書物というべきであろう。生物学に関心を持つ読者、教育関係者にお勧めしたいと考える。
【書き手】
養老 孟司
1937(昭和12)年、神奈川県鎌倉市生まれ。1962年東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。1995年東京大学医学部教授を退官し、2017年11月現在東京大学名誉教授。著書に『からだの見方』『形を読む』『唯脳論』『バカの壁』『養老孟司の大言論I〜III』など多数。
【初出メディア】
毎日新聞 2022年8月13日
【書誌情報】
坂上昭一の昆虫比較社会学著者:山根 爽一
編集:山根 爽一,松村 雄,生方 秀紀
出版社:海游舎
装丁:単行本(344ページ)
発売日:2022-04-30
ISBN-10:490593088X
ISBN-13:978-4905930884

