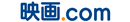那覇・国際通りで開催された恒例のレッドカーペット
沖縄国際映画祭、16回で幕なぜ沖縄の人々の心をつかんだのか振り返る
4月23日(火) 16:00
提供:
「ラフ&ピース(笑いと平和)」を旗印に2009年から16回にわたって行われてきた「沖縄国際映画祭」(2015年からは「島ぜんぶでおーきな祭」との名称を付して開催)は、実行委員会の中核を担っていた吉本興業が今年を最後に離脱を表明。それにともない映画祭実行委員会も解散となることから、今年の4月20、21日に行われた「第16回島ぜんぶでおーきな祭」が最後となる。
・【写真で述懐】安室奈美恵さん、黒木メイサ、阿部寛らも参加した沖縄国際映画祭
“笑い”をテーマに、映画のみならず、音楽、お笑い、ダンス、スポーツなど沖縄全域を網羅して行われる異色の映画祭は、春の風物詩として確かに沖縄に深く根付いていた。特に宜野湾コンベンションセンターをメイン会場としていた初期には10日間にわたり開催されていた時期もあり、最多で45万人近い観客を動員。以前、沖縄国際映画祭を取材していた外国人記者が「世界でも、子どもたちがこんなにも笑っている映画祭を観たことがない」と語るほどに、笑顔にあふれた映画祭だった。だがコロナ禍以降は週末2日間だけの開催となり、徐々に規模が縮小傾向にあったため、今回の離脱表明で決定的なものとなった。
やはり“吉本が手掛ける映画祭”というイメージが先行していたせいか、当初は批判的なコメントもあったようだ。映画祭の顔として尽力してきたガレッジセールのゴリは、「最初は吉本が映画祭をやると言っても、沖縄県民でさえ相手にしてくれなかった。でも3年、4年、10年と継続していく中で、地元の人から『そろそろ映画祭の時期だね』と言ってもらえるようになった。こういう映画祭を16年も続けることができて、ありがとうという気持ちです」と振り返る。
だが、この映画祭がなぜ沖縄の人々の心をつかんだのか。沖縄での盛り上がりとは裏腹に、その実体は県外の人々にはなかなか知られていない。しかし15年以上も映画祭が続くというのは容易なことではない。そこで今回は“最後の沖縄国際映画祭”を通じて、沖縄で何が行われていたのか振り返ってみたい。
■首里劇場などから沖縄の歴史を感じる
映画祭前夜となる19日には、クラフトビール醸造所「浮島ブルーイング」のタップルームで「首里劇場特集」と題したプレイベントを実施。平良竜次監督の「首里劇場ノスタルヂア」「焼け跡のバレエ発表会」、そして「ドキュメント九州」で放送された沖縄テレビ放送の小林美沙希アナウンサーが手掛けた番組「首里劇場沖縄に残る奇跡の映画館」の3本を上映。解体前までは“沖縄で現存する最古の映画館”と呼ばれていた首里劇場に対する注目度は高く、この日も会場には数十人の立ち見が出るほどの大盛況となった。
1950年に開館した首里劇場は、2022年の金城政則館長の他界によって閉館。戦後沖縄の芝居小屋の息吹を現代に伝えてきた首里劇場の建物は、建築的にも文化的にも非常に価値が高く、建築、映画関係など各分野の専門家が集結した「首里劇場調査団」がその建物の保存に向けて調査・研究が進められたが、2023年秋には建物は解体されることとなった。首里劇場調査団で副代表を務める平良氏は、このプレイベントで「ここ数年は沖縄も再開発がすごくて。歴史的な面白い建物であってもどんどん取り壊されていって。沖縄の戦後史がぞんざいに扱われているなと思っていた。その歴史のひとつが首里劇場だった。それだからこそ、こだわりがあった」と活動への思いを語った。
そして20、21日は映画祭本番。「沖縄国際映画祭」を語る上で、映画祭の名物プログラム「デジタルで甦る8ミリの沖縄」は欠かせない。8ミリフィルムの収集と公開を手掛ける沖縄アーカイブ研究所の真喜屋力監督と、『一生売れない心の準備はできてるか』の當間早志監督が仕掛ける本プログラムは、沖縄の人々が撮った8ミリ映画や、沖縄で撮影された劇映画の一場面などを紹介し、それがどこで撮られたのか、現在はどうなっているのかなどを、グーグルストリートビューや、実際に現場に足を運んで同じ角度で撮影した写真、地図などを駆使してプロファイリング化。その調査報告、比較映像などを楽しむ観客参加型の人気プログラムとなっている。上映会は非常にアットホームな空間で、壇上で話が進む最中に客席からも「あそこには○○があった」「それは○○のことだと思う」といった声が自由に飛び出すこともしばしばだ。
この日も、ある映像に映り込んでいた存在感のある男性が、実は沖縄出身の名優・津嘉山正種の若き日の姿であったことが明らかになるなど、何が飛び出すか分からないのもこのプログラムの魅力。スペシャルゲストとして参加していた板尾創路も「最初はどういう上映会なのか想像もつかなかったけど、普通に親戚が集まってみんなでワイワイ言っているようなゆるい感じが楽しかった。沖縄の人間じゃなくても楽しめたし、こうしたアーカイブは貴重な財産になるので、ぜひ続けていってほしいなと思います」と期待を寄せていた。
■海外からのゲストも参加
島で行われる“国際映画祭”ということで、海外ゲストの招へいにも積極的に取り組んでいた。沖縄国際映画祭の審査委員長や名誉顧問などを務めたこともある“釜山映画祭の父”キム・ドンホ氏は、過去に悲しい歴史を持つ沖縄という地に映画祭ができたことが「むしろ遅すぎたくらいだ」と語り、映画祭とは「人の感情を慰め、楽しませる“遊びの場”であるのだから」と指摘していた。その他、思い浮かぶだけでも「ダラス・バイヤーズ・クラブ」のジャン=マルク・バレ監督、「バットマン」シリーズのジョエル・シュマッカー監督、ニック・フロストやジョニー・ノックスビルらが沖縄にやってきた。また映画祭の特長としてフィリピンやインドネシア、タイ、インド、韓国、中国などアジア圏の作品を積極的に上映しており、日本では観る機会の少ない作品に触れることができた。
今年もタイ映画の「A TIME TO FLY」や、インドネシア映画「恋する牡丹」などを上映。元JKT48のジェシカ・べランダが主演を務める「恋する牡丹」は、北海道を舞台に複数の男女が繰り広げるすれ違いの恋模様が描かれる作品。ゲストで来場したべランダは「JKT48を卒業してからドラマなどでいくつか俳優業をやったことはありますが、主演映画はこれが初めてなので緊張しました」と挨拶。インドネシアに先行して、沖縄がワールドプレミア上映となったが、「これからインドネシアでも上映されるので是非ともインドネシアに遊びに来てね!」と観客にアピールしていた。
さらに余談だが、「沖縄国際映画祭」といえば、スイス・Cinerent社製の幅26.56メートル、高さ14.76メートルの移動式屋外スクリーンが語り草となっていた。宜野湾のビーチに、映画祭のためにスイスから取り寄せたスクリーンが鎮座する姿はなかなかの迫力だった。実は3月の夜のビーチは多少冷え込むのだが、その中で観た「ニュー・シネマ・パラダイス」「ショーシャンクの空に」「少林寺木人拳」などは開放的かつ幻想的な雰囲気と、ちょっぴりヒンヤリとした思い出も相まって非常に印象深い。
さて、映画祭2日目となる20日には映画祭の華であるレッドカーペットイベントを実施。那覇市の全面協力によって、沖縄のメインストリートとなる国際通りにレッドカーペットを敷き詰め、豪華ゲストが来場。今年は剛力彩芽、浅野忠信らをはじめ、大勢の吉本芸人たちがレッドカーペットをかっ歩した。そしてトリを飾ったのは映画祭実行委員会の大崎洋氏。沿道からは「16年ありがとう!」「まだ終わらないで!」という声も飛び交った。
■映画祭実行委員長の大崎洋氏が語ったこと
クロージングセレモニーの舞台に立った大崎実行委員長は「今年が最後かなと思うと少しさみしいです。46年前、1978年くらいに初めて沖縄に行きまして。そこから46年間、なんとか沖縄にご縁をつくりたいと思って通ってきました。2009年に吉本興業の社長に就任したときに真っ先に決めたのが沖縄国際映画祭の開催と、コンプライアンス会議でした。去年、悪の巣窟の吉本興業を退社しまして。非常にさわやかな気持ちでやっております」と冗談めかして会場を笑わせると、「来年に向けて沖縄の皆さまともう一度決意を新たにして。沖縄の方々が自らこの映画祭を引き継いでいただいて。僕たちに協力できることは今まで通り協力させていただいて。バトンタッチできればと思っております」と会場に呼びかけるなど、今後の展開にも含みを持たせた。
北野武を筆頭に、品川ヒロシ、劇団ひとりなど、映画監督としても高い評価を受ける芸人は多いが、沖縄国際映画祭という場でその才能を発揮したのがガレッジセールのゴリだ。2006年に初短編「刑事ボギー」で映画のキャリアを開始し、ショートショートフィルムフェスティバルで「話題賞」を獲得。そして長編監督デビュー作となる「南の島のフリムン」を第1回「沖縄国際映画祭」で上映。そこから毎年コンスタントに短編映画を撮り続け、短編「born、bone、墓音。」を長編化した18年の映画「洗骨」(監督名義は照屋年之)が国内外で高い評価を受けた。
20日にはゴリの新作「かなさんどー」発表会見が行われ、松田るか、浅野忠信、堀内敬子、そしてプロデューサーの福田淳が出席。映画のベースとなったのは、22年に満島ひかり主演で撮影した短編映画「演じる女」。撮影中は大変なことも多く、毎回「もうイヤだ」と思うのに、完成した映画を観て人々が笑ったり泣いたりしている姿を見るとすべてを忘れ、やみつきになってしまったといい、「これまで14本撮っているのってあまり知られていないと思うんです。撮る喜びが大きすぎて。やめられずにいます」と映画への魅力を語るゴリ。
そんなゴリの才能に惚れ込み、製作総指揮を務めているのが、近年はSTARTO ENTERTAINMENTの代表としても広く知られるようになった福田淳氏。「『洗骨』に感動しまくって。面識もないのにお会いして、『映画撮りましょうよ』と言ったのに暗い感じだった。昨日お会いした時にその理由が分かったのですが、僕のことを信用できなかったと言うんです。だから1年経ってやっと信頼してもらった。それでここに立つことができた」と冗談めかして製作の経緯を説明。映画はすでに完成しているとのことで、キャスト陣も「映画を観て泣いてしまった」と口にするなど、その出来が期待される。公開は25年を予定。
■クライマックスは音楽で祝福
そして「沖縄国際映画祭」のクライマックスといえば、音楽ライブ。会場に集まった参加者で映画祭が無事に終わったことを祝福し、笑顔を共有するというのが恒例のスタイルだ。今年はかりゆし58、夏川たまき、宮沢和史らが参加。かりゆし58の「アンマー」「オワリはじまり」や、THE BOOMの「星空のラブレター」「風になりたい」といった懐かしい曲が披露されて会場は大盛り上がり。最後は参加者全員がステージに上がり宮沢の「シンカヌチャー」を全員で大合唱し、大団円となった。
そしてその後、ステージは暗くなり、沖縄国際映画祭のテーマソングであるBEGIN with アホナスターズの「笑顔のまんま」が鳴り響く中、スクリーンには第1回から現在までの映画祭のダイジェスト映像を上映。映像を観た観客は笑顔を見せながら、それぞれに映画祭への思いをめぐらせているようだった。
なお、ここからは余談を少々。このステージで、かりゆし58の前川真悟が語っていたMCが印象的だったので引用する。「僕はこのイベントがとても好きです。たくさん理由はあるんですが、とても印象的なのが今から13年前。2011年3月に開催された国際映画祭でした。当時、東日本大震災で日本中、世界中がかたずをのんで。そんなことをやっている場合じゃないから自粛しましょうという流れが世の中に蔓延していました。その中でもこのイベントは、こんな時だからこそ、ひとつでも多くの笑顔をつくるのが大事じゃないかと言って決行しました。なんかこういうことのために、この島で生まれた祭りがエネルギーを発するのはとてもいいなと誇らしく思いました」。その思いは今でも変わらず、地震で大きな被害を受けている能登半島へ思いを馳せた。
あの当時のエンタテイメントをめぐる状況下では、誰もが絶望感や無力感を抱き、「自分たちになにができるのか」と自問自答していた。そんな時にこの映画祭はこう語っていた。
「私たちにできることが、きっとある」。その時は売り上げの一部や支援物資、そして会場で観客から義援金などを集め、被災地に寄付された。振り返ってみると、エンタメに関わる多くの人たちが、あの頃を境に下を向かず「私たちにできることが、きっとある」と模索を始めたように思う。映画祭の会場では毎年どこでも「笑顔のまんま」が流れていたが、この曲を聴くたびにあの時のことを思い出す。(取材・文/壬生智裕)
【関連記事】
・【特集】沖縄国際映画祭2019
・【フォトギャラリー】エンディングライブ、その他の写真
・【フォトギャラリー】レッドカーペット、その他の写真
・【写真で述懐】安室奈美恵さん、黒木メイサ、阿部寛らも参加した沖縄国際映画祭
“笑い”をテーマに、映画のみならず、音楽、お笑い、ダンス、スポーツなど沖縄全域を網羅して行われる異色の映画祭は、春の風物詩として確かに沖縄に深く根付いていた。特に宜野湾コンベンションセンターをメイン会場としていた初期には10日間にわたり開催されていた時期もあり、最多で45万人近い観客を動員。以前、沖縄国際映画祭を取材していた外国人記者が「世界でも、子どもたちがこんなにも笑っている映画祭を観たことがない」と語るほどに、笑顔にあふれた映画祭だった。だがコロナ禍以降は週末2日間だけの開催となり、徐々に規模が縮小傾向にあったため、今回の離脱表明で決定的なものとなった。
やはり“吉本が手掛ける映画祭”というイメージが先行していたせいか、当初は批判的なコメントもあったようだ。映画祭の顔として尽力してきたガレッジセールのゴリは、「最初は吉本が映画祭をやると言っても、沖縄県民でさえ相手にしてくれなかった。でも3年、4年、10年と継続していく中で、地元の人から『そろそろ映画祭の時期だね』と言ってもらえるようになった。こういう映画祭を16年も続けることができて、ありがとうという気持ちです」と振り返る。
だが、この映画祭がなぜ沖縄の人々の心をつかんだのか。沖縄での盛り上がりとは裏腹に、その実体は県外の人々にはなかなか知られていない。しかし15年以上も映画祭が続くというのは容易なことではない。そこで今回は“最後の沖縄国際映画祭”を通じて、沖縄で何が行われていたのか振り返ってみたい。
■首里劇場などから沖縄の歴史を感じる
映画祭前夜となる19日には、クラフトビール醸造所「浮島ブルーイング」のタップルームで「首里劇場特集」と題したプレイベントを実施。平良竜次監督の「首里劇場ノスタルヂア」「焼け跡のバレエ発表会」、そして「ドキュメント九州」で放送された沖縄テレビ放送の小林美沙希アナウンサーが手掛けた番組「首里劇場沖縄に残る奇跡の映画館」の3本を上映。解体前までは“沖縄で現存する最古の映画館”と呼ばれていた首里劇場に対する注目度は高く、この日も会場には数十人の立ち見が出るほどの大盛況となった。
1950年に開館した首里劇場は、2022年の金城政則館長の他界によって閉館。戦後沖縄の芝居小屋の息吹を現代に伝えてきた首里劇場の建物は、建築的にも文化的にも非常に価値が高く、建築、映画関係など各分野の専門家が集結した「首里劇場調査団」がその建物の保存に向けて調査・研究が進められたが、2023年秋には建物は解体されることとなった。首里劇場調査団で副代表を務める平良氏は、このプレイベントで「ここ数年は沖縄も再開発がすごくて。歴史的な面白い建物であってもどんどん取り壊されていって。沖縄の戦後史がぞんざいに扱われているなと思っていた。その歴史のひとつが首里劇場だった。それだからこそ、こだわりがあった」と活動への思いを語った。
そして20、21日は映画祭本番。「沖縄国際映画祭」を語る上で、映画祭の名物プログラム「デジタルで甦る8ミリの沖縄」は欠かせない。8ミリフィルムの収集と公開を手掛ける沖縄アーカイブ研究所の真喜屋力監督と、『一生売れない心の準備はできてるか』の當間早志監督が仕掛ける本プログラムは、沖縄の人々が撮った8ミリ映画や、沖縄で撮影された劇映画の一場面などを紹介し、それがどこで撮られたのか、現在はどうなっているのかなどを、グーグルストリートビューや、実際に現場に足を運んで同じ角度で撮影した写真、地図などを駆使してプロファイリング化。その調査報告、比較映像などを楽しむ観客参加型の人気プログラムとなっている。上映会は非常にアットホームな空間で、壇上で話が進む最中に客席からも「あそこには○○があった」「それは○○のことだと思う」といった声が自由に飛び出すこともしばしばだ。
この日も、ある映像に映り込んでいた存在感のある男性が、実は沖縄出身の名優・津嘉山正種の若き日の姿であったことが明らかになるなど、何が飛び出すか分からないのもこのプログラムの魅力。スペシャルゲストとして参加していた板尾創路も「最初はどういう上映会なのか想像もつかなかったけど、普通に親戚が集まってみんなでワイワイ言っているようなゆるい感じが楽しかった。沖縄の人間じゃなくても楽しめたし、こうしたアーカイブは貴重な財産になるので、ぜひ続けていってほしいなと思います」と期待を寄せていた。
■海外からのゲストも参加
島で行われる“国際映画祭”ということで、海外ゲストの招へいにも積極的に取り組んでいた。沖縄国際映画祭の審査委員長や名誉顧問などを務めたこともある“釜山映画祭の父”キム・ドンホ氏は、過去に悲しい歴史を持つ沖縄という地に映画祭ができたことが「むしろ遅すぎたくらいだ」と語り、映画祭とは「人の感情を慰め、楽しませる“遊びの場”であるのだから」と指摘していた。その他、思い浮かぶだけでも「ダラス・バイヤーズ・クラブ」のジャン=マルク・バレ監督、「バットマン」シリーズのジョエル・シュマッカー監督、ニック・フロストやジョニー・ノックスビルらが沖縄にやってきた。また映画祭の特長としてフィリピンやインドネシア、タイ、インド、韓国、中国などアジア圏の作品を積極的に上映しており、日本では観る機会の少ない作品に触れることができた。
今年もタイ映画の「A TIME TO FLY」や、インドネシア映画「恋する牡丹」などを上映。元JKT48のジェシカ・べランダが主演を務める「恋する牡丹」は、北海道を舞台に複数の男女が繰り広げるすれ違いの恋模様が描かれる作品。ゲストで来場したべランダは「JKT48を卒業してからドラマなどでいくつか俳優業をやったことはありますが、主演映画はこれが初めてなので緊張しました」と挨拶。インドネシアに先行して、沖縄がワールドプレミア上映となったが、「これからインドネシアでも上映されるので是非ともインドネシアに遊びに来てね!」と観客にアピールしていた。
さらに余談だが、「沖縄国際映画祭」といえば、スイス・Cinerent社製の幅26.56メートル、高さ14.76メートルの移動式屋外スクリーンが語り草となっていた。宜野湾のビーチに、映画祭のためにスイスから取り寄せたスクリーンが鎮座する姿はなかなかの迫力だった。実は3月の夜のビーチは多少冷え込むのだが、その中で観た「ニュー・シネマ・パラダイス」「ショーシャンクの空に」「少林寺木人拳」などは開放的かつ幻想的な雰囲気と、ちょっぴりヒンヤリとした思い出も相まって非常に印象深い。
さて、映画祭2日目となる20日には映画祭の華であるレッドカーペットイベントを実施。那覇市の全面協力によって、沖縄のメインストリートとなる国際通りにレッドカーペットを敷き詰め、豪華ゲストが来場。今年は剛力彩芽、浅野忠信らをはじめ、大勢の吉本芸人たちがレッドカーペットをかっ歩した。そしてトリを飾ったのは映画祭実行委員会の大崎洋氏。沿道からは「16年ありがとう!」「まだ終わらないで!」という声も飛び交った。
■映画祭実行委員長の大崎洋氏が語ったこと
クロージングセレモニーの舞台に立った大崎実行委員長は「今年が最後かなと思うと少しさみしいです。46年前、1978年くらいに初めて沖縄に行きまして。そこから46年間、なんとか沖縄にご縁をつくりたいと思って通ってきました。2009年に吉本興業の社長に就任したときに真っ先に決めたのが沖縄国際映画祭の開催と、コンプライアンス会議でした。去年、悪の巣窟の吉本興業を退社しまして。非常にさわやかな気持ちでやっております」と冗談めかして会場を笑わせると、「来年に向けて沖縄の皆さまともう一度決意を新たにして。沖縄の方々が自らこの映画祭を引き継いでいただいて。僕たちに協力できることは今まで通り協力させていただいて。バトンタッチできればと思っております」と会場に呼びかけるなど、今後の展開にも含みを持たせた。
北野武を筆頭に、品川ヒロシ、劇団ひとりなど、映画監督としても高い評価を受ける芸人は多いが、沖縄国際映画祭という場でその才能を発揮したのがガレッジセールのゴリだ。2006年に初短編「刑事ボギー」で映画のキャリアを開始し、ショートショートフィルムフェスティバルで「話題賞」を獲得。そして長編監督デビュー作となる「南の島のフリムン」を第1回「沖縄国際映画祭」で上映。そこから毎年コンスタントに短編映画を撮り続け、短編「born、bone、墓音。」を長編化した18年の映画「洗骨」(監督名義は照屋年之)が国内外で高い評価を受けた。
20日にはゴリの新作「かなさんどー」発表会見が行われ、松田るか、浅野忠信、堀内敬子、そしてプロデューサーの福田淳が出席。映画のベースとなったのは、22年に満島ひかり主演で撮影した短編映画「演じる女」。撮影中は大変なことも多く、毎回「もうイヤだ」と思うのに、完成した映画を観て人々が笑ったり泣いたりしている姿を見るとすべてを忘れ、やみつきになってしまったといい、「これまで14本撮っているのってあまり知られていないと思うんです。撮る喜びが大きすぎて。やめられずにいます」と映画への魅力を語るゴリ。
そんなゴリの才能に惚れ込み、製作総指揮を務めているのが、近年はSTARTO ENTERTAINMENTの代表としても広く知られるようになった福田淳氏。「『洗骨』に感動しまくって。面識もないのにお会いして、『映画撮りましょうよ』と言ったのに暗い感じだった。昨日お会いした時にその理由が分かったのですが、僕のことを信用できなかったと言うんです。だから1年経ってやっと信頼してもらった。それでここに立つことができた」と冗談めかして製作の経緯を説明。映画はすでに完成しているとのことで、キャスト陣も「映画を観て泣いてしまった」と口にするなど、その出来が期待される。公開は25年を予定。
■クライマックスは音楽で祝福
そして「沖縄国際映画祭」のクライマックスといえば、音楽ライブ。会場に集まった参加者で映画祭が無事に終わったことを祝福し、笑顔を共有するというのが恒例のスタイルだ。今年はかりゆし58、夏川たまき、宮沢和史らが参加。かりゆし58の「アンマー」「オワリはじまり」や、THE BOOMの「星空のラブレター」「風になりたい」といった懐かしい曲が披露されて会場は大盛り上がり。最後は参加者全員がステージに上がり宮沢の「シンカヌチャー」を全員で大合唱し、大団円となった。
そしてその後、ステージは暗くなり、沖縄国際映画祭のテーマソングであるBEGIN with アホナスターズの「笑顔のまんま」が鳴り響く中、スクリーンには第1回から現在までの映画祭のダイジェスト映像を上映。映像を観た観客は笑顔を見せながら、それぞれに映画祭への思いをめぐらせているようだった。
なお、ここからは余談を少々。このステージで、かりゆし58の前川真悟が語っていたMCが印象的だったので引用する。「僕はこのイベントがとても好きです。たくさん理由はあるんですが、とても印象的なのが今から13年前。2011年3月に開催された国際映画祭でした。当時、東日本大震災で日本中、世界中がかたずをのんで。そんなことをやっている場合じゃないから自粛しましょうという流れが世の中に蔓延していました。その中でもこのイベントは、こんな時だからこそ、ひとつでも多くの笑顔をつくるのが大事じゃないかと言って決行しました。なんかこういうことのために、この島で生まれた祭りがエネルギーを発するのはとてもいいなと誇らしく思いました」。その思いは今でも変わらず、地震で大きな被害を受けている能登半島へ思いを馳せた。
あの当時のエンタテイメントをめぐる状況下では、誰もが絶望感や無力感を抱き、「自分たちになにができるのか」と自問自答していた。そんな時にこの映画祭はこう語っていた。
「私たちにできることが、きっとある」。その時は売り上げの一部や支援物資、そして会場で観客から義援金などを集め、被災地に寄付された。振り返ってみると、エンタメに関わる多くの人たちが、あの頃を境に下を向かず「私たちにできることが、きっとある」と模索を始めたように思う。映画祭の会場では毎年どこでも「笑顔のまんま」が流れていたが、この曲を聴くたびにあの時のことを思い出す。(取材・文/壬生智裕)
【関連記事】
・【特集】沖縄国際映画祭2019
・【フォトギャラリー】エンディングライブ、その他の写真
・【フォトギャラリー】レッドカーペット、その他の写真