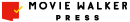映画からインスピレーションを受けることもあるゆっきゅんがフランス映画の魅力、おもしろさを語る!/撮影/杉映貴子
映画の原体験は『下妻物語』!アーティスト・ゆっきゅんがひも解くフランス映画の奥深さ「映画を観たあとに持ち帰った問いが、ずっと心のなかで生き続ける」
1月31日(水) 18:30
映画ファンのための“ここでしか観られない”作品の数々を発信するAmazon Prime Video チャンネル「スターチャンネルEX」。現在、「Gaumont(ゴーモン)」セレクションと題して、フランスの老舗映画会社「Gaumont」の作品群のなかから、日本ではなかなか観る機会のない貴重なレア作品を中心にした10作品を一挙配信中だ。
【写真を見る】ジャック・ドワイヨンがジェーン・バーキンを主演に迎えた美しくも恐ろしい家族の物語『放蕩娘』
そこで今回は、音楽活動の傍ら、映画評の執筆や映画関連のイベントなどでも活躍するアーティストのゆっきゅんが、本特集のなかから気になる3作品をセレクト。昨年12月にアンスティチュ・フランセ東京にて開催された「映画のアトリエ~フランス映画の秘宝を探して~」のトークショーにもゲストとして出演したゆっきゅんに、ピックアップした作品の見どころや魅力、さらに自身が好きなフランス映画などについても語ってもらった。
■「感情表現が、頭突きやソーサーで頭を殴るとか、“アクション”に表れているのがおもしろい」(『放蕩娘』)
まず紹介したいのは、先述のアンスティチュ・フランセ東京でのトークショー上映作品でもあった『放蕩娘』(81)。昨年7月に享年76歳でこの世を去ったジェーン・バーキンの知る人ぞ知る衝撃作だ。セルジュ・ゲンズブールと別れたばかりのバーキンとジャック・ドワイヨン監督が初めてタッグを組んだ記念すべき作品であり、本作をきっかけに2人は結ばれ、1982年には娘のルー・ドワイヨンが誕生。以降10年ほど、公私共にドワイヨンのパートナーとなったバーキンは、計3作のドワイヨン作品で主演を務めている。
精神的に不安定な状態に陥っていたアン(バーキン)は、夫と暮らす家を出て、ノルマンディーの実家に帰り、しばらく両親のもとで過ごそうとする。そんななか、母親はアンの姉の出産の立ち会いのために、家を離れることに。父親(ミシェル・ピコリ)と2人きりになったことで、胸の奥に秘めていた父への想いを募らせていくアン。やがて、苦悩しながらも、近親相姦的な怪しい関係になっていく。
「ELLEやFIGAROを読んでいるので、ジェーン・バーキンはファッションアイコンのイメージが強くて。“女優としてのジェーン・バーキン”をちゃんと意識して観たのは、本作が初めてでした」と明かすゆっきゅん。「ジェーンは声がすてきですよね。その声の表現が、この作品のキーになっていると思う。全編ずっと、まるで秘密を打ち明ける時のようなウィスパーボイスで、それが本作の“密室性”をすごく高めているんです。『いま、あなたの目の前には私しかいないのよ…』という雰囲気が、囁くような発声から感じられて。それが時間の経過につれ、2人の間の危険性をどんどん高めていく力になっていました」。
ちなみに、トークショーでの対談相手だった、ゆっきゅんの大学&大学院時代の指導教授で、映画批評家の三浦哲哉は、本作におけるバーキンの特徴として、トレードマークのすきっ歯がのぞく「半開きの口もと」について言及していたとのこと。「アンのキャラクターの幼さを強調するというか、どこか相手の庇護欲をかき立てるところがありますよね」。
ジャン=リュック・ゴダール監督の『軽蔑』(63)などで知られるフランスの名優ミシェル・ピコリ演じる父親に対し、娘が抱き続ける複雑な感情について、「2人の関係性のなかでの感情表現が、“アクション”に表れているのがおもしろい」と指摘する。
「いきなり頭突きをするとか、ティーカップのソーサーで頭を殴るとか、思わず笑ってしまうようなジェーンの身体的な動作が独特でおもしろかったです。ベッドの上で、アンが自分のシャツをたくし上げて、むき出しになった父親のおなかに上半身を押し付けたあと、バッと身体を離すシーンとかも…。執拗なまでの、いわゆる性接触ではない形での肉体的な接触。メタファーだと思うんですけど、すごく印象的でした」。
もう一つ、ゆっきゅんが気になった演出は「扉の使われ方」だという。「劇中でドアを閉めるシーンが多く映されていて。ドアを閉めることによって、関係の密室性というか、2人の逃げ場のない感じがよく出ているなと。終盤、アンが一度、実家を出たあと、また戻ってくるんですけど、その時も父と娘が扉をはさんで対面する。やっぱり、扉が重要なモチーフとして扱われているように思いました。忘れられないシーンですね」。
■「おばあさんたちが高齢になったいまでもお互いに大切な友だちとして仲良くしている」(『ジャンキーばあさんのあぶないケーキ屋』)
続いては、1950年代からフランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、ジャック・リヴェットといった“ヌーヴェルヴァーグ”の監督たちの作品で活躍し、2013年に74歳でその生涯を閉じたフランスの名女優、ベルナデット・ラフォン主演の痛快フレンチ・コメディ。今回が日本初公開となるジェローム・エンリコ監督の『ジャンキーばあさんのあぶないケーキ屋』(12)は、彼女にとってほぼ最後の主演作となった。
最愛の夫に先立たれ、わずかな年金で苦しい生活を送っている老女ポーレット(ラフォン)は、あまり治安のよくないパリ郊外の団地で一人暮らし。ある夜、団地の外で大麻の密売が行われているのを目撃し、密売人たちの稼ぎがいいことを知った彼女は、かつて夫婦でケーキ屋を営んでいたころの腕を活かし、大麻入りのクッキーやケーキを販売することを思いつく。ポーレットが作るお菓子はひそかに評判となり、事情を知った彼女の友人3人も店のスタッフとして参加することに。おかげでケーキ屋はますます繁盛するが、彼女たちの予想を超える成功は、やがて大切な孫の命を危険にさらす事態へと発展してしまう…。
主演のラフォンが出演したジャン・ユスターシュ監督の恋愛映画『ママと娼婦』(73)を昨年偶然にも観ていたというゆっきゅんは、「あの作品のマリー役の人が、40年後に、このおばあさんになったんだ!と思うと、楽しい気持ちになりました」と笑う。「おもしろい邦題のイメージどおり、おばあさんがやりたい放題する終始愉快なお話で、爆笑しながら観ていました。友だちにも『この映画観て!』と宣伝活動していますよ(笑)」。
本作に惹かれた一番の理由については、「まず、私は女性同士の友情が描かれている作品が好きなんです」と話す。「女友だちとの友情は、ライフステージの変化によって、30代前後の時期に離ればなれになってしまう…とよく言われるじゃないですか。それが、本作のおばあさんたちは、過去になにがあったかは知らないけれど、高齢になったいまでもお互いに大切な友だちとして仲良くしているという設定で。それが2人ではなくて、4人グループというのもすごくいいなって。古くからの友人なんでしょうね。ポーレットが『実はこのお菓子には大麻が入っていて…』と彼女たちに打ち明けた時、すぐに『そう。じゃあ、手伝うよ!』という反応が返ってきたところも、観ていて笑顔になりました」。
アナーキーなおばあさんたちが繰り広げるドタバタ劇でありながら、笑いだけでなく、心温まるシーンも多い。なかでもゆっきゅんの胸を打ったのは、終盤、ポーレットたちが大麻の密売で稼いだお金で旅行に出た時のワンシーン。「ギャンブルで一晩遊んだあとの夜明けの時間帯、酔っ払ってご機嫌の4人が手をつなぎながら、港の遊歩道を楽しそうにヘラヘラ歩いていく姿を後ろから撮っているんです。時々、船の汽笛の音に振り返る人もいたりして。みんな、自分たちがいずれ捕まることは心のどこかでわかっていて、これが最初で最後の旅行なんだ…と思っている感じが伝わってきて、すごくグッときました」。
独り身の高齢者の厳しい生活という、日本でも変わらぬ社会的なテーマを扱っていても、その語り口はどこまでもポジティブで軽やか。「夫もいないし、残り少ない人生だし、もう、やっちゃおうか!という、彼女たちのたくましさがおもしろかった。自由なおばあさんたちから元気をもらえる映画です」。
■「精神的に自立していない思春期に、近すぎる関係になってしまうことの危うさ」(『呼吸―友情と破壊』)
3本目は、『イングロリアス・バスターズ』(09)、『複製された男』(13)などで女優としても活躍するメラニー・ロランが、自身とほぼ同世代の作家で“第二のサガン”と評されたアンヌ=ソフィ・ブラムスの17歳の時のデビュー作「深く息を吸って」を自ら監督として映画化した青春ドラマ『呼吸―友情と破壊』(14)。主人公の女子高生2人を演じたジョセフィーヌ・ジャピとルー・ドゥ・ラージュは、本作でそれぞれセザール賞有望若手女優賞、セザール賞最優秀女優賞にノミネートされるなど、その演技を高く評価された。
17歳のシャルリ(ジャピ)はまじめで内向的、友人に恵まれている一方で、どこか孤独を感じていた。そんなある日、サラ(ラージュ)という美しい転校生がやって来る。個性的でカリスマ性のあるサラは、なぜかシャルリを気に入り、2人は急接近。親しくなるにつれ、奔放なサラにどんどん惹かれていくシャルリだったが、いつしかその関係に綻びが生じ始める。シャルリが失われた友情を取り戻そうとすればするほど、サラの冷酷さはエスカレートしていく。
「精神的にまだ自立していない、自分と他人との境界がそんなにはっきりしていない思春期に、2人きりという近すぎる関係になってしまうことの危うさが描かれている作品でした。そういう時期に急激に仲良くなる女の子2人って、ずっと仲良いままではいなかったりするじゃないですか。普遍的な話だと思いつつ、その関係性がすごくリアルでしたね。観ていてヒリヒリ感を覚えるのは、きっと監督であるメラニー・ロランに、この物語を描かなきゃいけない!という切実さがあったからだと思います」。
ゆっきゅんは「2人の関係が変容するきっかけの一つ」として、サラに秘密があると感じたシャルリが、夜に帰宅する彼女をこっそり尾行し、家を覗いてしまったことを挙げる。「母親はNPO職員で海外にいる。自分は叔母と生活している」と周囲に語っていたサラの嘘が明らかになる描写だ。「サラが家に入ってから、カメラが横にゆっくりと移動していくショットはインパクトがありました。その直前にサラが学校で“サファリ”の話をしていたこともあって、まるで夜のサファリパークを見ているような感じがして。家の中には獰猛な母がいて、部屋の窓の柵は檻みたいに見えたんです。しかも、壁の外の暗闇にシャルリが静かに立っているっていう…青春ドラマから心理サスペンスへと切り替わった瞬間でした」。
終盤になってくると、様々なシーンで、キーンと響く耳鳴りのような音響が入っているのも印象的。「本当に自分の耳鳴りかと思っちゃうくらい。シャルリが感じているものが、観ているこちらの身体にも浸透してくる感覚でした。画面全体にあふれる、出口のない、切迫しているムードがすごいなと思いましたね。シャルリに喘息の持病があるという設定も効いていて、タイトルどおり、息が詰まるようなシーンが何度もありました」。
■「レポートの課題でBunkamuraル・シネマに行ったのが、フランス映画を劇場で観る初めての経験」
高校生の時から、音楽や美術、映画が好きで、「作品に触れた感動や自分の感性の部分を言語化できるようになりたいという想いから、映画評論家の方がいる大学だけを受験しました」と語るゆっきゅん。青山学院大学文学部比較芸術学科に進学したあとは、映画批評家の三浦哲哉のゼミに入り、映画監督の山戸結希をテーマに卒論を執筆。その後、進んだ大学院での修士論文では“少女マンガ実写化映画の変遷”をテーマにしたという。
そんなゆっきゅんに映画の原体験について尋ねると、「小学3年生の時に映画館で観た『下妻物語』です」との答えが返ってきた。「それ以降、実家のわりと近くにあった岡山県唯一のミニシアターに母親を連れて行く形で、いろんな映画を観に通いました。邦画ばっかりでしたけど。あと、oniビジョンという岡山県のケーブルテレビがあって、そこでスターチャンネルや日本映画の専門チャンネルを通して文化享受をしてきましたね」。
大学生になってからは渋谷の映画館を中心に、思う存分、映画鑑賞三昧の日々。「フランス映画に初めてきちんと触れたのも、大学の映画の授業がきっかけでした。まず、クラスみんなでジャン・ルノワール監督の『ピクニック』を観たんです。その後、当時が2014年春だったので、ちょうど公開されていた『アデル、ブルーは熱い色』を観てレポートを書きなさいという課題が出て。『アデル』は過激そうで、ちょっと無理かも…という人は、ジャック・タチ映画祭に行きなさいって(笑)。それで、いまは場所を移転したBunkamuraル・シネマに行ったのが、フランス映画を劇場で観るという初めての経験だった気がします」と、ゆっきゅんは懐かしそうに振り返る。
■「映画や映像と、自分が歌う、表現していくことの関係が年々、密になっている感覚があります」
学生のころから好きなフランスの映画監督はエリック・ロメール。「新文芸坐のオールナイト上映には何回も行きました。ロメールの作品は古さをまったく感じないというか、私にはずっと新鮮に、新しいことに見えます。特に『緑の光線』とか『レネットとミラベル/四つの冒険』が好きですね。いわゆる大作とは違う、ちょっと力を抜いて観られる会話劇で、登場人物たちの人間関係を通して描く“人生のひととき”な感じが好きです」。
音楽活動をしているゆっきゅんは「映画からインスピレーションを受けることも多い」という。「こういう映画みたいな曲を書きたいなと思って歌詞を書いたりもすることもあります。次に出す曲は、一昨年日本で公開されたバーバラ・ローデン監督・脚本・主演の『WANDA/ワンダ』とか、アニエス・ヴァルダ監督の『冬の旅』とか、女性が1人で放浪するような映画にインスパイアされて作ったものなんです。特定の映画じゃなくても、頭のなかに浮かんだ映像を、どう歌に落とし込もうかと考えることも増えてきて。ずっと映画を観てきたので、映画や映像と、自分が歌う、表現していくことの関係が年々、密になっている感覚がありますね」。
■「フランス映画は、わかりやすい大きな1つの答えがもらえるようなものではない」
ここ2~3年、フランス映画は新作というよりも「レトロスペクティブがあまりにも充実しているので、劇場で上映される監督映画特集によく足を運んでいる」とのこと。「サッシャ・ギトリ監督、ジャン・ユスターシュ監督、アルノー・デプレシャン監督、あとフランスじゃなくてベルギーですけど、シャンタル・アケルマン監督の特集上映にも通いました。リバイバルされるだけの価値があるってことだから、レトロスペクティブって信頼してしまうとこがあって。いまの感覚のまま昔の作品を観てもやっぱりおもしろいんですよね。そういう人が増えているみたいです。アケルマン監督特集では、代表作の『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』に比べればマイナーな『一晩中』を平日の夜の回に観に行ったのですが、ほぼ満席だったんです!」。
「フランス映画は、ハリウッド映画みたいにわかりやすい大きな1つの答えがもらえるようなものでは、たぶん、まったくない」と話すゆっきゅん。その代わりに「映画を観たあとに持ち帰った問いが、ずっと心のなかで生き続けたり、人生のとある場面で、これって、あの映画で観たアレだったのかと気づいたり…あとで咲くことが多いと思います。(少し難しいと思っても)肩の力を抜いて、適当にでも、どんどん観ていけばいいんですよ」と笑いながら、ニュアンスに満ちたフランス映画の奥深い魅力を表現してくれた。
スターチャンネルEXの「Gaumont(ゴーモン)」セレクションでは、「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン」誌元編集委員でアンスティチュ・フランセの映画プログラム主任を務める坂本安美が作品セレクトを担当。ここで紹介した3作品のほか、ヴァレリー・ルメルシエが監督・脚本・主演を兼任した『愛しのプリンセスが死んだワケ』(05)やフランスを代表する名匠サッシャ・ギトリの『これで三度目』(52)、モーリス・ピアラ監督の長編デビュー作『裸の幼年時代』(68)といった日本初公開作品を含むバラエティに富んだ、見逃せない注目作がずらりと並んでいる。この機会に気になる作品をチェックして、フランス映画のおもしろさをぜひ体感してみてほしい。
取材・文/石塚圭子
【関連記事】
・ 「おしん」「渡鬼」泉ピン子が英国の伝説女優に重ねた生き様「長くドラマを続けていくというのは大変なこと」
・ あなたはどのマッツが好き?情けない中年男に、やさぐれ医師、裏社会のスキンヘッド…“北欧の至宝”マッツ・ミケルセンに魅せられる10選
・ ダイアナ元妃が語り継がれるプリンセスである理由は“不幸な美しさ”?チャールズ国王の後輩、ハリー杉山が語る英国の王室事情
・ 知られざる生々しい実像に、その輝きの根源を知る…ファン必見の映画『オードリー・ヘプバーン』を解説
・ パリ留学中の和田彩花が語るフランス映画の醍醐味「作られた場所の文化や歴史、作り手のルーツなどが組み合わさっている」
【写真を見る】ジャック・ドワイヨンがジェーン・バーキンを主演に迎えた美しくも恐ろしい家族の物語『放蕩娘』
そこで今回は、音楽活動の傍ら、映画評の執筆や映画関連のイベントなどでも活躍するアーティストのゆっきゅんが、本特集のなかから気になる3作品をセレクト。昨年12月にアンスティチュ・フランセ東京にて開催された「映画のアトリエ~フランス映画の秘宝を探して~」のトークショーにもゲストとして出演したゆっきゅんに、ピックアップした作品の見どころや魅力、さらに自身が好きなフランス映画などについても語ってもらった。
■「感情表現が、頭突きやソーサーで頭を殴るとか、“アクション”に表れているのがおもしろい」(『放蕩娘』)
まず紹介したいのは、先述のアンスティチュ・フランセ東京でのトークショー上映作品でもあった『放蕩娘』(81)。昨年7月に享年76歳でこの世を去ったジェーン・バーキンの知る人ぞ知る衝撃作だ。セルジュ・ゲンズブールと別れたばかりのバーキンとジャック・ドワイヨン監督が初めてタッグを組んだ記念すべき作品であり、本作をきっかけに2人は結ばれ、1982年には娘のルー・ドワイヨンが誕生。以降10年ほど、公私共にドワイヨンのパートナーとなったバーキンは、計3作のドワイヨン作品で主演を務めている。
精神的に不安定な状態に陥っていたアン(バーキン)は、夫と暮らす家を出て、ノルマンディーの実家に帰り、しばらく両親のもとで過ごそうとする。そんななか、母親はアンの姉の出産の立ち会いのために、家を離れることに。父親(ミシェル・ピコリ)と2人きりになったことで、胸の奥に秘めていた父への想いを募らせていくアン。やがて、苦悩しながらも、近親相姦的な怪しい関係になっていく。
「ELLEやFIGAROを読んでいるので、ジェーン・バーキンはファッションアイコンのイメージが強くて。“女優としてのジェーン・バーキン”をちゃんと意識して観たのは、本作が初めてでした」と明かすゆっきゅん。「ジェーンは声がすてきですよね。その声の表現が、この作品のキーになっていると思う。全編ずっと、まるで秘密を打ち明ける時のようなウィスパーボイスで、それが本作の“密室性”をすごく高めているんです。『いま、あなたの目の前には私しかいないのよ…』という雰囲気が、囁くような発声から感じられて。それが時間の経過につれ、2人の間の危険性をどんどん高めていく力になっていました」。
ちなみに、トークショーでの対談相手だった、ゆっきゅんの大学&大学院時代の指導教授で、映画批評家の三浦哲哉は、本作におけるバーキンの特徴として、トレードマークのすきっ歯がのぞく「半開きの口もと」について言及していたとのこと。「アンのキャラクターの幼さを強調するというか、どこか相手の庇護欲をかき立てるところがありますよね」。
ジャン=リュック・ゴダール監督の『軽蔑』(63)などで知られるフランスの名優ミシェル・ピコリ演じる父親に対し、娘が抱き続ける複雑な感情について、「2人の関係性のなかでの感情表現が、“アクション”に表れているのがおもしろい」と指摘する。
「いきなり頭突きをするとか、ティーカップのソーサーで頭を殴るとか、思わず笑ってしまうようなジェーンの身体的な動作が独特でおもしろかったです。ベッドの上で、アンが自分のシャツをたくし上げて、むき出しになった父親のおなかに上半身を押し付けたあと、バッと身体を離すシーンとかも…。執拗なまでの、いわゆる性接触ではない形での肉体的な接触。メタファーだと思うんですけど、すごく印象的でした」。
もう一つ、ゆっきゅんが気になった演出は「扉の使われ方」だという。「劇中でドアを閉めるシーンが多く映されていて。ドアを閉めることによって、関係の密室性というか、2人の逃げ場のない感じがよく出ているなと。終盤、アンが一度、実家を出たあと、また戻ってくるんですけど、その時も父と娘が扉をはさんで対面する。やっぱり、扉が重要なモチーフとして扱われているように思いました。忘れられないシーンですね」。
■「おばあさんたちが高齢になったいまでもお互いに大切な友だちとして仲良くしている」(『ジャンキーばあさんのあぶないケーキ屋』)
続いては、1950年代からフランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、ジャック・リヴェットといった“ヌーヴェルヴァーグ”の監督たちの作品で活躍し、2013年に74歳でその生涯を閉じたフランスの名女優、ベルナデット・ラフォン主演の痛快フレンチ・コメディ。今回が日本初公開となるジェローム・エンリコ監督の『ジャンキーばあさんのあぶないケーキ屋』(12)は、彼女にとってほぼ最後の主演作となった。
最愛の夫に先立たれ、わずかな年金で苦しい生活を送っている老女ポーレット(ラフォン)は、あまり治安のよくないパリ郊外の団地で一人暮らし。ある夜、団地の外で大麻の密売が行われているのを目撃し、密売人たちの稼ぎがいいことを知った彼女は、かつて夫婦でケーキ屋を営んでいたころの腕を活かし、大麻入りのクッキーやケーキを販売することを思いつく。ポーレットが作るお菓子はひそかに評判となり、事情を知った彼女の友人3人も店のスタッフとして参加することに。おかげでケーキ屋はますます繁盛するが、彼女たちの予想を超える成功は、やがて大切な孫の命を危険にさらす事態へと発展してしまう…。
主演のラフォンが出演したジャン・ユスターシュ監督の恋愛映画『ママと娼婦』(73)を昨年偶然にも観ていたというゆっきゅんは、「あの作品のマリー役の人が、40年後に、このおばあさんになったんだ!と思うと、楽しい気持ちになりました」と笑う。「おもしろい邦題のイメージどおり、おばあさんがやりたい放題する終始愉快なお話で、爆笑しながら観ていました。友だちにも『この映画観て!』と宣伝活動していますよ(笑)」。
本作に惹かれた一番の理由については、「まず、私は女性同士の友情が描かれている作品が好きなんです」と話す。「女友だちとの友情は、ライフステージの変化によって、30代前後の時期に離ればなれになってしまう…とよく言われるじゃないですか。それが、本作のおばあさんたちは、過去になにがあったかは知らないけれど、高齢になったいまでもお互いに大切な友だちとして仲良くしているという設定で。それが2人ではなくて、4人グループというのもすごくいいなって。古くからの友人なんでしょうね。ポーレットが『実はこのお菓子には大麻が入っていて…』と彼女たちに打ち明けた時、すぐに『そう。じゃあ、手伝うよ!』という反応が返ってきたところも、観ていて笑顔になりました」。
アナーキーなおばあさんたちが繰り広げるドタバタ劇でありながら、笑いだけでなく、心温まるシーンも多い。なかでもゆっきゅんの胸を打ったのは、終盤、ポーレットたちが大麻の密売で稼いだお金で旅行に出た時のワンシーン。「ギャンブルで一晩遊んだあとの夜明けの時間帯、酔っ払ってご機嫌の4人が手をつなぎながら、港の遊歩道を楽しそうにヘラヘラ歩いていく姿を後ろから撮っているんです。時々、船の汽笛の音に振り返る人もいたりして。みんな、自分たちがいずれ捕まることは心のどこかでわかっていて、これが最初で最後の旅行なんだ…と思っている感じが伝わってきて、すごくグッときました」。
独り身の高齢者の厳しい生活という、日本でも変わらぬ社会的なテーマを扱っていても、その語り口はどこまでもポジティブで軽やか。「夫もいないし、残り少ない人生だし、もう、やっちゃおうか!という、彼女たちのたくましさがおもしろかった。自由なおばあさんたちから元気をもらえる映画です」。
■「精神的に自立していない思春期に、近すぎる関係になってしまうことの危うさ」(『呼吸―友情と破壊』)
3本目は、『イングロリアス・バスターズ』(09)、『複製された男』(13)などで女優としても活躍するメラニー・ロランが、自身とほぼ同世代の作家で“第二のサガン”と評されたアンヌ=ソフィ・ブラムスの17歳の時のデビュー作「深く息を吸って」を自ら監督として映画化した青春ドラマ『呼吸―友情と破壊』(14)。主人公の女子高生2人を演じたジョセフィーヌ・ジャピとルー・ドゥ・ラージュは、本作でそれぞれセザール賞有望若手女優賞、セザール賞最優秀女優賞にノミネートされるなど、その演技を高く評価された。
17歳のシャルリ(ジャピ)はまじめで内向的、友人に恵まれている一方で、どこか孤独を感じていた。そんなある日、サラ(ラージュ)という美しい転校生がやって来る。個性的でカリスマ性のあるサラは、なぜかシャルリを気に入り、2人は急接近。親しくなるにつれ、奔放なサラにどんどん惹かれていくシャルリだったが、いつしかその関係に綻びが生じ始める。シャルリが失われた友情を取り戻そうとすればするほど、サラの冷酷さはエスカレートしていく。
「精神的にまだ自立していない、自分と他人との境界がそんなにはっきりしていない思春期に、2人きりという近すぎる関係になってしまうことの危うさが描かれている作品でした。そういう時期に急激に仲良くなる女の子2人って、ずっと仲良いままではいなかったりするじゃないですか。普遍的な話だと思いつつ、その関係性がすごくリアルでしたね。観ていてヒリヒリ感を覚えるのは、きっと監督であるメラニー・ロランに、この物語を描かなきゃいけない!という切実さがあったからだと思います」。
ゆっきゅんは「2人の関係が変容するきっかけの一つ」として、サラに秘密があると感じたシャルリが、夜に帰宅する彼女をこっそり尾行し、家を覗いてしまったことを挙げる。「母親はNPO職員で海外にいる。自分は叔母と生活している」と周囲に語っていたサラの嘘が明らかになる描写だ。「サラが家に入ってから、カメラが横にゆっくりと移動していくショットはインパクトがありました。その直前にサラが学校で“サファリ”の話をしていたこともあって、まるで夜のサファリパークを見ているような感じがして。家の中には獰猛な母がいて、部屋の窓の柵は檻みたいに見えたんです。しかも、壁の外の暗闇にシャルリが静かに立っているっていう…青春ドラマから心理サスペンスへと切り替わった瞬間でした」。
終盤になってくると、様々なシーンで、キーンと響く耳鳴りのような音響が入っているのも印象的。「本当に自分の耳鳴りかと思っちゃうくらい。シャルリが感じているものが、観ているこちらの身体にも浸透してくる感覚でした。画面全体にあふれる、出口のない、切迫しているムードがすごいなと思いましたね。シャルリに喘息の持病があるという設定も効いていて、タイトルどおり、息が詰まるようなシーンが何度もありました」。
■「レポートの課題でBunkamuraル・シネマに行ったのが、フランス映画を劇場で観る初めての経験」
高校生の時から、音楽や美術、映画が好きで、「作品に触れた感動や自分の感性の部分を言語化できるようになりたいという想いから、映画評論家の方がいる大学だけを受験しました」と語るゆっきゅん。青山学院大学文学部比較芸術学科に進学したあとは、映画批評家の三浦哲哉のゼミに入り、映画監督の山戸結希をテーマに卒論を執筆。その後、進んだ大学院での修士論文では“少女マンガ実写化映画の変遷”をテーマにしたという。
そんなゆっきゅんに映画の原体験について尋ねると、「小学3年生の時に映画館で観た『下妻物語』です」との答えが返ってきた。「それ以降、実家のわりと近くにあった岡山県唯一のミニシアターに母親を連れて行く形で、いろんな映画を観に通いました。邦画ばっかりでしたけど。あと、oniビジョンという岡山県のケーブルテレビがあって、そこでスターチャンネルや日本映画の専門チャンネルを通して文化享受をしてきましたね」。
大学生になってからは渋谷の映画館を中心に、思う存分、映画鑑賞三昧の日々。「フランス映画に初めてきちんと触れたのも、大学の映画の授業がきっかけでした。まず、クラスみんなでジャン・ルノワール監督の『ピクニック』を観たんです。その後、当時が2014年春だったので、ちょうど公開されていた『アデル、ブルーは熱い色』を観てレポートを書きなさいという課題が出て。『アデル』は過激そうで、ちょっと無理かも…という人は、ジャック・タチ映画祭に行きなさいって(笑)。それで、いまは場所を移転したBunkamuraル・シネマに行ったのが、フランス映画を劇場で観るという初めての経験だった気がします」と、ゆっきゅんは懐かしそうに振り返る。
■「映画や映像と、自分が歌う、表現していくことの関係が年々、密になっている感覚があります」
学生のころから好きなフランスの映画監督はエリック・ロメール。「新文芸坐のオールナイト上映には何回も行きました。ロメールの作品は古さをまったく感じないというか、私にはずっと新鮮に、新しいことに見えます。特に『緑の光線』とか『レネットとミラベル/四つの冒険』が好きですね。いわゆる大作とは違う、ちょっと力を抜いて観られる会話劇で、登場人物たちの人間関係を通して描く“人生のひととき”な感じが好きです」。
音楽活動をしているゆっきゅんは「映画からインスピレーションを受けることも多い」という。「こういう映画みたいな曲を書きたいなと思って歌詞を書いたりもすることもあります。次に出す曲は、一昨年日本で公開されたバーバラ・ローデン監督・脚本・主演の『WANDA/ワンダ』とか、アニエス・ヴァルダ監督の『冬の旅』とか、女性が1人で放浪するような映画にインスパイアされて作ったものなんです。特定の映画じゃなくても、頭のなかに浮かんだ映像を、どう歌に落とし込もうかと考えることも増えてきて。ずっと映画を観てきたので、映画や映像と、自分が歌う、表現していくことの関係が年々、密になっている感覚がありますね」。
■「フランス映画は、わかりやすい大きな1つの答えがもらえるようなものではない」
ここ2~3年、フランス映画は新作というよりも「レトロスペクティブがあまりにも充実しているので、劇場で上映される監督映画特集によく足を運んでいる」とのこと。「サッシャ・ギトリ監督、ジャン・ユスターシュ監督、アルノー・デプレシャン監督、あとフランスじゃなくてベルギーですけど、シャンタル・アケルマン監督の特集上映にも通いました。リバイバルされるだけの価値があるってことだから、レトロスペクティブって信頼してしまうとこがあって。いまの感覚のまま昔の作品を観てもやっぱりおもしろいんですよね。そういう人が増えているみたいです。アケルマン監督特集では、代表作の『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』に比べればマイナーな『一晩中』を平日の夜の回に観に行ったのですが、ほぼ満席だったんです!」。
「フランス映画は、ハリウッド映画みたいにわかりやすい大きな1つの答えがもらえるようなものでは、たぶん、まったくない」と話すゆっきゅん。その代わりに「映画を観たあとに持ち帰った問いが、ずっと心のなかで生き続けたり、人生のとある場面で、これって、あの映画で観たアレだったのかと気づいたり…あとで咲くことが多いと思います。(少し難しいと思っても)肩の力を抜いて、適当にでも、どんどん観ていけばいいんですよ」と笑いながら、ニュアンスに満ちたフランス映画の奥深い魅力を表現してくれた。
スターチャンネルEXの「Gaumont(ゴーモン)」セレクションでは、「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン」誌元編集委員でアンスティチュ・フランセの映画プログラム主任を務める坂本安美が作品セレクトを担当。ここで紹介した3作品のほか、ヴァレリー・ルメルシエが監督・脚本・主演を兼任した『愛しのプリンセスが死んだワケ』(05)やフランスを代表する名匠サッシャ・ギトリの『これで三度目』(52)、モーリス・ピアラ監督の長編デビュー作『裸の幼年時代』(68)といった日本初公開作品を含むバラエティに富んだ、見逃せない注目作がずらりと並んでいる。この機会に気になる作品をチェックして、フランス映画のおもしろさをぜひ体感してみてほしい。
取材・文/石塚圭子
【関連記事】
・ 「おしん」「渡鬼」泉ピン子が英国の伝説女優に重ねた生き様「長くドラマを続けていくというのは大変なこと」
・ あなたはどのマッツが好き?情けない中年男に、やさぐれ医師、裏社会のスキンヘッド…“北欧の至宝”マッツ・ミケルセンに魅せられる10選
・ ダイアナ元妃が語り継がれるプリンセスである理由は“不幸な美しさ”?チャールズ国王の後輩、ハリー杉山が語る英国の王室事情
・ 知られざる生々しい実像に、その輝きの根源を知る…ファン必見の映画『オードリー・ヘプバーン』を解説
・ パリ留学中の和田彩花が語るフランス映画の醍醐味「作られた場所の文化や歴史、作り手のルーツなどが組み合わさっている」